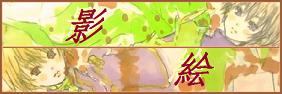□
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
こちらは、自作小説「Xylophone」の原稿置き場です。
Xylophoneとは木琴です。
このお話を思いついたとき、タイトルを木琴にしようか鉄琴にしようか非常に悩んだ覚えがあります(笑)
ただ、この物語は、森をテーマというかモチーフにしていて、緑のイメージで構想したものだったので、木琴の方を取りました。
また、ブログ名は、文法を間違えているかもしれませんが、「木琴で奏でるグレゴリオ聖歌」、みたいな感じです。
この物語を思いついたのは、サラ=ブライトマンさんの「エデン」というアルバムに収録されている「エデン」という曲の前奏で、グレゴリオ聖歌風の歌声が流れるのですが、それを聴いた時でした。ふわあっと情景が浮かんできて、まず緑の中を白い馬の群れが走っていました。よく見たらどうも一角獣だったみたいなんですが、とにかく、ニンフのようなものとか、よく知らないような幻想的な世界が思い浮かんできて、この世界を物語にできたら、と思ってメモに残しておいたまま今に至ります。
本当は、「グレゴリア」と題名をつけようかと悩んでいたのですが、当初の予定通りで行こうと思いました。
書きたい物語は実を言うとまだ30個以上残っていて、いつ消化できるのやらという感じなんですが、これを先にまわそうと思ったのは、主要人物が比較的少ないからです(笑)
今連載している別の小説「Ourselves」というものが、主要人物を限りなく増やしたせいでとんでもないことになっておりまして、とても、その小説を考えながらほかのキャラを動かすのは無理だと判断いたしました。けれど、同じ物語ばかり書いていると浮気心も出てくるもので、実際にかけるかどうかはわからないのですがブログだけでも立ち上げました。
まずは「Ourselves」を完結させるほうが先決だし、片手間にやると絶対に満足のいくものがかけないと思うので、本格的に書くのは先のことになるかもしれませんが、もともと思いつきで文章を書く質ですし、もしふわっと浮かんだら忘れないうちにここに書き留めておこうと思います。
登場人物、及びあらすじについてはおいおい、こちらの概説の記事で追記していく予定です。
ではもう一度、改めまして、紺色仔扉と申します。
現在、「青硝子ノ山羊ノ子」というブログ名で、小説「Ourselves」を連載しております。こちらがある程度の目処がつくまで、ほかの物語を書くペースは非常に遅くなると思うのですが、続けていくつもりですのでどうぞよろしくお願いいたします。詳しくは、管理人の本館「寄木仔鹿」でご確認ください。リンクのバナーから入れるようにしております。
登場人物についての説明は、小説の内容がある程度進んだらきちんとまとめたいと思います。
とりあえず今は、主要人物の名前だけあげておきます。
以下はこの物語のイメージ曲「エデン」です。動画サイトがここしかなかったけど音質悪いなあ・・・http://www.dailymotion.com/video/x13k5z_sarah-brightman-eden_music
Xylophoneとは木琴です。
このお話を思いついたとき、タイトルを木琴にしようか鉄琴にしようか非常に悩んだ覚えがあります(笑)
ただ、この物語は、森をテーマというかモチーフにしていて、緑のイメージで構想したものだったので、木琴の方を取りました。
また、ブログ名は、文法を間違えているかもしれませんが、「木琴で奏でるグレゴリオ聖歌」、みたいな感じです。
この物語を思いついたのは、サラ=ブライトマンさんの「エデン」というアルバムに収録されている「エデン」という曲の前奏で、グレゴリオ聖歌風の歌声が流れるのですが、それを聴いた時でした。ふわあっと情景が浮かんできて、まず緑の中を白い馬の群れが走っていました。よく見たらどうも一角獣だったみたいなんですが、とにかく、ニンフのようなものとか、よく知らないような幻想的な世界が思い浮かんできて、この世界を物語にできたら、と思ってメモに残しておいたまま今に至ります。
本当は、「グレゴリア」と題名をつけようかと悩んでいたのですが、当初の予定通りで行こうと思いました。
書きたい物語は実を言うとまだ30個以上残っていて、いつ消化できるのやらという感じなんですが、これを先にまわそうと思ったのは、主要人物が比較的少ないからです(笑)
今連載している別の小説「Ourselves」というものが、主要人物を限りなく増やしたせいでとんでもないことになっておりまして、とても、その小説を考えながらほかのキャラを動かすのは無理だと判断いたしました。けれど、同じ物語ばかり書いていると浮気心も出てくるもので、実際にかけるかどうかはわからないのですがブログだけでも立ち上げました。
まずは「Ourselves」を完結させるほうが先決だし、片手間にやると絶対に満足のいくものがかけないと思うので、本格的に書くのは先のことになるかもしれませんが、もともと思いつきで文章を書く質ですし、もしふわっと浮かんだら忘れないうちにここに書き留めておこうと思います。
登場人物、及びあらすじについてはおいおい、こちらの概説の記事で追記していく予定です。
ではもう一度、改めまして、紺色仔扉と申します。
現在、「青硝子ノ山羊ノ子」というブログ名で、小説「Ourselves」を連載しております。こちらがある程度の目処がつくまで、ほかの物語を書くペースは非常に遅くなると思うのですが、続けていくつもりですのでどうぞよろしくお願いいたします。詳しくは、管理人の本館「寄木仔鹿」でご確認ください。リンクのバナーから入れるようにしております。
登場人物についての説明は、小説の内容がある程度進んだらきちんとまとめたいと思います。
とりあえず今は、主要人物の名前だけあげておきます。
以下はこの物語のイメージ曲「エデン」です。動画サイトがここしかなかったけど音質悪いなあ・・・http://www.dailymotion.com/video/x13k5z_sarah-brightman-eden_music
PR
Xylophone
おとぎばなし
昔々、世界にはそれは美しい双人の女神がいらっしゃいました。
姉の名をテレサ、妹の名をクレア、といいました。
テレサは美しい翼を持ち、空の住人たちに愛されました。
たくさんの鳥たちが、彼女をお嫁さんにしたいと願いました。
テレサはしかし、決して誰のお嫁さんにもなりませんでした。
テレサは空を愛していたのです。
いつしかテレサは、空という彼に恋い焦がれ、地上から去って行きました。
より近くで、彼を感じていられるように、空の中に生きました。
彼女を追って、たくさんの鳥たちが、木の上から空へと住まいを移しました。
誰もがテレサの気を引くために、きらびやかな巣を作り、美しい花束を携えてきました。
けれど、テレサは熱に浮かされたように、空にばかり目を向けていました。
彼女にとっては、周りの鳥達が、何をしていようが、何の興味もなかったのです。
妹のクレアは、美しくない娘でしたが、とてもかしこく、働き者でした。
彼女の働きぶりに、地上の人々は惹かれ、やがて彼女の周りに住まいを移しました。
クレアとクレアに惹かれた者たちは、少しずつ大地をならし、花を植え、美しい街を作っていったのです。
ところがある時、空から太陽が消えてしまいました。
空は真っ暗な闇に覆われ、作物は育たず、生き物たちは皆死んで行きました。
クレアは空を見上げ、ようやくあることに気がつきました。
太陽が消えたのではなく、太陽を覆い隠すものが、空の上に生まれてしまっていたのです。
これこそが、テレサの周りに作られた空の街でした。
鳥たちはテレサのために街を作るのに夢中で、地上に光が射さなくなることなど、どうでもよかったのです。
あいかわらず、テレサは空ばかりを見上げ、何も顧みませんでした。
クレアは怒り、空への階段を上り終わると、テレサの目を潰してしまいました。
テレサは、美しかったその瞳を、失ってしまいました。
それに怒った鳥たちは、地上を滅ぼそうと、空から飛び降りてきました。
けれど、巣を作るばかりで、他に何もしてこなかった鳥達は、地上の人間達に捕まり、焼いて食べられてしまいます。
鳥たちは、地上へ攻め入ることを、諦めました。
やがて月日がたち、地上は流行り病に襲われました。
人々も家畜も、次々と死んで行きました。
人々は、かつて交わりを絶った、空の国に逃げようとしました。
鳥たちの国は相変わらず美しく、病などに侵されはしなかったからです。
鳥たちは決して、ただでは人々を招きいれようとはしませんでした。
代わりに、クレアの両目を求めました。
人々はクレアの両目を差し出しました。
けれど鳥たちは、クレアの両目をテレサに返したのち、扉を閉ざしました。
【罪深く醜い生き物は、テレサには似合わない】
鳥たちはようやく、世界の支配者となったのです。
鳥たちがもしもまた、空を閉ざしてしまうなら、今度こそ人々になすすべはありませんでした。
人々は鳥にかしずくことを誓いました。
鳥たちは人の行いを許し、太陽の見える空と、病を治す薬を与えました。
人はようやく、【美しさ】を手に入れることとなりました。
「怖いよ、おかあさん」
年端のいかない稚児がぐずりだす。
古くから伝わる童話を語って聞かせていた母親は、苦笑しながらその子を抱き抱えた。
抱かれた子供より少し大人びた子供は、むっとしたまま母親に言った。
「やっぱりそのお話、何かが変だよ、おかあさん」
「そうね、わたしも子供のころはそう思ったけれど」
母親は子供たちの翼を優しく撫でる。
「けれど、大人になったら、その感覚はなくなってしまったわ。これはね、美しさを捨ててはいけないという教訓なのよ。私たちはみな等しく美しいけれど、それを失ったら、かつての【人】と同類。【鳥】である私たちは決して誇りを失ってはならないし、美しさを捨ててはだめよ」
母親は優しい声で言った。
「奇妙なことだね」
母子の会話を耳にした、通りすがりの青年はくすりと笑った。
「驚いた。救いようのない、と思っていた彼らでも、その子供はちゃんとまともな【感覚】とやらを持って生まれては来るものらしい」
青年はくつくつと喉を鳴らしながら家路へとつく。
「まあどうせ、その【本能】とやらも時が過ぎれば失われてしまうみたいだけれど」
美しさ美しさと狂ったように唱える彼らは等しく、
実は既にその美しさを失っていることに気づかない。
もともと持ってすらいなかったことにも気付かない。
「よくまあ、事実をあそこまで捻じ曲げられるなあ」
青年は白い玉座に腰かけると、嘆息した。
「童話って言うのは、少なかれ事実を脚色したものであるはずなのに、かけらも残っていないなんて」
青年の肩に止まった青い燕がキィキ、と鳴く。青年はその頭を指でそっと撫でて柔らかく笑った。
「まあ・・・あたってる部分なんてただのひとつだけ・・・かな。どうでもいいけど」
青年は、ふう、と長い溜息をついて、深く椅子に身をうずめた。
「ああ・・・まだかなあ。もう、僕ずっと待ってるんだけどねえ」
今日も、まだ【知らせ】は来ない。
彼はずっと待っていた。気が遠くなるような長い時間を。
正直、何度【止めようか】と思ったか覚えていない。それでも、どうしても、願わずにはいられなかった。そのためだけに生きたのだ。今まで、生きてきているのだ。
「童話、ね。せいぜい広めるがいいさ。僕は何にも手助けしない。【美しい】嘘に侵されているがいい。最期に鳴いてすがるがいいよ。僕の望みはそれだけだもの」
ふと、目の前に飛んできた小さな虫を、燕が素早くついばんだ。
青年は不快そうに笑う。
その目に映る虹色の光が、微かに陰る。
おとぎばなし
昔々、世界にはそれは美しい双人の女神がいらっしゃいました。
姉の名をテレサ、妹の名をクレア、といいました。
テレサは美しい翼を持ち、空の住人たちに愛されました。
たくさんの鳥たちが、彼女をお嫁さんにしたいと願いました。
テレサはしかし、決して誰のお嫁さんにもなりませんでした。
テレサは空を愛していたのです。
いつしかテレサは、空という彼に恋い焦がれ、地上から去って行きました。
より近くで、彼を感じていられるように、空の中に生きました。
彼女を追って、たくさんの鳥たちが、木の上から空へと住まいを移しました。
誰もがテレサの気を引くために、きらびやかな巣を作り、美しい花束を携えてきました。
けれど、テレサは熱に浮かされたように、空にばかり目を向けていました。
彼女にとっては、周りの鳥達が、何をしていようが、何の興味もなかったのです。
妹のクレアは、美しくない娘でしたが、とてもかしこく、働き者でした。
彼女の働きぶりに、地上の人々は惹かれ、やがて彼女の周りに住まいを移しました。
クレアとクレアに惹かれた者たちは、少しずつ大地をならし、花を植え、美しい街を作っていったのです。
ところがある時、空から太陽が消えてしまいました。
空は真っ暗な闇に覆われ、作物は育たず、生き物たちは皆死んで行きました。
クレアは空を見上げ、ようやくあることに気がつきました。
太陽が消えたのではなく、太陽を覆い隠すものが、空の上に生まれてしまっていたのです。
これこそが、テレサの周りに作られた空の街でした。
鳥たちはテレサのために街を作るのに夢中で、地上に光が射さなくなることなど、どうでもよかったのです。
あいかわらず、テレサは空ばかりを見上げ、何も顧みませんでした。
クレアは怒り、空への階段を上り終わると、テレサの目を潰してしまいました。
テレサは、美しかったその瞳を、失ってしまいました。
それに怒った鳥たちは、地上を滅ぼそうと、空から飛び降りてきました。
けれど、巣を作るばかりで、他に何もしてこなかった鳥達は、地上の人間達に捕まり、焼いて食べられてしまいます。
鳥たちは、地上へ攻め入ることを、諦めました。
やがて月日がたち、地上は流行り病に襲われました。
人々も家畜も、次々と死んで行きました。
人々は、かつて交わりを絶った、空の国に逃げようとしました。
鳥たちの国は相変わらず美しく、病などに侵されはしなかったからです。
鳥たちは決して、ただでは人々を招きいれようとはしませんでした。
代わりに、クレアの両目を求めました。
人々はクレアの両目を差し出しました。
けれど鳥たちは、クレアの両目をテレサに返したのち、扉を閉ざしました。
【罪深く醜い生き物は、テレサには似合わない】
鳥たちはようやく、世界の支配者となったのです。
鳥たちがもしもまた、空を閉ざしてしまうなら、今度こそ人々になすすべはありませんでした。
人々は鳥にかしずくことを誓いました。
鳥たちは人の行いを許し、太陽の見える空と、病を治す薬を与えました。
人はようやく、【美しさ】を手に入れることとなりました。
「怖いよ、おかあさん」
年端のいかない稚児がぐずりだす。
古くから伝わる童話を語って聞かせていた母親は、苦笑しながらその子を抱き抱えた。
抱かれた子供より少し大人びた子供は、むっとしたまま母親に言った。
「やっぱりそのお話、何かが変だよ、おかあさん」
「そうね、わたしも子供のころはそう思ったけれど」
母親は子供たちの翼を優しく撫でる。
「けれど、大人になったら、その感覚はなくなってしまったわ。これはね、美しさを捨ててはいけないという教訓なのよ。私たちはみな等しく美しいけれど、それを失ったら、かつての【人】と同類。【鳥】である私たちは決して誇りを失ってはならないし、美しさを捨ててはだめよ」
母親は優しい声で言った。
「奇妙なことだね」
母子の会話を耳にした、通りすがりの青年はくすりと笑った。
「驚いた。救いようのない、と思っていた彼らでも、その子供はちゃんとまともな【感覚】とやらを持って生まれては来るものらしい」
青年はくつくつと喉を鳴らしながら家路へとつく。
「まあどうせ、その【本能】とやらも時が過ぎれば失われてしまうみたいだけれど」
美しさ美しさと狂ったように唱える彼らは等しく、
実は既にその美しさを失っていることに気づかない。
もともと持ってすらいなかったことにも気付かない。
「よくまあ、事実をあそこまで捻じ曲げられるなあ」
青年は白い玉座に腰かけると、嘆息した。
「童話って言うのは、少なかれ事実を脚色したものであるはずなのに、かけらも残っていないなんて」
青年の肩に止まった青い燕がキィキ、と鳴く。青年はその頭を指でそっと撫でて柔らかく笑った。
「まあ・・・あたってる部分なんてただのひとつだけ・・・かな。どうでもいいけど」
青年は、ふう、と長い溜息をついて、深く椅子に身をうずめた。
「ああ・・・まだかなあ。もう、僕ずっと待ってるんだけどねえ」
今日も、まだ【知らせ】は来ない。
彼はずっと待っていた。気が遠くなるような長い時間を。
正直、何度【止めようか】と思ったか覚えていない。それでも、どうしても、願わずにはいられなかった。そのためだけに生きたのだ。今まで、生きてきているのだ。
「童話、ね。せいぜい広めるがいいさ。僕は何にも手助けしない。【美しい】嘘に侵されているがいい。最期に鳴いてすがるがいいよ。僕の望みはそれだけだもの」
ふと、目の前に飛んできた小さな虫を、燕が素早くついばんだ。
青年は不快そうに笑う。
その目に映る虹色の光が、微かに陰る。
序章
上限の月が浮かんでいる。
空は、真っ黒だった。
少年は、頭巾の下からそっと、空を見上げる。
見つめる先は、うっすらと滲んだ空、月の輪郭の外側だった。
その少年の袖を、もう一人の少年がそっと引く。
二人は再び音も立てずに歩き出す。
黒い光の中に浮かぶ、灰色の城の輪郭の中へ、二人は入って行った。
「ああ、息が詰まる」
少年の一人が、頭を隠していた頭巾をとって、ぶるぶると頭を振った。
不揃いに切られた金髪がふわりと広がる。
先刻空を眺めていた少年もまた、外套を脱いだ。先の少年よりは短めの髪が、さらりと流れる。
「ねえ、ロゼ、ここ教会だったみたいだよ」
「らしいな」
「何それ、そっけないなあまったく」
少年は長く伸びた髪をつまんでいじりながらふくれっ面になる。
「入った瞬間、虹色の光が床に映っていた。どうせいつもどおり薔薇窓でもあるんだろ?」
「いつもどおりっちゃいつもどおり・・・なんだけどさ」
髪の長い少年は静かに呟いた。少年のそういう声は、久し振りに聞く。
「レヴィ?」
ロゼ、と呼ばれた少年がそっと、もう一人の少年の手を取る。レヴィ、と呼ばれた少年は寂しげに笑った。これも久しぶりに見る表情だ。
「ほら、見てよ。こんな絵、僕は初めて見るよ。・・・初めて、見たよ」
教会の薔薇窓というのは大抵、天使だったり、神様だったり、聖母や預言者、聖書に描かれている事柄の絵画が色硝子の工芸として形作られている。そして、少年達は、それがひどく嫌いだった。
―お前達は救われようがない。
そう、言われているような気になるのだ。その無機質で残酷な目の奥で。
けれど、今二人が見ていたそれは、それまでのどれとも違っていた。
緑の髪の少年と、金髪の少女が、寄り添って、目を瞑っている。
二人は小さな赤子を守るようにそっと抱きあげていた。
その赤子の顔は見えない。ただ、布からはみ出た小さな手が見えるだけだ。その手を少年がそっと握っている。
周りは白い水仙の花で囲われている。緑を基調とした硝子。
それは、神々しいわけでも、厳めしいわけでもない。ただ静かで、儚い絵だった。普通の宗教画と比べれば、地味で見劣りがするものかもしれなかった。
それでも、少年たちにとっては、まるで胸を締め付けられるような、美しさがあったのだ。
「あ・・・れ・・・?」
頬を伝うものを感じて、少年は手を頬にあてた。
「ロゼったら・・・何泣いてんのさ」
レヴィ、と呼ばれた少年は苦笑しながら、その涙をぬぐってやる。
「ありがたい、って、こういうことを言うんだろうね」
「え?」
「ほら、見れて良かった、って思うんだよ、この絵なら。僕達がこんなところまで逃げてなきゃ、きっと一生見ることもなかったんだろうね。あんな小さな村でさ、きっとずっと閉じ込められたままだったんだから」
「レヴィ、オーレ」
「僕さ、今更だけど、ううん、今頃やっとだけど、やらなきゃよかったな、って。あはは、自分の罪深さをこんなところでやっと自覚するなんてね。この絵はずるい。ずるいよ」
「レヴィオーレ」
ロゼ、と呼ばれた少年は、レヴィオーレの額に自分の額をそっと当てて目を閉じた。
「なにも考えなくていいから」
ソキツィロゼはふわりとほほ笑む。
「お前が懺悔なんてし出したら、俺がお前を守りたい気持ちまで懺悔しなきゃいけない。そんなの面倒だ。俺はやりたくないからな」
「何それ」
レヴィオーレはようやくくすりと笑う。
「でも、さ」
レヴィオーレは言いかけて、止める。
「なんだよ?」
「ううん、ただ、・・・そうだな、もう少し、ここになら、いてもいいんじゃないかなとか、さ」
「居たいだけ居るがよい」
ふいに、聞き覚えのないしわがれた声が聞こえて、兄弟はさっと身をひるがえし、声のした方を睨みつけた。
人の気配に気づかなかったなんて、不覚だ。今までの自分たちなら絶対にあり得ない。
老婆はすっぽりと布で姿を覆い隠していた。木椅子に溶け込んで、暗がりの中では判別できなかったのだ。
「お前は誰だ」
ソキツィロゼは低い声で問う。
「何、この教会で寝泊まりさせてもらっておる、ただの乞食じゃ」
二人が殺気を放ちながら黙っていると、老婆はくつくつと笑って、ゆっくりと腰を上げ、薔薇窓のそばへとゆっくり歩み寄る。座っても立っても変わりがないほどに、酷く腰が曲がっている。
「儂はこの窓が好きでの」
老婆は優しく言った。
「この絵にまつわる優しい話が好きでの。この教会が好きになってしもうたのじゃ。以来、ここには半分棲みついているようなもの。ここは公式の教会ではないがの」
二人は黙っていた。見も知らぬ他人に簡単に気を許せはしない。
けれど、老婆は返事を待っていた。いつまでも、待っている。
やがて、嘆息とともに、レヴィオーレが、折れた。
「何が言いたいんです?」
老婆はくすりと笑った。
「いや・・・単に年寄りの話につき合うてほしいだけじゃ。なにせ、孫のような年端の子供を見ると、めんこゆくて仕方ないでのう」
老婆は優しく笑った。
「ここの教会はの、巷に出回っている聖書は信じておらぬ。この国にだけ語り継がれる、とある物語だけを信じておる。まるで夢物語じゃ。だが儂も、この国の者たちも、取ってつけたような聖書の物語よりも、ずっと、その話の方が真実味のあるような気がしてならぬ。何千年もの時の中で、歴史は歪んでしまったなれど、儂は【鳥】を天使だの、絶対神だの創造主だの、と人間のちっぽけな想像力でこじつけた神話よりは、語り継がれた童話を信ずるよ。そういう子どもたちが増えると良い」
「童話?」
ソキツィロゼは訝しげにつぶやいた。
「神話が童話?」
「子供に語り聞かせる意味では同じ根っこじゃろうて」
老婆はくつくつと喉を鳴らす。
「あんな小難しゅうて大人でもやっとわかるような話よりは十分に信じられることだよ」
「この薔薇窓に描かれている物語なんですか。水仙の―」
「この国には水仙が咲き誇るでの」
レヴィオーレの問いに、老婆はあいまいな答えを返す。
「レヴィ?」
ぼんやりと薔薇窓を眺める弟の横顔を、ソキツィロゼは不安げに見詰めた。
レヴィオーレは苦笑する。
「聞きたいな」
それは降参したような、か細い声だった。
「いい加減、救われたいな」
逃げるのは疲れたよ、と、レヴィオーレが呟いた気がした。
ソキツィロゼは首を振ると、嘆息した。
老婆はそっと二人に歩み寄り、その頭を背伸びして優しく撫でた。
それは緑の物語。
森緑の果ての、物語―。
第一部
かつて世界は闇に覆われた。
生きるもの全てを飲み込み、その命を奪うそれは、【バベル】と呼ばれた。
夢想都市と呼ばれた世界で最も美しく豊かに栄えた街、アトランティカの地の底から突如湧き起こったそれは、またたく間にアトランティカを飲み込み、周りの海を全て黒に染め上げていった。
その闇に触れた者は等しく、異形へと姿を変え、言葉さえも失い化け物のように甲高い声で鳴いたという。
バベルはヘドロのようであり、霧のようであり、霧雨のようでもあった。
その雨に打たれた者の皮膚は溶け、焼けただれたという。
その霧に包まれた者は気管をやられ、呼吸も能ず眼球を飛びださせもだえ苦しんだ。
空中に拡散するそれは、空をも黒い灰で包み込み、天に住まう命をも奪っていく。
逃げ場などどこにもなかった。
人々は世界の終わりを知った。もはやなす術などない。
これは神の所業だと、誰もが理解した。
【バベル】の真実を知っていた者など、地上、否、アトランティカに住まう一部の者のみであった。そして彼らはその真実を語る間もないまま死を迎える。
全て人間が絶望した頃、バベルの暴走はぴたりと止んだ。
【バベル】を【閉じた】のは、たった一人の少年だった。
少年は天に住まう【鳥】と呼ばれる種族の出で、見たこともないほどに美しかった。
人々は、彼と比べ、己がどれだけ不細工にできているかを思い知った。
バベルなど起こらずとも、彼らは少年の美しさに叶いなどしない。
少年は英雄と崇められた。少年を生み出した【鳥】の一族は、殿上人、【アルクメネ】と讃えられるようになり、やがて世界の支配階級となって行った。
かつての地上人は【ウィルド】と呼ばれ、金字塔状に身分階級が形成されるようになる。
ウィルドの中でも上位の者は、天上に上ることを許され、アルクメネとして出世した。
アルクメネの役割は即ち、【天啓グリーグの意思を世に伝えること】である。
グリーグとは、かつて世界をバベルから救った少年の名であった。
やがてグリーグもその天命を終え、アルクメネは符号化された【グリーグ】より意思を賜るようになった。
符号化されたそれは、厳密にはグリーグ自身とは言えないが、それでも人々を導く素晴らしい知恵を携えていた。
しかしアルクメネは気づいていた。
グリーグその人が死んでからというもの、世界に異変が起きている。
グリーグによってもたらされた均衡は崩れていた。
なぜなら世界各地で、【異形の化け物】が見られるようになっていたのだ―
かつて世界は闇に覆われた。
生きるもの全てを飲み込み、その命を奪うそれは、【バベル】と呼ばれた。
夢想都市と呼ばれた世界で最も美しく豊かに栄えた街、アトランティカの地の底から突如湧き起こったそれは、またたく間にアトランティカを飲み込み、周りの海を全て黒に染め上げていった。
その闇に触れた者は等しく、異形へと姿を変え、言葉さえも失い化け物のように甲高い声で鳴いたという。
バベルはヘドロのようであり、霧のようであり、霧雨のようでもあった。
その雨に打たれた者の皮膚は溶け、焼けただれたという。
その霧に包まれた者は気管をやられ、呼吸も能ず眼球を飛びださせもだえ苦しんだ。
空中に拡散するそれは、空をも黒い灰で包み込み、天に住まう命をも奪っていく。
逃げ場などどこにもなかった。
人々は世界の終わりを知った。もはやなす術などない。
これは神の所業だと、誰もが理解した。
【バベル】の真実を知っていた者など、地上、否、アトランティカに住まう一部の者のみであった。そして彼らはその真実を語る間もないまま死を迎える。
全て人間が絶望した頃、バベルの暴走はぴたりと止んだ。
【バベル】を【閉じた】のは、たった一人の少年だった。
少年は天に住まう【鳥】と呼ばれる種族の出で、見たこともないほどに美しかった。
人々は、彼と比べ、己がどれだけ不細工にできているかを思い知った。
バベルなど起こらずとも、彼らは少年の美しさに叶いなどしない。
少年は英雄と崇められた。少年を生み出した【鳥】の一族は、殿上人、【アルクメネ】と讃えられるようになり、やがて世界の支配階級となって行った。
かつての地上人は【ウィルド】と呼ばれ、金字塔状に身分階級が形成されるようになる。
ウィルドの中でも上位の者は、天上に上ることを許され、アルクメネとして出世した。
アルクメネの役割は即ち、【天啓グリーグの意思を世に伝えること】である。
グリーグとは、かつて世界をバベルから救った少年の名であった。
やがてグリーグもその天命を終え、アルクメネは符号化された【グリーグ】より意思を賜るようになった。
符号化されたそれは、厳密にはグリーグ自身とは言えないが、それでも人々を導く素晴らしい知恵を携えていた。
しかしアルクメネは気づいていた。
グリーグその人が死んでからというもの、世界に異変が起きている。
グリーグによってもたらされた均衡は崩れていた。
なぜなら世界各地で、【異形の化け物】が見られるようになっていたのだ―
第一章
テレサと呼ばれる天上の地。
その森林の奥に、金字塔型の金色の符号模型があった。
それは【天啓グリーグ】のおはします社である。
この中に入ることを許されているのは限られたアルクメネであった。
扉の前、彼らは皆、その手首につけた金色の輪で認証を行う。
この輪は、天啓グリーグの符号がわずかに施されている。
社に入ることができるのは、グリーグの符号をその身に宿した者のみであった。
そうしなければ、かつての地上、【クレア】の技術に半分も及ばないテレサの技術上、微妙な釣り合いの下に保たれている天啓グリーグの残像は、消えてしまう恐れがあった。
グリーグの知恵なしにこの世界は成り立たない。
グリーグの残像が消えてなくなることこそ、アルクメネの最も恐れていることであった。
社に近づく3人の影がある。
彼らは認証を行い、中へと足を踏み入れた。
一人は腰が曲がった老成した翁であり、
一人は非常に若く、もう一人は体の大きい中年の男である。
彼らは翠玉の薄い正方形の瓦が敷き詰められた回廊を歩いていく。
靴底が、鉄琴のような音を奏でていた。
回廊を渡りきり、大理石でできた鳥居をくぐると、金と緑の糸で編まれた薄い暖簾の奥に、白い光が見える。
その白い光―【玉座】にこそ、天啓グリーグは眠っていた。
およそこの世のすべての緑という色を薄くにじませたような美しい髪。
年をとっても変わらず容色の衰えなかった彼の姿は、符号と言えど酷く美しい。
これぞまさに神に遣わされた寵児、否、誰もが彼こそが神であると信じて疑わなかった。
グリーグは眼をこすり、伸びをした。その気だるげな仕草でさえ艶めかしい。
『ああ、来たね。どうしたの?』
グリーグの声は、琴のように耳に心地よい。
「は」
翁は首を垂れる。
「以前から申し上げていた異形の件でございます」
『ああ、あれね。それで?原因はわかったのかな。君達はそろいもそろって、一向に重い腰を上げようとしないから・・・こういうことこそ迅速に対応しなければ取り返しのつかないことになるでしょう?目は覚めたの?』
「はい。その件ですが、その・・・非常に遺憾なことでありますが・・・調べた結果―」
『ああうっとうしい』
グリーグは天を仰いだ。
『もういいや。そこの・・・えっと、キシュキ、だったかな。君が言ってごらん。これも勉強だよ』
「えっ」
名を呼ばれた金髪の少年は、肩を跳ねさせた。胡桃色の瞳が揺れている。少年は黒髪の中年の男を窺った。男は嘆息する。
「グリーグ殿。こいつは能力はずば抜けて高いが、ここぞという時にすぐ腰が引けましてな。だからこそ慣らすためにこうして連れてきてやっているのですが・・・申し訳ない」
グリーグはくすりと笑った。
『ほんとにねえ。今のアルクメネ達が死んでしまったら、次は君達がここを背負っていかなければならないのに、そんなことでどうするのかな。まあいいや。じゃああなたが説明してくれる?』
男は豪快に笑った。
「グリーグ様はなかなかにせっかちな方でございますな」
「こ、これ・・・!!」
翁が慌てる。男のこういう遠慮のない物言いやきっぷの良さが、グリーグは気に入っているらしかった。だからこそ、他の老アルクメネを差し置いてこの男が重用されているのだ。正直少年はおまけのようなものだった。
「私はやはり年長を敬いたい。デバーラ殿に敬意を」
男が言うと、グリーグはつまらなさそうに肩をすくめ、デバーラ翁に向き直った。
『ああごめんね、ついからかいたくなっちゃってさ。お話続けていいよ。ご老人は嫌いじゃないんだ。むしろ好き』
翁は慌てたように身を小さくした。
「も、もったいなきお言葉であります」
実際の年齢を考えれば、翁よりもグリーグの方が年上になる。翁がびくびくするのも無理はないのだろうと黒髪の男は思いやった。この翁は生前のグリーグをも見てきたのだ。符号でさえこれほどに美しいのだから、実物は気圧されるほどだったろう。
「異形の件でありますが、やはり、【バベル】の扉がわずかに開いているようであります。隙間、割れ目ほどのものであろうと推測いたしましたが、既にこれだけの化け物が確認されている現状、これ以上バベルが開くことがあればこの世界はそう長くは持ちますまい。一刻も早く、まだ綻びの小さき段階でバベルを再び閉じてしまわねばなりません」
グリーグは頬杖をついて嘆息した。
『だろうと思ったよ。それで?バベルが開いてしまった原因はわかったの?』
「いえ・・・それが・・・さっぱり」
『困ったねえ』
グリーグは口元を手で覆って、うーん、と唸った。
『普通だったら開くはずはないんだけどなあ・・・それとも最初に閉じた時に何か見落としでもあったかなあ・・・でもそれを知るためにはもう一度中をのぞく必要がありそうだし』
「そ、そんなことをしたら世界が飲み込まれてしまいます」
少年が慌てたように口走り、はっとして口を押さえると顔を真っ赤に染めた。
グリーグは苦笑する。
『もちろん、そんなことわかってるよ。危険性の方が高すぎる。だから外側から攻めなきゃいけないよねえ。困った困った』
「グリーグ様にもなす術はないのですか」
翁が絶望したように言う。
「我々はこのまま先延ばしにされた破滅を待てと」
『やだなぁ、違うよ。そういうことは言ってないよ。ただね、ほら、今の僕はただの符号であって本物じゃない。実態を持たない。本物と比べれば発想力や思考力は格段に劣るし、直接何かをできるわけじゃあないんだよ』
三人は息をのんだ。グリーグの符号はあまりにもよくできていて、本人であるという錯覚に捕われていたのだ。まさか符号の口から【本体とは別物だ】と聞かされることになるなど、誰が想像するだろう。
『うーん・・・結局さ、僕が行かないと何にも把握すらできないんだよねえ。困った困った』
グリーグはなぜか楽しげに笑った。そして徐に空を仰ぎ、ぱちん、と指を鳴らす。
グリーグの指先に、青い燕が止まった。グリーグはその目を見つめる。
やがて燕は森の中に消えた。
「今のは・・・?」
少年が独り言つと、グリーグはにっこりと笑った。
『僕のたった一人のお友達だよ』
少年が面くらっていると、燕はややあって、舞い戻ってきた。
足で、とても美しい絹布のようなものを引きずっている。
およそ全ての色の絵具をにじませたような美しいそれは、【鳥】の翼だった。
「翼・・・?これが、翼!?」
少年は驚愕する。
【鳥】とよばれる種族のもつ翼であれば、それは等しく鷲のような、梟のような、鳥類の翼の大型のものであった。だというのに、燕が携えてきたそれは明らかに翼らしくなく、それでいて神と言うものに翼があるなればかくやありき、と思わせる幻想を孕んでいる。
「これがグリーグ様の翼じゃ」
翁は少年に向かって優しく言った。
「ほれぼれするじゃろう」
「これが・・・」
黒髪の男もようやくそれだけを言った。
翁はほほ笑む。
「もう片方の翼は残していらっしゃったのですな」
『うん、こんなこともあろうかと思ってね。僕の羽は酷く繊細だし、本体から切り離した状態では、管理を誤れば腐らないとも限らない。だから勝手に僕が独断で場所を決めて保存していたんだ。場所を内緒にしていてごめんね』
「いえ。我々はグリーグ様のなさることに口出しなどするつもりもございませんよ」
翁はほほ笑む。
「して、その翼を今度は何にお使いになるのですか」
「あのう・・・」
少年がおずおずと口を挟む。
「もう片方の翼は、どうなさったんですか?」
『気になる?』
「え?あ、や、その」
グリーグはにっこりとわらって指で自分の頭をとんとん、と突いた。
『こ、れ。この符号、僕の片翼を媒介にして作られたものなんだよ。だからこうして長年符号が保たれているの』
少年は顔を真っ赤にした。興奮すると顔が紅潮するのだ。
「す、すごい技術だ・・・」
「落ち着け」
黒髪の男が小声で言って嘆息する。
『本当はやりたくなかったけれどね。僕はこの世に生まれ変わろうと思うよ』
「は?」
翁が声を漏らした。
「ど、どういう意味でございますか」
『この世の者は等しく皆死してもう一度この世に生まれ変わり、循環していく。それが世の理。だけど僕は一度も転生できていない。なぜかわかる?』
グリーグはにっこりとほほ笑んだ。
『【僕】を構成する要素が一部欠けた状態だからだよ。ほら、この翼』
グリーグは己の翼を撫でた。
『逆にいえば、こうして翼だけ別に保管しておけば、僕は生まれ変われない。つまり、こうして【グリーグ】としてずっと居られる。もし転生してもその僕が今のグリーグである僕の記憶を有して生まれてこれる可能性はほぼないに等しいんだ。それはとても危険なことだった。だって、君達世界は【グリーグ】の記憶を必要としているでしょう?』
グリーグは苦笑する。
『けれど、こうなってしまった以上、やはり僕自身が現場に行かなければいけないみたいだ。僕はそのわずかな可能性に欠けてみるよ。このまま僕の符号は残しておくといい。そうすれば仮に僕の転生が記憶を持たずとも、僕の知識を与えてやることは後からでも可能だ。この翼を今から空に還すよ。そうすれば僕の生まれ変わりがこの世界のどこかに生まれるだろう。ただしその子は不完全な子だ。もう片翼がない状態で無理矢理生まれてくる子だからね。その子が生まれて、知覚ができる年齢になった頃、』
グリーグはまっすぐに三人の目を見つめた。
『【この僕】を消してほしい。デバーラ、あなたならやり方はわかるね?今ここにいる二人に教えておきなさい。あなたはもう年だから、その頃まで元気でいてくださればいいけれど、万が一ということもある』
「御意にございます」
翁は首を垂れた。黒髪の男はふと、顎をさすりながら何事かを考える。
「グリーグ殿。そのやり方であれば今までも御身の転生を作ることは可能でしたな?なぜ今までやらなかったのです」
『言ったでしょう?生まれてくる子は不完全な子、だって。僕の予想では恐らく、力の制御ができないままに生まれてくる。僕の力は、自分で言うのもなんだけど、結構すごいからね。だからどうしても、この符号に用いた翼も必要になってくる。けれどその時、【グリーグ】は消える』
男は息を呑んだ。
「他に・・・方法はないのですか」
『君達は【バベル】を目にしたことがないから、そんな悠長なことが言っていられるんだよ』
少年は俯いた。
「確かに・・・文献に記載されている状況を想像するだけでも恐ろしいです。きっと現実はもっと酷い」
『僕自身が生きていればもっと酷い状況でもバベルを封印するくらい楽だったんだけどねえ』
グリーグから表情が消える。何かを考えているようだった。
『生まれ変わってくる子も僕そのものじゃないからね。君達が育てるといいよ。【英雄】になれるように、ね』
グリーグは寂しげに笑った。
少年は顔をあげて、グリーグを見た。他の二人は俯いている。グリーグの目が一瞬、笑っていないように見えた気がして、少年は少し身震いをした。けれどグリーグの符号は、とても神々しい。自分はただ、気圧されただけなのだと思った。グリーグの翼は日の光を鈍く反射してまるで銀河のようだ。
一、
テレサと呼ばれる天上の地。
その森林の奥に、金字塔型の金色の符号模型があった。
それは【天啓グリーグ】のおはします社である。
この中に入ることを許されているのは限られたアルクメネであった。
扉の前、彼らは皆、その手首につけた金色の輪で認証を行う。
この輪は、天啓グリーグの符号がわずかに施されている。
社に入ることができるのは、グリーグの符号をその身に宿した者のみであった。
そうしなければ、かつての地上、【クレア】の技術に半分も及ばないテレサの技術上、微妙な釣り合いの下に保たれている天啓グリーグの残像は、消えてしまう恐れがあった。
グリーグの知恵なしにこの世界は成り立たない。
グリーグの残像が消えてなくなることこそ、アルクメネの最も恐れていることであった。
社に近づく3人の影がある。
彼らは認証を行い、中へと足を踏み入れた。
一人は腰が曲がった老成した翁であり、
一人は非常に若く、もう一人は体の大きい中年の男である。
彼らは翠玉の薄い正方形の瓦が敷き詰められた回廊を歩いていく。
靴底が、鉄琴のような音を奏でていた。
回廊を渡りきり、大理石でできた鳥居をくぐると、金と緑の糸で編まれた薄い暖簾の奥に、白い光が見える。
その白い光―【玉座】にこそ、天啓グリーグは眠っていた。
およそこの世のすべての緑という色を薄くにじませたような美しい髪。
年をとっても変わらず容色の衰えなかった彼の姿は、符号と言えど酷く美しい。
これぞまさに神に遣わされた寵児、否、誰もが彼こそが神であると信じて疑わなかった。
グリーグは眼をこすり、伸びをした。その気だるげな仕草でさえ艶めかしい。
『ああ、来たね。どうしたの?』
グリーグの声は、琴のように耳に心地よい。
「は」
翁は首を垂れる。
「以前から申し上げていた異形の件でございます」
『ああ、あれね。それで?原因はわかったのかな。君達はそろいもそろって、一向に重い腰を上げようとしないから・・・こういうことこそ迅速に対応しなければ取り返しのつかないことになるでしょう?目は覚めたの?』
「はい。その件ですが、その・・・非常に遺憾なことでありますが・・・調べた結果―」
『ああうっとうしい』
グリーグは天を仰いだ。
『もういいや。そこの・・・えっと、キシュキ、だったかな。君が言ってごらん。これも勉強だよ』
「えっ」
名を呼ばれた金髪の少年は、肩を跳ねさせた。胡桃色の瞳が揺れている。少年は黒髪の中年の男を窺った。男は嘆息する。
「グリーグ殿。こいつは能力はずば抜けて高いが、ここぞという時にすぐ腰が引けましてな。だからこそ慣らすためにこうして連れてきてやっているのですが・・・申し訳ない」
グリーグはくすりと笑った。
『ほんとにねえ。今のアルクメネ達が死んでしまったら、次は君達がここを背負っていかなければならないのに、そんなことでどうするのかな。まあいいや。じゃああなたが説明してくれる?』
男は豪快に笑った。
「グリーグ様はなかなかにせっかちな方でございますな」
「こ、これ・・・!!」
翁が慌てる。男のこういう遠慮のない物言いやきっぷの良さが、グリーグは気に入っているらしかった。だからこそ、他の老アルクメネを差し置いてこの男が重用されているのだ。正直少年はおまけのようなものだった。
「私はやはり年長を敬いたい。デバーラ殿に敬意を」
男が言うと、グリーグはつまらなさそうに肩をすくめ、デバーラ翁に向き直った。
『ああごめんね、ついからかいたくなっちゃってさ。お話続けていいよ。ご老人は嫌いじゃないんだ。むしろ好き』
翁は慌てたように身を小さくした。
「も、もったいなきお言葉であります」
実際の年齢を考えれば、翁よりもグリーグの方が年上になる。翁がびくびくするのも無理はないのだろうと黒髪の男は思いやった。この翁は生前のグリーグをも見てきたのだ。符号でさえこれほどに美しいのだから、実物は気圧されるほどだったろう。
「異形の件でありますが、やはり、【バベル】の扉がわずかに開いているようであります。隙間、割れ目ほどのものであろうと推測いたしましたが、既にこれだけの化け物が確認されている現状、これ以上バベルが開くことがあればこの世界はそう長くは持ちますまい。一刻も早く、まだ綻びの小さき段階でバベルを再び閉じてしまわねばなりません」
グリーグは頬杖をついて嘆息した。
『だろうと思ったよ。それで?バベルが開いてしまった原因はわかったの?』
「いえ・・・それが・・・さっぱり」
『困ったねえ』
グリーグは口元を手で覆って、うーん、と唸った。
『普通だったら開くはずはないんだけどなあ・・・それとも最初に閉じた時に何か見落としでもあったかなあ・・・でもそれを知るためにはもう一度中をのぞく必要がありそうだし』
「そ、そんなことをしたら世界が飲み込まれてしまいます」
少年が慌てたように口走り、はっとして口を押さえると顔を真っ赤に染めた。
グリーグは苦笑する。
『もちろん、そんなことわかってるよ。危険性の方が高すぎる。だから外側から攻めなきゃいけないよねえ。困った困った』
「グリーグ様にもなす術はないのですか」
翁が絶望したように言う。
「我々はこのまま先延ばしにされた破滅を待てと」
『やだなぁ、違うよ。そういうことは言ってないよ。ただね、ほら、今の僕はただの符号であって本物じゃない。実態を持たない。本物と比べれば発想力や思考力は格段に劣るし、直接何かをできるわけじゃあないんだよ』
三人は息をのんだ。グリーグの符号はあまりにもよくできていて、本人であるという錯覚に捕われていたのだ。まさか符号の口から【本体とは別物だ】と聞かされることになるなど、誰が想像するだろう。
『うーん・・・結局さ、僕が行かないと何にも把握すらできないんだよねえ。困った困った』
グリーグはなぜか楽しげに笑った。そして徐に空を仰ぎ、ぱちん、と指を鳴らす。
グリーグの指先に、青い燕が止まった。グリーグはその目を見つめる。
やがて燕は森の中に消えた。
「今のは・・・?」
少年が独り言つと、グリーグはにっこりと笑った。
『僕のたった一人のお友達だよ』
少年が面くらっていると、燕はややあって、舞い戻ってきた。
足で、とても美しい絹布のようなものを引きずっている。
およそ全ての色の絵具をにじませたような美しいそれは、【鳥】の翼だった。
「翼・・・?これが、翼!?」
少年は驚愕する。
【鳥】とよばれる種族のもつ翼であれば、それは等しく鷲のような、梟のような、鳥類の翼の大型のものであった。だというのに、燕が携えてきたそれは明らかに翼らしくなく、それでいて神と言うものに翼があるなればかくやありき、と思わせる幻想を孕んでいる。
「これがグリーグ様の翼じゃ」
翁は少年に向かって優しく言った。
「ほれぼれするじゃろう」
「これが・・・」
黒髪の男もようやくそれだけを言った。
翁はほほ笑む。
「もう片方の翼は残していらっしゃったのですな」
『うん、こんなこともあろうかと思ってね。僕の羽は酷く繊細だし、本体から切り離した状態では、管理を誤れば腐らないとも限らない。だから勝手に僕が独断で場所を決めて保存していたんだ。場所を内緒にしていてごめんね』
「いえ。我々はグリーグ様のなさることに口出しなどするつもりもございませんよ」
翁はほほ笑む。
「して、その翼を今度は何にお使いになるのですか」
「あのう・・・」
少年がおずおずと口を挟む。
「もう片方の翼は、どうなさったんですか?」
『気になる?』
「え?あ、や、その」
グリーグはにっこりとわらって指で自分の頭をとんとん、と突いた。
『こ、れ。この符号、僕の片翼を媒介にして作られたものなんだよ。だからこうして長年符号が保たれているの』
少年は顔を真っ赤にした。興奮すると顔が紅潮するのだ。
「す、すごい技術だ・・・」
「落ち着け」
黒髪の男が小声で言って嘆息する。
『本当はやりたくなかったけれどね。僕はこの世に生まれ変わろうと思うよ』
「は?」
翁が声を漏らした。
「ど、どういう意味でございますか」
『この世の者は等しく皆死してもう一度この世に生まれ変わり、循環していく。それが世の理。だけど僕は一度も転生できていない。なぜかわかる?』
グリーグはにっこりとほほ笑んだ。
『【僕】を構成する要素が一部欠けた状態だからだよ。ほら、この翼』
グリーグは己の翼を撫でた。
『逆にいえば、こうして翼だけ別に保管しておけば、僕は生まれ変われない。つまり、こうして【グリーグ】としてずっと居られる。もし転生してもその僕が今のグリーグである僕の記憶を有して生まれてこれる可能性はほぼないに等しいんだ。それはとても危険なことだった。だって、君達世界は【グリーグ】の記憶を必要としているでしょう?』
グリーグは苦笑する。
『けれど、こうなってしまった以上、やはり僕自身が現場に行かなければいけないみたいだ。僕はそのわずかな可能性に欠けてみるよ。このまま僕の符号は残しておくといい。そうすれば仮に僕の転生が記憶を持たずとも、僕の知識を与えてやることは後からでも可能だ。この翼を今から空に還すよ。そうすれば僕の生まれ変わりがこの世界のどこかに生まれるだろう。ただしその子は不完全な子だ。もう片翼がない状態で無理矢理生まれてくる子だからね。その子が生まれて、知覚ができる年齢になった頃、』
グリーグはまっすぐに三人の目を見つめた。
『【この僕】を消してほしい。デバーラ、あなたならやり方はわかるね?今ここにいる二人に教えておきなさい。あなたはもう年だから、その頃まで元気でいてくださればいいけれど、万が一ということもある』
「御意にございます」
翁は首を垂れた。黒髪の男はふと、顎をさすりながら何事かを考える。
「グリーグ殿。そのやり方であれば今までも御身の転生を作ることは可能でしたな?なぜ今までやらなかったのです」
『言ったでしょう?生まれてくる子は不完全な子、だって。僕の予想では恐らく、力の制御ができないままに生まれてくる。僕の力は、自分で言うのもなんだけど、結構すごいからね。だからどうしても、この符号に用いた翼も必要になってくる。けれどその時、【グリーグ】は消える』
男は息を呑んだ。
「他に・・・方法はないのですか」
『君達は【バベル】を目にしたことがないから、そんな悠長なことが言っていられるんだよ』
少年は俯いた。
「確かに・・・文献に記載されている状況を想像するだけでも恐ろしいです。きっと現実はもっと酷い」
『僕自身が生きていればもっと酷い状況でもバベルを封印するくらい楽だったんだけどねえ』
グリーグから表情が消える。何かを考えているようだった。
『生まれ変わってくる子も僕そのものじゃないからね。君達が育てるといいよ。【英雄】になれるように、ね』
グリーグは寂しげに笑った。
少年は顔をあげて、グリーグを見た。他の二人は俯いている。グリーグの目が一瞬、笑っていないように見えた気がして、少年は少し身震いをした。けれどグリーグの符号は、とても神々しい。自分はただ、気圧されただけなのだと思った。グリーグの翼は日の光を鈍く反射してまるで銀河のようだ。
一、
一、
とても、暗い、暗い。
自分に目など、必要ないと思った。
こんな暗闇の中で、光すらほとんど射さない状況で、目を凝らしても見えるものは、腐った死体や腐りかけの人ばかり。
異臭にもいつの間にか、慣れた。
心を消してしまえば、臭い、と思う気力もなくなった。
わずかな音に耳を澄ますことにさえ、疲れてしまった。
耳も必要ない。鼻も必要ない。
常に唾液を生み出すこの口だって、気持ちが悪い。
少年はただ、膝を抱えて、膝頭に頭をのせ、眠り続けていた。
もうどれくらい体を洗えていないだろう。
死体から湧いた虫は、少年の皮膚にも吸いつき、勝手に死んでいった。
自分はもうとっくに、気持ちの悪い存在になったのだなあ、と、おぼろげに思った。
周期的に内から湧いてくる、生きていたいという衝動が、気持ち悪かった。
―早く死にたい。死にたい死にたい死にたい。
少年は泣きそうになって、また、そのことに自分で嫌悪した。
暗い、暗い、冷たい石の箱。
ぞっとするほど細くなった自分の手首を無意味に握りながら、少年は嘆息した。
いつまで経っても救いは来ない。
一秒でさえ待てなかった。
早く死にたかった。なのに、まだ生きている。
ふと、天井から足音が聞こえた。少年はぼんやりと天を仰ぐ。
しばらくして足音はぴたり、と止むと、耳をつんざくような音が響いた。
少年はびくっと肩をすくめる。
カーン、カーン、と、少年の真上で、何かを酷くぶつけあっているような音と振動が、少年の皮膚に響き伝わる。
少年は歯をかたかたと鳴らした。立ち上がりたかったがそんな筋力すら残っていない。
やがて、天井にぴしり、と割れ目ができる。
少年はぎょっとした。まさかこんな形で死ぬことになるなんて思いもしなかった。
自分がこの重たい石に押しつぶされ血まみれになって死んだ姿を想像して、ぞっとする。
そのあとにたくさんの蛆虫がわくだろう。そんな気持ちの悪いことに、これ以上なりたくなかった。
―嫌だ!!死にたくない・・・!!
少年は、半狂乱で思った。歯ががたがたと震える。
爪の下が、炎が出そうなほど、熱くなっていく。いつの間にか、部屋が鈍く照らされていた。周りの状況が、ようやく少年の目に映る。そして、少年はぞっとした。
怪物のような虫がいる。
こちらを見ている。
何匹も居て、少年を狙っているかのようだ。
少年は、部屋を照らす光が少年の体から放たれていることには気づいていなかった。がたがたと震えながら懸命に足で床を蹴る。けれど筋力の衰えた足では、やせ細った体すら動かせなかった。
やがて少年は、その虫達のほとんどが、生きていないことに気付いた。
虫だと思っていたものは、人の体だった。
骨だった。
小さな虫達に体をしゃぶりつくされ、手足の外れてしまった、皮膚も筋肉もどろどろにとけてしまった、人のなれの果てだ。
―嫌、だ
少年は口をきつく覆った。悲鳴が出そうだった。とうに声の出し方など忘れたけれど、喉の奥が苦しく痛くて、涙があふれてくる。
爆音がして、天井が崩れ落ちてきた。
【虫達】は皆その下敷きになって、これ以上ないほどにつぶれ飛散した。
―いっそ気を失えたら良かったのに。
少年はとめどなく泣いた。けれど意識は痛みを覚えるごとにはっきりとしていく。
体中が酷く熱かった。内側がやけどしているかのようだ。
垢と汗と埃で汚れきった皮膚だけが、妙に冷えている。
「ごめん!無事?」
光の差した天井から、若い男の声が聞こえた。
少年はそれを見上げる。けれど、強すぎる光に目がくらんだ。
「緑の髪・・・よかった!!生きてる!!ごめんね、出してあげるから」
「怖い」
少年の喉から、奇妙な音が漏れた。それが声だったということに気付くのに、時間がかかった。
頭痛が走る。少年は、これが怒りなのか恐怖なのか、安堵なのか判別できなかった。
ただそれは酷く熱い感情で、自分を焼き焦がしそうで。
喉が張り裂けるように痛いと思った。自分が化け物のように叫んでいるからだと気づく頃には、辺りが白い光で満たされて、目がつぶれていた。
少年の周りから、水面にひろがる波紋のように、澄み切った鉄琴のような音が生まれ響く。
それは世界中に響き渡る音だった。
少年は知る由もない。
光はある時ぷつりと消え、少年の意識も死んだ。
目の前に白いかすみがかかっている。
やがてそれは次第に晴れた。
赤い布が見える。
それが天井だと気づくのに、時間がかかった。
体を起こしながら、どうして自然に体を起こしたくなったんだろうかと、ふと疑問に思う。
見渡すと、そこはかつて自分の暮らしていた光の世界の部屋に、似ていた。
ぼんやりと視線をさまよわせていると、自分の両手が目に入る。
どす黒かったはずのその皮膚は、信じられないほど白く、【人の】ものだった。そのままぼんやりと部屋の一点を眺めていると、扉が開いて、白と紺の布を身にまとった女が何かを持ってくる。
そして少年が体を起こしていることに気づいて、目を丸くした。
何事かを言ったが、少年には知覚できない。
女は扉の向こうへあわただしく姿を消す。
どれくらいの時間が経ったのかわからないが、やがて、背の高い痩身の男が姿を現した。
少年は、その青年の顔をぼんやりと見上げる。青年はしばらく少年の目を見ていたが、やがて、少年の顔の前で手のひらをひらひらと振った。
「見える?」
その声にどこか聞きおぼえがあるな、と思いながら、少年は目の前で高速にぶれる肌色を眺める。
やがてそれになんとなく不快感を感じ、少年はようやく思い切り顔をしかめて強い力でその手をはたいた。
青年はぱっと表情を明るくする。
「よかった!やっと表情が・・・!!」
「あ?」
少年から、不快そうな声が漏れる。
「うん、最初に見た時は骸骨みたいだったけど、今はガリ痩せ程度だし。看病ありがとう。助かったよ」
青年はそばに控えていた女に笑いかけた。女は縮こまる。
「いえ、私共、キシュキ様のお役に立てますのならば」
「お疲れ様。みんなほとんど寝ないで彼を見ていてくれてたようだし、今日はゆっくり休んで。あとで美味しい甘味もよこそう」
「あ、ありがとうございます。女中頭に伝えてまいります!」
青年は、あわただしく扉の向こうへと引っ込む女を優しいまなざしで見送った。
青年は胡桃色の瞳をキラキラと輝かせて少年の頭を撫でる。
「よかったぁ・・・せっかく君、生まれてきてくれたのに死んでしまってたらどうしようかと思ったよ。しかしウィルドも酷いことするねえ。見つけるのに一苦労だった」
少年はようやく、違和感の正体に気付く。
「羽・・・」
少年が眉をひそめると、青年はきょとん、として自分の背中を見やった。
「ああ、これ・・・ってそっか、君は見るの初めてなのか」
青年は頭を掻いた。
「はじめまして。俺はキシュキ=レシラ。君達の世界で言うテレサの住人だよ」
「テレ・・・サ」
「あれ?知らない?」
「覚えてない」
少年はつっけんどんに言った。正直頭痛がする。まだ本調子ではないらしい。
「君達翼がない人の居る世界を俺達はクレアと言うし、俺達【鳥】のことを君達はテレサ、とか、アルクメネ、って呼ぶんだよ。ってこれ、義務教育の知識のはずなんだけどなあ。っていうか君何歳」
「覚えてない」
「ええ!?ええっとね・・・でもたしか君のお父上はムネモシネだよね?だったら高等教育は受けてるはずなんだけどなあ・・・」
「知るか」
少年は深く息を吐いた。
「なんなの?さっきから。ていうかあんた何」
青年―キシュキは目を丸くした。
「ず、ずいぶん口が悪いね」
「殺してやろうか」
「・・・まあ、元気な証拠だね」
「その花畑な脳みそえぐってやりたい」
「け、結構殺伐とした発言をするね、君」
キシュキは苦笑する。
キシュキはもう一度少年の頭をくしゃくしゃと撫でた。
「でも・・・いずれにしろウィルドっていうのは残酷だね。力があるだけであんな酷い所に閉じ込めるなんて・・・そもそもあれ、大罪人の無期懲役用の牢獄らしいね。あれはさすがに酷いよ・・・あんなの・・・あんな所に入るくらいなら死刑の方がずっと良心的だ」
キシュキは思い出したように顔をしかめる。
「僕がそれくらいのことをしたからだろ」
少年は気だるげに言った。キシュキは目を丸くした後、なぜかくすりと笑う。少年が顔をしかめると照れたように頬を掻いた。
「いや、なんだかやっぱりグリーグ様と似た雰囲気あるんだなあって思ってさ」
少年はますます顔をしかめる。
キシュキはにっこりと笑った。
「俺達、君の大切なものを預かっているんだ。それを返したくて君をここに招待した。本当はテレサに上がるには公式の手続きを踏まなきゃいけないんだけど、君は存在からして【特例】だし、別にいいよね。文句あるならムネモシネなんて俺がやっつけてやるよ、言葉攻めで」
キシュキは片眼を瞑って見せる。
少年は嘆息した。
「僕はあんたらに会うのは今日が初めてだしそもそも大事なものなんて一つもない。人違いじゃないの」
「まさか」
キシュキの声が静かに響く。
「君のその髪、それから死の淵に遭って体から放った緑白の光、そして何よりグリーグ様が君だと言っている。それだけで十分だ。君は待ち望まれた子なんだよ。災いなんかじゃない」
その言葉に、記憶の奥で言われた言葉が蘇り、少年は再び眉根を寄せた。
「むしろ、申し訳ないよ。もっと早くに君に気付くべきだった。まさか、【鳥】の生まれ変わりがただの【人】の下に生まれるだなんて、想像もしなかったんだ。不完全な子、って言うのはこういう意味だったんだなあ」
「さっきから待ち望まれただの不完全だの言いたい放題うるさいよ」
少年はキシュキを睨みつける。それは殺気のこもった目だった。だがキシュキは笑顔を崩さない。少年は嘆息した。この男は余程気が太いらしい。あるいは単なる馬鹿か。
「それにしても」
キシュキは嬉しそうににこにこと笑う。
「グリーグ様よりは濃い緑の髪だし、グリーグ様と違って瞳の色も人の色だけど、まるで君、森みたいだね。君も十分美しい!」
「は?」
少年はげんなりした。
少年の視線に気づいたのか、キシュキは、あ、と声を漏らす。
「グリーグ様が気になるんだね?大丈夫、君がもう少し肉をつけたら会わせてあげるよ。元気そうだけどやっぱり病人なんだ。君、痩せすぎてる。もう少し元気にならないと歩くのも一苦労だよ」
「僕何にも言ってないんだけどいい加減にして」
「あはは。じゃあ、今日のところは僕も退散するかな。何か入用なものがあったら何でも言ってよ。あ、あとご飯はちゃんと食べなさい。今日からは流動食じゃなくて済むね」
キシュキは長めの金髪をひらりと舞わせて扉へ向かう。
扉の取っ手をつかんで、ふと振り返った。とても優しい笑みだ。
「俺達【鳥】は、君の味方だよ、ギリシェ=ラスバーン」
嫌味のない香水のほのかな香りが、部屋に残る。
その残り香になんとなく意識を取られながら、ギリシェはもう一度部屋を見回して顔をしかめた。趣味が悪いにもほどがある。
金と白の家具はやたらごてごてごてとした装飾を施されている。天井が黒みがかった赤い色であるのもあまり好きではない。しかも床の絨毯は金色の刺繍の施された紺色ときた。
一つ一つはそこまで悪くもないのかもしれない。だがそれを一つの部屋にこれでもかと押し込めたことに問題がある。ギリシェは胸に刻んだ。この邸の主は気違いだ。
自分にかけられている上布団もまた、真っ白でごてごてと刺繍や網模様を施されているブツだと気がついて、ギリシェは嘆息する。
脇の小さな台に乗せられた食事の盆に手を伸ばした。見た目は悪くない。口に運んでみる。味もまあ悪くない。というか旨い。
しばらくがつがつとむさぼった後、急に満腹感が来てギリシェは手を止めた。改めて見てみると皿の中身はほとんど減っていない。余程自分の胃が小さくなったのだな、と認識する。
ギリシェは食べていた間、詰め込むのに必死で気づいていなかった。壁にかけられたどでかい女の肖像画がいつの間にか垂直に傾いていた。
ギリシェはふと、ようやく違和感に気がつく。何か部屋の様子が変わっている気がする。
しかしすぐには気がつかなかった。ようやく絵の位置が変わっていることに気付いた時には、ごごご、という小さな音と共に今度はその絵がギリシェの方へ向って伸びてくる。さすがにぎょっとする。壁とギリシェとの間はかなり離れているからまさかぶつかってくることはないだろうが、それでも自分の5倍くらいの大きさの顔が近づいてくるのは気味が悪かった。この際乙女が美人であろうと何の意味もない。
やがて絵の動きはぴたり、と止まり、しばらくしてがさごそという音と共に、ひょこり、と何かが乙女の脳天から顔を出した。ますますぎょっとする。
その少年は水晶のような薄青の髪をしていた。じいっ、とこちらを見ている。正直あまり気持ちはよくない。
しかももじもじとしているのが手にとるように分かった。ギリシェはだんだん苛々してきた。限りなくうっとうしい。帰れ、とでもいい放ってやりたい。
だが面倒だったのでそのまま睨むだけに留めておく。しばらく沈黙が続いた。ギリシェは目を閉じて舌打ちをする。ようやくもう一度がさっ、と音がした。少年は絵の傍で立っていた。腕組みをしてギリシェをじいっと見ている。だが睨まれているわけでもなさそうだった。とても眠たそうな目で凝視されても非常に困る。大きな垂れ目と左の頬の中央にある黒子が、よけいに少年の表情にぼんやり感を与えている。
「何?」
結局、折れたのはギリシェだった。少年はふにゃり、と笑う。どうやら延々ギリシェが何かしら言うのを待っていたらしい。少年は大股で歩いてきた。あまりに早く目の前に来たのでギリシェは仰け反りそうになる。
「だぁれ?」
少年はこもった高めの声で言いくさった。その質問に苛つけばいいのか脱力すればいいのか分からなくなる。
しかもやたら顔が近い。にこにこ笑いながらどんどん迫ってくる。ついに鼻の頭がぶつかる一歩手前まで来た。ギリシェは顔をしかめながらその胸を押し離す。
―聞く前に自分が名乗れよこの頓珍漢。
ギリシェは心の中で毒づいた。口には出さない。口に出すのは面倒だった。こんな見も知らぬ胡散臭い初対面の人間のために声を出してやると言う労力を使う意義が見いだせない。
けれどどこか落ち着かなくて、目も反らせなかった。もしも目をそらせば自分の見ていないところで何かを観察される心地になる。
少年の瞳は綺麗な菫色だった。その中に自分が映っている。いつの間にか記憶の中の自分の姿よりも大人びた顔に成長していることを認識する。
少年はきょとん、としたまま首をかしげた。どうやら何故ギリシェが答えてくれないのかを不思議がっているらしい。ギリシェは眉根を寄せて目を閉じ、ゆっくりと息を吐いた。とても疲れていた。
「ギリシェ、僕」
結局、また折れたのもギリシェだった。少年はにっこりとそれはそれは嬉しそうに笑った。
「どうしてこんなところに【はねなし】がいるの?面白いなぁ」
―はねなし?
ギリシェは眉をひそめる。しばらくして、自分達【人】のことなのだと認識する。確かに【鳥】とは違い自分達は翼を持たない。
けれども生憎、その質問を満たせる答えをギリシェは持っていなかった。むしろ教えてほしいくらいだ。自分は確かに牢獄にいたはずだった。なのにいつの間にこんな風に趣味の悪い―万歩譲ってやってよく言うなら高級志向、の部屋に移動しているのだか。
ふと、少年の羽を眺めていてギリシェはあることに気がついた。
少年の羽は瞳と同じ紫色に滲んでいる。先刻のキシュキと呼ばれていた男も、瞳と同じ黄緑の翼を持っていた。けれどそもそも、これは翼と言えるのだろうか。おおよそギリシェの知っている鳥の翼とまるで似ていない。どちらかと言えば麻や絹で織られた滑らかな布のようだった。本当にこんな薄っぺらい物で飛べるのかと訝しく思いたくなる。とはいえ、やはり着ている服と比べると明らかに材質は違うものだった。もっと滑らかだ。
―収集家が好きそうな素材。
ギリシェは思う。世の中には兎や狐の毛皮、鹿の角などを集めている輩がいる。より美を求め、彼らや彼らに従属する者たちは狩りに勤しむ。人は美しいものを見ると、手に入れたいという衝動に勝てない。
目の前にいる少年は、まさに【人】の餌食になりそうな存在だった。この翼を使って着物を作ったらきっと金持ちは相当な額を出して買うだろうな、とギリシェはぼんやりと思う。少年の外見もまた、色好みの気違い共が大金撒き散らして欲しがりそうな物件だった。そういう思考自体とても残酷なものであることにギリシェは気づけない。ギリシェはただ、不快そうに鼻で笑っただけだった。
「ていうか、あれ、何。なんかの仕掛け?どこにつながってんの」
ギリシェは気だるげに言った。いまだ垂直に傾いてこっちを見ている乙女の目線がどうにも気になって仕方がない。
少年はのろのろと振り返り、へらっと笑った。ギリシェの苛々度が5くらい上がった。
「ああ、あれ僕が作ってみたんだよ、兄さんが作りかけて途中で放棄した仕掛けだよ。なんか適当にぶった切ってつなげて踏んづけといたらできちゃった」
―・・・・・・。
ギリシェは何も言うまいと思った。何か言いたくなったら負けなような気がする。
少年はもう一度乙女を振り返る。
「ちなみにこの向きだと、廊下に出るよ。反対側に回すと裏口の近くに出られるし、逆さまにすると兄さんの部屋の天井裏に―」
「ちょっと、なんで天井裏なの」
つい口を挟んでしまって、ギリシェは顔を思い切りしかめた。何も言うつもりはなかったのだ。本当に。
「だって」
少年はきょとん、とした。
「だって真っ向から入ったら兄さんにばれるじゃない」
―そもそも兄さんって誰。
ギリシェは小さく嘆息する。
少年はにこり、と笑った。
「あと、絵を裏返せば秘密の場所に行けるよ、でも内緒なんだ。僕が其処を知っているって誰も知らないし、知られちゃいけないんだ。ふふ」
とても嬉しそうに話す。
―僕に話した時点で内緒も何も。
ギリシェは溜息をつくことすら面倒になった。
「ねえ、連れていってあげよっか、ここ、退屈でしょ?兄さんの顔拝むしかやることないなんて可哀相」
「は?」
ギリシェは眉をひそめる。
―退屈なのは否定はしないけど、
「ちょっと、一体どういう流れでそうなるわけ」
「ええ~、それはだって、そうだねえ、僕が連れていきたいから!」
「意味わかんないんですけど」
「いいじゃない!ばれなきゃ大丈夫」
「いやばれるだろ」
「なんで?ばれたらなんでだめなの?」
「は?」
ギリシェはもう一度眉間にしわを寄せた。頭痛がしてきたのは気のせいだろうか。
しばらく考えて、一つの結論に至る。
―単に見せびらかしたいだけだろ、あんた。
頭が痛い。
こめかみを押さえていると、ふわり、と体が浮いてぎょっとした。目の前に少年の顔が近付いている。ギリシェは少年の片翼に抱きかかえられていた。何処から驚けばいいのか分からない。翼はとても滑らかで温かで、気持ちがよかった。あまりの気持ちよさに、少しだけ眠たくなる。
「まだ歩けないだろうから僕が運んであげる!」
少年はそれはそれは楽しそうに言うと、また乙女の方へと歩む、巨大化する乙女の顔にギリシェはげんなりしていた。いくら美人でもこの大きさはやり過ぎだと思う。
絵の裏は、不思議な構造をしていた。カラクリと言うからには、鉄の棒のようなものや銅線をつないでいるのかと思ったが、そうではない。金銀の針のように細い光が幾何学的な模様に交錯している。よくよく見ると、文字のようなものが浮かんでいる部分もあった。数字らしきものもちかちかと青や赤に光っている。
「よいしょ、と」
少年は器用にその光をまたがって、光の無いところに収まった。数字の部分に手をかざす。かさかさ、と妙な音がして、二人は一気に金色の細い光の糸に囲まれた。糸は編まれ籠状になっていく。急にふわり、と少年の体が浮いた。風が下から吹いている。二人の体がくるん、と籠の中で回転する。頭がくらっ、とした。
そそそ、という、それはそれは控えめな紙を擦るような音と共に、絵はもう一度壁に吸い込まれていく。かち、と音がして、乙女の絵はもとの位置に、何事もなかったかのように収まった。その品のよい微笑の先には、ちゃんと整えられていない白い寝床がある。さっきまで誰かのいたぬるい熱が残っている。
二、
非常に不快だった。
まず、温い。そしてちりちりと耳障りな音がする。
言うなれば腹から嚥下したとき口まで上ってくる胃液の中に体をびしょ濡れにされたような感覚だった。目を見開くこともできなかったけれど閉じ切ることもなんだかできず、そうしているうちに角膜の上を金色と灰色の針金のような光の点線がひどく忙しなく縦に横に斜めに螺旋を描いて動いた。それを見ていただけで気分が悪くなった。そして何より音だ。脳髄にまでじんじんと響いてくるから、耳を塞いだところでほぼ意味はない。ちり、ぎり、がり、とまるで金属で金属を削るようなキーキーとした音がとぎれとぎれにのろのろと鳴った。それらがすべて自分達を包み込んだ。世界は水色と黄色。ところどころ意味のわからない赤橙と橙の色をした球体のような円盤のような半透明のものがぴょんぴょん飛んで行った。
そう長い時間ではなかったのかもしれないけれど、十分にギリシェにとっては疲労の材料になった。
空間が巻貝のようにぐるぐると絞り上げられ、先端の方へ二人は吸いこまれていく。痛くはなかった。自分の周りにねっとりと纏わりついていた温い液体のようなものが体からしぼりとられていくようで、ようやくすう、と息ができたような心地がした。ギリシェは大きくため息をついた。ため息がこんなにも気持ちの良いものだとはついぞ知らなんだ。これからは大いに息を吐くとしよう。
「着いたよー。あはは、相変わらず気色悪かった!」
薄青の髪の少年は妙にすっきりした顔もちで言った。ギリシェは一瞬何を言われたのかわからなくて、止まる。
自分もあまり気持ちよくないなら何故にこの移動手段を使うのかと問いたくないこともなかった。ぐっとこらえる。面倒な会話で時間が浪費されるのは疲れるから嫌いだ。
まずは状況を判断しよう、とギリシェは辺りを見渡した。黙ってそうするのは一種の癖だ。人にいちいち分からないことを聞くのはあまり好きではなかった。わずらわしいからだ。自分の目で見て知ることができることは、意外と多いものだ。もしよくわからなくてもそれは今の自分にはきっと必要がないから分からないのだ。それがギリシェの信条のようなものだった。分からないものは目に焼き付けておけばいい。いつかそれが必要になった時に、それが何だったのかきっと分かるだろう。そう思っている。
一面は緑の森だ。青緑の瑞々しく肉厚な葉の茂った木が地面中に根を張っている。普通の木と違うところ言えば、根にもまた葉がまるで蔦や蔓草の類のように茂っているということだろうか。おかげで地上で見られる草のようなものはないけれど、十分に地面も緑に覆われている。
そして不自然に、ぽっかりと空いた、いや、空けられた空間がある。作為的にも見えるよく伸びた三つの木の枝が絡み合って網をつくり、屋根になっている。その下でその格子の影を映しているのはやや茶色がかった黄色の四角錐の大きな物体だった。その全ての辺と中線もまた、先刻奇妙な空間で見たものとよく似た、赤みのある金色の点線状の光の通路になっている。そしてその四角錐の周りの地面に、ぽつぽつと長方形の白金の薄板が刺さっている。まるで規則性がない並びのように見えて目を細めたら、実はそれらの板は四角錐の建物を中心に据えた見えない正方形の辺上にきちんと立っているのだとわかった。それがわかって改めて眺めると、不整合に見えたそれらの構造が実は綿密な計算のもとに配置されているのだと分かる。地上ではまず見ない様式美だ。少なくとも地上の人間達は均等を好む。対称なものを美しいと直感的に感じる。今目の前にある建築物は、全体としてみれば点対称ですらない。
そして、妙に静かだった。風ひとつ吹いていないのだ。空気はあるはずなのに、居心地が悪くなるような静けさだ。身動きをして音を立ててはいけないかのような心地になる。
意味が分からなかった。結局分かるのは、地上とこの羽のある生物たちの暮らす環境は似ているようで実は全然違うのであろうということ、そして美しいようでどこか怖いものなのだと肌で感じ取れるだけ。
「ここはピルミラ。グリーグ様の社だよ」
少年が、それをじっと見つめながらささやく。
だからグリーグって誰だよ、と思う。鳥達の常識を自分のようなただの人間も当然のように持っているように思わないでほしい。父親なら知っていたかもしれないな、と頭の中で言葉がかすっていって、ギリシェはかぶりを振った。どうでもいいことだ。自分は知らない。それが事実だ。あと、耳元で話すのやめてほしい。
「グリーグ様はもう亡くなってるから、今は誰も住んでないんだけど、ただ、多分ここは保管庫なんだと思う。上の人たちは、文化的遺産であるグリーグ様の住まいの永久的保護のために立ち入り禁止、だなんて言ってるけど、現にあの人たち結構ここにちょこちょこ達言ってるみたいだし、それは多分詭弁だよね。多分、【あれ】を保護してるんだ、ここで。腐らないように」
―【あれ】、ねえ。
だからなんだよ、と思ったりしなくもない。そんなことを自分に話したところでさっぱり意味が分からないのだから非常に不毛だ。無駄だ。
溜息でもつこうかな、と思ったがやめておくことにした。わざわざ人前でするものでもない。あとあと面倒だ。自分はなるべく透明に生きていきたいのだ。
まあ、もう少し人並みに生きていてもいいなら、の話だが。
「多分、【それ】をここから出しちゃいけないのと、僕が外を歩いちゃいけない理由はつながっているんだと思うんだけど、いかんせん兄さんに聞くわけにもいかないから、ばれちゃうから、僕には未だに痒いところに手が届かない気持ちってこういうことなのかなって」
先刻から筋の通らない言葉遣いなやつだな、とギリシェは思った。そうしてふと、なんでこいつら、羽があるのに歩くんだろう、と思ったりした。そういえばキシュキと名乗った青年も女中も羽があるくせに床をぺたぺたと歩いていたように記憶している。
ふと、少年は不思議そうにギリシェの顔を覗き込んだ。いちいち距離が近い。まあだからと言ってひるむわけでもないのだが。少々のことでは動じない癖がついてしまっている。
「君、変な子」
「は?」
つい相手をしてしまった。
「だって、さっきからずっと取り乱すこともなくだんまりなんだもん。臆してるわけじゃないんだよね?人ってみんなそうなの?」
「さあ」
「さあって」
「僕に人類一般の傾向を語れと言われてもな。言うほど経験積んでないもん」
「そうなの?」
ふーん、と少年は一人で納得したようだった。そうして唐突ににっこりと嬉しそうな笑顔を浮かべる。
何、と思ったりする。
「えへへ、でもなんだか楽だな!僕が一人でしゃべってても変な空気にならないしね!やっぱり相手がいるっていいことだよね。一人きりの時ぶつぶつ独り言言っててたまに無性に恥ずかしくなる時あるんだよね」
そこまできちんと耳を傾けてもいないんだけど、と心の中でだけ応対して、ギリシェはそのまま四角錐の方へ視線を戻した。
なんだろう。最初の衝撃が薄れると、だんだん愛着がわいてくるというか、この形がどこか可愛いものに思えてくる。何の変哲もない図形の塊なのに、奇妙な感覚なことだ。
上手い言葉が見つからないけれど、少なくとも警戒心があおられたりはしない。この場所にいると、神経を張り詰めようとする気が削がれていく。
「あのね、ちょっとついてきてよ」
少年はさらりと言うと、そのままピルミラの方へ近づいていく。その足取りを見ながら、やっぱり人よりも足取りに重さがないんだな、とギリシェは少しだけ思う。
着いていかない理由もないけれどついていかなければならない理屈もないんだけどな、などと思いながらギリシェは大人しくその後ろを着いて行った。
「ほら、こっち。ここまで寄ってみて」
少年は手招きする。ピルミラの壁にぴったりと鼻と手を寄せて中を食い入るように見る。
ギリシェも、さすがにそこまではしなかったが少年の肩の後ろから覗いてみた。
離れた所からは分からなかったが、ピルミラの壁は透明で、中が見えるようになっていた。点線の光がちらちらとせわしなく動いて交錯するので鬱陶しかったりする。
けれど、その光達が載る物、内部の中央に浮かんでいるそれは、綺麗だと思った。
片翼だ。
はっきりとした色は壁の色に透かされてよくわからないけれど、光沢や影の度合いでかなりいろんな色の混じった翼なのだろうとは分かった。朱子織のようになめらかで柔らかそうだ。こうして見るだけでも、収集品に興味のないギリシェでさえ惹きつけられるものがある。魅入るとでも言うのだろうか。
「あれ?」
ギリシェはふと呟いた。よく考えてみれば、その翼はキシュキ達のような翼とは全く違うものだ。どちらかと言えば―美しさは劣るにしても―目の前にいるこの線の細い少年の翼に近い。
「鳥の翼ってやつは、いろんな種類があるんだな」
ギリシェは多分、少年に対しては初めて自分から声をかけてみる。
少年は目を丸くして振り返る。しばらくじっとギリシェの目を見つめた後、なぜか顔を赤らめてうつむいた。何故そこではにかむ必要があるのかギリシェにはよく分からない。奇妙奇天烈とはこのことだな、と呑気にそんなことを考える。
「僕のは・・・ううん、違うんだ、僕のは、ちょっと、特別なんだ。特別っていうか、奇形と言った方が正しいんじゃないかな・・・あ、グリーグ様の翼が奇形だなんて言ってないよ!?だってグリーグ様はあの翼でちゃんと飛べた。僕は飛べない。あんなに美しくもない。だから僕は多分奇形だ」
少年はぼそぼそと言う。どこか覇気がなかった。
まあ絶対に気にかけなければいけないことでもないはずなので、とりあえずギリシェは頭の中で少年の発言を整理する。
察するに、このピルミラの中にある翼はグリーグという奴の翼と言うことだろうか。そして、様と呼ばれるからにはなかなか立場の偉い人物なのだろう。そういえばもう死んだとか言っていたような気がする。つまり翼を片方だけぶった切ってここに押し込んでいるということか。見た目は綺麗だが意外と鳥達も残酷な―いや、思い切ったことをするもんなんだな、と少しだけ思う。少なくとも自分の知っている限りでは、地上の人間は敬意を表している相手の体を切断したりはしないはずだ。
ギリシェは少年の髪色と同じ柔らかで薄い翼をじっと眺めた。奇形、ねえ。
たしかにまるで女の服みたいな布が申し訳程度についているくらいのようなものだから、あってもなくてもよさそうだとも思う。けれど同時に純粋に綺麗だとも思った。もしも少年の背からこのなめらかな布のような翼がなくなってしまったら、なんだか心もとない感じだ。この翼があるから少年は鳥なのだ。人のような何の変哲もない生き物ではない。美しいものなのだ。大鷲のような翼も似合っただろうとは思うけれど、この翼は個人的に嫌いではない。
何か言った方がいいかと思って言葉を探す。けれど、変に慰めていると受け取られたくはない。単に思ったことを言いたくなっただけなのだから。
結局、何を言っても嘘くさくなりそうで、ギリシェは黙って少年の頭を撫でた。翼に触れようかとも思ったが、知覚はあるはずだ。下手に触って痛かったらよくない。
少年は戸惑ったように身をすくめていたが、やがて肩の力を抜いた。まるで野良猫を懐かせたような気分になる。
「ほんとはね、」
少年はグリーグの翼であろうものに視線を戻して静かに続けた。
「僕は自分のこの羽に、劣等感を、みじめさを感じてもいるし、ちょっと酔ってもいるんだ。
「僕のこの翼だけが、グリーグ様のものとそっくりで、他の【鳥】たちはみんなただの鳥と同じものしか持っていない。僕が自分を卑下するのもただの申し訳で、本当は心の奥底で、自己満足してるよ。だって僕の翼はグリーグ様と同じなんだ。みんなよりもずっと綺麗だし希少価値があって。だけどこんな風におごっている自分が気持ちよくもあるけど嫌いでもあるんだ。だから僕は人前では自分を卑下しないではいられないし、自分を奇形だって言わずにはいられない。自分で言って自分で傷ついて、一人になった時に自分に言い訳するんだ。だけど僕は綺麗な子だからいいんだって。慰めるみたいにさ。だけど僕は・・・綺麗なものになりたいんじゃなくて、かっこよくなりたいんだ。女みたいに儚いって言われても全然嬉しくなかったよ。僕は男らしくなりたいだけなんだけどな。骨太っていうかさ。兄さんは趣味がちょっとおかしいからなぁ。線が細けりゃいいって思ってる」
少年は、小さく嘆息した。中腰になっていた体を起こす。
「うん、満足した。聞いてくれてありがとう」
ギリシェは少しだけ顔をしかめた。礼を言われるのはなんだか居心地が悪い。言われ慣れていないのだ。なんだか腹立つし、妙な気持ちになる。
ギリシェは自分が捻くれているのは重々承知している。だから謝られるのと同じくらい礼を言われるのはあまり好きじゃない、つまりそういうことだ。どちらの行為も単なる本人の自己完結の手段にしか感じられないからだ。けれど、今は、この少年に素直に自己完結させてやってもいいかな、と思った。彼はこう言うことできっと、ゆらぐ細い自分を支えるのだろう。いつものギリシェなら、礼を言われるのは好かない、くらいはつい言ってしまうけれど。
「あれね、」
少年はグリーグの翼を指差す。
「片方しかないでしょ?もう片方はね、転生に使ったらしいんだよね」
「転生?」
「生まれ変わる、ってこと。僕達の魂は、君達もきっとそうだと思うけれど、この体の成分すべてが一つの魂を構成しているんだ。魂は光から生まれて光に還る。ほら、あの太陽」
少年は梢から微かに見える、世界の昼を照らす丸い光を指差した。
「【人々】の死生観がどうなってるのかはよく知らないけどさ、この世で生きていると、魂は汚れも吸っていくんだ。だから老いて行くし、いつかは摩耗して死んでしまう。だけど生まれ変わって、もう一度同じ存在になることはできる。死ぬ時は体のすべてを太陽にお返しするんだよ。あそこでもう一度綺麗に体を掃除してもらって、もう一回生まれてくる。だけど、体の何かを失ったままだったり、逆に要らないものを持っていってしまうと少しずつ違うものが魂に混じっていくんだ。生まれ変わった時、前とは違う魂になってしまってる。別人になるんだ。だから僕達鳥は、体の全てを必ず太陽に還す。火葬する人々がかわいそうだな、ってときどき思うよ。君達は必ず魂を構成する何かを無くしたまま生まれ変わっていくから、きっといつかは魂もなくなっちゃって、何者にもなれなくなるんだろうね。世界から消えてしまうんだろう。
「まあ、それはいいとして、とにかく、普通は両翼含めて体全部使って生まれ変わるのに、なぜかグリーグ様はああして羽を片方だけ残していったんだ。理由は僕にはよくわからないんだけど・・・なんでなんだろう。だけどこうして鮮度を保つようにこの中に閉じ込めているってことはね、きっとまた何かに使うつもりなんだ。多分・・・生まれ変わってきた子に役立てるんだと思う」
少年は口元に手を置いて何事か考え込む。
「ただこの辺は機密事項らしくて外部には漏らされてないし、僕もこれを見て初めてその可能性を思いついただけだから、全然分かんないんだけど」
なんでそういう重要なことをよそ者の僕に話してんの?という突っ込みはしないほうがいいんだろうな、とギリシェは心の中でだけ思う。そもそも、ここに自分を連れてきている時点で非常におかしい。見れて悪かったとは思わないけれど、どうしてこの少年は自分にこれを見せたのだろうかと思わずにはいられない。
とはいえ、見せられて見てしまったもの、聞いてしまったものはもうどうしようもないのだから、ギリシェはそれ以上は深く追求しないでおくことにした。ギリシェが黙っていると、少年は困ったように微笑んだ。
「ほんと、変な子だね、何で僕が君にこれを見せたかって聞かないの?」
―ああ、これは聞かなきゃいけなかったわけ。
人との対話は加減が難しいな、と思いながら心の中でだけ嘆息した。
「見てしまったものをなかったことに出来るわけじゃないだろ」
思ったままを答えると、少年は吹き出した。
「まあ、そう、だけどさ!」
くすくすと笑いをこらえている。
「なんだかものすごく君面白いね。おおらかだね!なんだか新鮮」
「いや、多分僕が普通より変わってるだけだから」
自分が人間一般に対して思いやる必要はないのだけれど、一応申し訳程度に言い訳をしておく。少なくともギリシェ自身は自分が一般的な感覚を持てていないことくらいは認識できている。
「鳥にもいないよ、君みたいなの」
少年はにっこり笑った。
「あ、そうだ、名前聞いてなかったや。なんて言うの?僕はシンシア。さっき君に気色悪く迫ってたキシュキってやつの弟なんだ」
「似てないな、顔が」
「顔以外は似てるって言いたいの?心外なんだけどちょっと」
シンシアは少し口をとがらせる。男らしくなりたいと言った傍からその仕草はどうなのだろうと少し思ったりする。
「兄さんには気をつけてね。あの人自分の研究しか頭にないから、目をつけられてる君は相当執着されるはずだよ、なんの目的かは知らないけどさ」
シンシアはあさっての方向を見たまま言った。
「僕はギリシェ。見ての通り人」
シンシアはまた吹き出した。
とりあえず放っておいて、改めてギリシェは自分の周りの世界を見渡してみた。
瞼を閉じても、その裏側に陽の光を透かして緑の色が映り揺れる。緑は嫌いじゃなかった。自分が溶け込める気がする。誰にも見つかることもなく、誰にも邪魔されることなく。
ただ静かに暮らしたいだけだ。それだけだ。誰と関わりたいわけでもない。
とはいえ、シンシアとの最初は不毛に思えた会話も、意外と楽しかったかなと思ったりした。
「人間は火葬したり土葬したり水葬したり、いろいろするけど」
ギリシェはふと、これだけは言っておこうと思って口を開く。
「僕の生まれた地方では土葬だったから他のことはよくは知らないけどさ、多分目的は一緒だと思う。土葬することで、体が土に還る、って考え方。大地の一部になるんだ。自然の一部になって、循環して、命が廻る。そういう考え方をしてる。だから多分、根本的に死生観はやっぱり違うんだと思う」
シンシアは戸惑ったように眉をひそめた。
「何それ。自然になって満足してるの?それって自己満足じゃない?元々あった自然の、土や木や風たちのありようをそうすることで少しずつ変えていってるってことでしょう?いつか摩耗しちゃうよ。人ったらなんてもったいないことをするんだろ」
「そもそもたしか、自然っていう大きな塊の一部が人間になったって考え方じゃなかったっけな」
ギリシェは記憶を頼りに呟く。聖書の暗記をさせられたのなんて物心がつくかつかないかのことだから、うろ覚えだ。
「だから、多分それで摩耗したりはしない。むしろ世界のあるがままに直してるつもりだと思う。人は全体的に捉えてるんだろ。で、あんた達は個を捉えてるってこと。僕から言わせれば結局どっちも自己本位で自己満足な結論のように思うけど」
「なぜ?」
シンシアが不安そうに小さな声で問う。
ギリシェは答えなかった。特に理由なんてない。ただ、なんだから苛々するだけだ。綺麗事なんかどうでもいいのだ。そんなものあったって今生きている瞬間が幸せでいられるわけでもなし。ギリシェはおもむろに自分の掌を見つめる。何度も赤黒く生ぬるい液体で汚れてきたそれは、今は何事もなかったように白く滑らかだ。なんてくだらない。生まれ変わるとか役に立つとか還るとか、どうだっていい。少なくとも死んだら終わりなことだけがわかっている。それがすべてだ。
「帰ろうか」
ギリシェは言った。一体いつこの時間は終わるのかな、と思っていた。そろそろ限界だ。別にシンシアといた時間が嫌だったわけではない。ただ、漫然と時が一つの場所で過ぎていくのは大嫌いだった。温いものは大嫌いだ。痛いくらいでちょうどいい。痛覚が刺激されていれば満足だ。熱くても冷たくても。なんだっていいのだ。早く終われと思う。小さな時間の切片がとめどなく繋がり続けばいい。それでようやくギリシェは生きていると感じられる。死にたくはない。
シンシアはギリシェの顔を覗き込んで、頬をひっぱりやがった。
「何」
「怖い顔しているんだもの」
「怖い顔して何が悪いわけ」
「・・・悪かないかもだけど、なんか、こう」
シンシアの言葉は尻切れトンボになった。肩をすくめる。
「ほんと、変な子」
無理やり完結させた。ギリシェは今度こそため息をついた。
ふと、背中の内側を、斜めにざらりとした感触が走って行った。
―何だ?
それは、左の肩甲骨の辺りだったようにも思う。気色悪かった。つい振り返ったが、自分の背中が見えるわけがない。見えたのはピルミラの奥でぼんやりと透けるグリーグの翼だけだ。
もしも体を内側から誰かに撫でられたらこんな感覚なんだろうか、といい加減なことを考える。奇妙な違和感は脳に残り続けた。気色悪い。
「なんで君をここに連れてくる気になったかっていうとね、」
シンシアはギリシェの様子には気付かなかったようにのんびりと言葉を紡ぐ。
「最初は君のこと興味本位で覗いたんだ。だって、兄さんが最近下界に降りて行ったって聞いて、どうやら誰かを連れて帰ってきたらしいって噂で、何事だろうかと思って。もしも人に惚れた子でもいるんならからかってやろうとか顔拝んでみたいとか思ってさ、ほら、僕の友達にそういう子いるじゃない?」
―いや、いるじゃない、って言われても僕知らないから。
もはやつっこむのも面倒だ。
「でもまあ、男の子だったから、なんだ、って思って、やっぱり兄さんって研究にしか興味ないんだな、さっさと腰落ちつけろよこん畜生この目ざわりとか思ったわけなんだけどまあそれはいいとして、」
シンシアははあ、と深く嘆息する。
「わざわざこうして何者でもない人間をここに連れてくるのはありえないと思ったんだ。ということは何かしら君には重大な秘密があって・・・兄さんのもっぱらの興味と照らし合わせた結果、グリーグ様に関することに君がかかわりがあるんじゃないかって思って。僕もこう見えてあの鬼畜兄貴の弟だからね、馬鹿じゃないんだ」
「誰も馬鹿とは言ってないけど」
疲れたようにギリシェが言うと、シンシアはにっこりと笑う。
「で、もしもそうなら遅かれ早かれ、君がここに連れてこられる可能性もなくはないと思うんだ。あの人はグリーグ様のキチガイ信者だから、きっと君は何の知識もないままここに連れてこられても、兄さんに言いくるめられて、兄さん達に言いように使われてしまうんじゃないかと思って。だから連れてきた。まあ、僕がずっとずっと、ここをせっかく自力で見つけたのに誰にも自慢できなくて欲求不満がたまってたっていうのもあるけど」
「あんたさ、」
「シンシア」
「・・・とにかく、僕はあんた達鳥にとっては支配層、究極的にいえばただの僕で奴隷身分の人間なんだけど。特に僕はその中でも多分底辺以下の位置づけなわけ。なのにまるで、自分と同等扱いするんだな。なんで?」
「なんで名前で呼んでくれないの?」
「は・・・だから、僕が今聞きたいのはそういうことじゃ」
「呼んでよ。なんか気持ち悪い」
気持ち悪いのはこっちだと言いたい。ギリシェは下唇をかんだ。
「そもそも初対面のくせしてここまでだらだら話してたこと自体非常なんだよ。そこまであんたと僕は親しいわけでもないだろうが」
まあ少々親しいからって名前で呼んでやる義理もないのだが。基本的にギリシェは人の名前を覚えるのは苦手だ。そもそも覚えるのが好かなかった。今までも、名前はまるでただの物質名のように呼ばれてきた。他と区別するためにただ与えられただけの名前だ。ギリシェの名前を呼ぶ輩がどういう意図でギリシェを呼び利用してきたか思い出したくもないほどに知っていた。だからそういう奴らの名前を覚えたいとも思わない。自分の名前も嫌いなのに、どうして他人の名前を大事にしてやらねばならないのか。
「じゃあ、」
シンシアは喧嘩腰でつんけんとして言った。
「親しくなればちゃんと呼んでくれるね?僕の名前」
「は?」
そうきたか、とギリシェはさらに唇を噛みしめる。なんだか馬鹿らしくなってきた。
「そんな約束してやる義理ないんだけど」
「僕こそ君にそこまで拒否されるいわれはないよ。ほんっと失礼で常識のない人だね」
常識云々言えた立場かと言いたい。そもそもあんたは鳥で僕は人だ。常識なんかあっても同じとは限らないじゃないか。けれどその反論たちは、心の中だけにとどまった。本気で意地を張っていることが馬鹿らしくなった。そうして自分が、子供じみた意地を張っていたこともようやく自覚する。ギリシェは嘆息した。
「はぁ・・・シンシア、いいから僕の聞いたことに答えろって」
シンシアはにやりと笑った。つくづく嫌な奴だ。
「よし、一歩前進。次はシンシィって呼んでね。あ、シアでもいいよ」
「は?」
我ながら驚くほど低い声が出た。
「シンシィ、って前兄さんが可愛かった時僕をそう呼んでたんだよね。あの人今はシア、って呼んでる。僕はどっちでもいいよ。ここでは仲のいい子は愛称で呼ぶ決まりなんだ」
そもそもあんたと仲良くするつもりないから。あとここに長居する気もないから。
ギリシェは応対するのもおっくうになった。
そもそもここまで話がずれると、先の質問の答えをしつこく聞こうとするのさえ馬鹿らしいことに思えてきた。つくづく他人との会話は思い通りに効率よく進まず不便だ。そもそも目の前の相手は人ですらない。
頭が痛い。
「君のこと、そういう風に扱いたくないよ」
シンシアが静かな声で言う。
それが先のギリシェの言葉に対する返答であることに気付くのに少し時間を要した。
「それがなんでかっていうことをつまり僕は聞きたかったんだけどねえ」
もはや苛々した気持ちを隠す気も起きない。シンシアは肩をすくめた。
「うーん、僕にもよくわからないんだけど、なんていうか、僕初めて【羽なし】を見たからさ、よくわからないんだよね。しかも、文字通り羽がないだけで僕らとたいして変わらないじゃん。なんか親近感わいちゃって。僕と同じように、君ったら兄さんにひじょーに興味持たれてる立場みたいだし。他人の気がしないって言うかさ」
「僕は他人の気しかしないな」
「まあ、そう言わないでよ。ていうかそろそろ戻った方がいいかな。よく考えたら君がいないことに誰か気付いたらまずいよね。ま、さっきみたいに兄さんが人払いしたら、少なくとも半刻は誰も部屋に入ろうとはしないだろうけどさ」
シンシアはにこにこしながら言った。一つの木に近付き、根元に片膝を立ててかがむ。よく育った根の一本を、ひょい、と持ち上げた。まるで軟体動物のようにくにゃりと動かされたそれに、ギリシェも多少驚く。シンシアはその下に在った灰色の石をぐい、と押した。途端に勢いよく木が黄色と橙色の光の交錯する線で網状に下から上へと覆われていく。
シンシアは、そっとギリシェの手をとった。
「さあ帰るよ。君、もう少し寝ててもらわないとね。兄さんにばれたら後が大変だ」
触れている手を、嫌だとは思わなかった。ギリシェはいつの間にか、軽く引かれただけの手のままに付いていっていた。網に近付くと、少しだけ網目がほぐれて、光も薄くなった。シンシアがそのまま中に入って見えなくなったので、ギリシェもそのまま後に続く。
キン、という音がして、また視界が反転した。シンシアが羽で自分とギリシェをくるみこんだ。耳の奥まで入り込んでくる機械音のような奇妙な音は相変わらず耳障りだし、目もちかちかして非常に不快だ。けれど来た時ほど自分の体も強張ってはいなかった。慣れたのかもしれない。この装置にも、世界にも、そして、この一見人畜無害そうでそうでもなさそうな少年にも。
ギリシェはそのまま目を閉じた。頭が痛いし体はだるい。まだ本調子ではないらしい。あの暗闇は、よほどギリシェの体力を削ぎ落としていたようだ。
芳しい緑の匂いが遠ざかっていく。
非常に不快だった。
まず、温い。そしてちりちりと耳障りな音がする。
言うなれば腹から嚥下したとき口まで上ってくる胃液の中に体をびしょ濡れにされたような感覚だった。目を見開くこともできなかったけれど閉じ切ることもなんだかできず、そうしているうちに角膜の上を金色と灰色の針金のような光の点線がひどく忙しなく縦に横に斜めに螺旋を描いて動いた。それを見ていただけで気分が悪くなった。そして何より音だ。脳髄にまでじんじんと響いてくるから、耳を塞いだところでほぼ意味はない。ちり、ぎり、がり、とまるで金属で金属を削るようなキーキーとした音がとぎれとぎれにのろのろと鳴った。それらがすべて自分達を包み込んだ。世界は水色と黄色。ところどころ意味のわからない赤橙と橙の色をした球体のような円盤のような半透明のものがぴょんぴょん飛んで行った。
そう長い時間ではなかったのかもしれないけれど、十分にギリシェにとっては疲労の材料になった。
空間が巻貝のようにぐるぐると絞り上げられ、先端の方へ二人は吸いこまれていく。痛くはなかった。自分の周りにねっとりと纏わりついていた温い液体のようなものが体からしぼりとられていくようで、ようやくすう、と息ができたような心地がした。ギリシェは大きくため息をついた。ため息がこんなにも気持ちの良いものだとはついぞ知らなんだ。これからは大いに息を吐くとしよう。
「着いたよー。あはは、相変わらず気色悪かった!」
薄青の髪の少年は妙にすっきりした顔もちで言った。ギリシェは一瞬何を言われたのかわからなくて、止まる。
自分もあまり気持ちよくないなら何故にこの移動手段を使うのかと問いたくないこともなかった。ぐっとこらえる。面倒な会話で時間が浪費されるのは疲れるから嫌いだ。
まずは状況を判断しよう、とギリシェは辺りを見渡した。黙ってそうするのは一種の癖だ。人にいちいち分からないことを聞くのはあまり好きではなかった。わずらわしいからだ。自分の目で見て知ることができることは、意外と多いものだ。もしよくわからなくてもそれは今の自分にはきっと必要がないから分からないのだ。それがギリシェの信条のようなものだった。分からないものは目に焼き付けておけばいい。いつかそれが必要になった時に、それが何だったのかきっと分かるだろう。そう思っている。
一面は緑の森だ。青緑の瑞々しく肉厚な葉の茂った木が地面中に根を張っている。普通の木と違うところ言えば、根にもまた葉がまるで蔦や蔓草の類のように茂っているということだろうか。おかげで地上で見られる草のようなものはないけれど、十分に地面も緑に覆われている。
そして不自然に、ぽっかりと空いた、いや、空けられた空間がある。作為的にも見えるよく伸びた三つの木の枝が絡み合って網をつくり、屋根になっている。その下でその格子の影を映しているのはやや茶色がかった黄色の四角錐の大きな物体だった。その全ての辺と中線もまた、先刻奇妙な空間で見たものとよく似た、赤みのある金色の点線状の光の通路になっている。そしてその四角錐の周りの地面に、ぽつぽつと長方形の白金の薄板が刺さっている。まるで規則性がない並びのように見えて目を細めたら、実はそれらの板は四角錐の建物を中心に据えた見えない正方形の辺上にきちんと立っているのだとわかった。それがわかって改めて眺めると、不整合に見えたそれらの構造が実は綿密な計算のもとに配置されているのだと分かる。地上ではまず見ない様式美だ。少なくとも地上の人間達は均等を好む。対称なものを美しいと直感的に感じる。今目の前にある建築物は、全体としてみれば点対称ですらない。
そして、妙に静かだった。風ひとつ吹いていないのだ。空気はあるはずなのに、居心地が悪くなるような静けさだ。身動きをして音を立ててはいけないかのような心地になる。
意味が分からなかった。結局分かるのは、地上とこの羽のある生物たちの暮らす環境は似ているようで実は全然違うのであろうということ、そして美しいようでどこか怖いものなのだと肌で感じ取れるだけ。
「ここはピルミラ。グリーグ様の社だよ」
少年が、それをじっと見つめながらささやく。
だからグリーグって誰だよ、と思う。鳥達の常識を自分のようなただの人間も当然のように持っているように思わないでほしい。父親なら知っていたかもしれないな、と頭の中で言葉がかすっていって、ギリシェはかぶりを振った。どうでもいいことだ。自分は知らない。それが事実だ。あと、耳元で話すのやめてほしい。
「グリーグ様はもう亡くなってるから、今は誰も住んでないんだけど、ただ、多分ここは保管庫なんだと思う。上の人たちは、文化的遺産であるグリーグ様の住まいの永久的保護のために立ち入り禁止、だなんて言ってるけど、現にあの人たち結構ここにちょこちょこ達言ってるみたいだし、それは多分詭弁だよね。多分、【あれ】を保護してるんだ、ここで。腐らないように」
―【あれ】、ねえ。
だからなんだよ、と思ったりしなくもない。そんなことを自分に話したところでさっぱり意味が分からないのだから非常に不毛だ。無駄だ。
溜息でもつこうかな、と思ったがやめておくことにした。わざわざ人前でするものでもない。あとあと面倒だ。自分はなるべく透明に生きていきたいのだ。
まあ、もう少し人並みに生きていてもいいなら、の話だが。
「多分、【それ】をここから出しちゃいけないのと、僕が外を歩いちゃいけない理由はつながっているんだと思うんだけど、いかんせん兄さんに聞くわけにもいかないから、ばれちゃうから、僕には未だに痒いところに手が届かない気持ちってこういうことなのかなって」
先刻から筋の通らない言葉遣いなやつだな、とギリシェは思った。そうしてふと、なんでこいつら、羽があるのに歩くんだろう、と思ったりした。そういえばキシュキと名乗った青年も女中も羽があるくせに床をぺたぺたと歩いていたように記憶している。
ふと、少年は不思議そうにギリシェの顔を覗き込んだ。いちいち距離が近い。まあだからと言ってひるむわけでもないのだが。少々のことでは動じない癖がついてしまっている。
「君、変な子」
「は?」
つい相手をしてしまった。
「だって、さっきからずっと取り乱すこともなくだんまりなんだもん。臆してるわけじゃないんだよね?人ってみんなそうなの?」
「さあ」
「さあって」
「僕に人類一般の傾向を語れと言われてもな。言うほど経験積んでないもん」
「そうなの?」
ふーん、と少年は一人で納得したようだった。そうして唐突ににっこりと嬉しそうな笑顔を浮かべる。
何、と思ったりする。
「えへへ、でもなんだか楽だな!僕が一人でしゃべってても変な空気にならないしね!やっぱり相手がいるっていいことだよね。一人きりの時ぶつぶつ独り言言っててたまに無性に恥ずかしくなる時あるんだよね」
そこまできちんと耳を傾けてもいないんだけど、と心の中でだけ応対して、ギリシェはそのまま四角錐の方へ視線を戻した。
なんだろう。最初の衝撃が薄れると、だんだん愛着がわいてくるというか、この形がどこか可愛いものに思えてくる。何の変哲もない図形の塊なのに、奇妙な感覚なことだ。
上手い言葉が見つからないけれど、少なくとも警戒心があおられたりはしない。この場所にいると、神経を張り詰めようとする気が削がれていく。
「あのね、ちょっとついてきてよ」
少年はさらりと言うと、そのままピルミラの方へ近づいていく。その足取りを見ながら、やっぱり人よりも足取りに重さがないんだな、とギリシェは少しだけ思う。
着いていかない理由もないけれどついていかなければならない理屈もないんだけどな、などと思いながらギリシェは大人しくその後ろを着いて行った。
「ほら、こっち。ここまで寄ってみて」
少年は手招きする。ピルミラの壁にぴったりと鼻と手を寄せて中を食い入るように見る。
ギリシェも、さすがにそこまではしなかったが少年の肩の後ろから覗いてみた。
離れた所からは分からなかったが、ピルミラの壁は透明で、中が見えるようになっていた。点線の光がちらちらとせわしなく動いて交錯するので鬱陶しかったりする。
けれど、その光達が載る物、内部の中央に浮かんでいるそれは、綺麗だと思った。
片翼だ。
はっきりとした色は壁の色に透かされてよくわからないけれど、光沢や影の度合いでかなりいろんな色の混じった翼なのだろうとは分かった。朱子織のようになめらかで柔らかそうだ。こうして見るだけでも、収集品に興味のないギリシェでさえ惹きつけられるものがある。魅入るとでも言うのだろうか。
「あれ?」
ギリシェはふと呟いた。よく考えてみれば、その翼はキシュキ達のような翼とは全く違うものだ。どちらかと言えば―美しさは劣るにしても―目の前にいるこの線の細い少年の翼に近い。
「鳥の翼ってやつは、いろんな種類があるんだな」
ギリシェは多分、少年に対しては初めて自分から声をかけてみる。
少年は目を丸くして振り返る。しばらくじっとギリシェの目を見つめた後、なぜか顔を赤らめてうつむいた。何故そこではにかむ必要があるのかギリシェにはよく分からない。奇妙奇天烈とはこのことだな、と呑気にそんなことを考える。
「僕のは・・・ううん、違うんだ、僕のは、ちょっと、特別なんだ。特別っていうか、奇形と言った方が正しいんじゃないかな・・・あ、グリーグ様の翼が奇形だなんて言ってないよ!?だってグリーグ様はあの翼でちゃんと飛べた。僕は飛べない。あんなに美しくもない。だから僕は多分奇形だ」
少年はぼそぼそと言う。どこか覇気がなかった。
まあ絶対に気にかけなければいけないことでもないはずなので、とりあえずギリシェは頭の中で少年の発言を整理する。
察するに、このピルミラの中にある翼はグリーグという奴の翼と言うことだろうか。そして、様と呼ばれるからにはなかなか立場の偉い人物なのだろう。そういえばもう死んだとか言っていたような気がする。つまり翼を片方だけぶった切ってここに押し込んでいるということか。見た目は綺麗だが意外と鳥達も残酷な―いや、思い切ったことをするもんなんだな、と少しだけ思う。少なくとも自分の知っている限りでは、地上の人間は敬意を表している相手の体を切断したりはしないはずだ。
ギリシェは少年の髪色と同じ柔らかで薄い翼をじっと眺めた。奇形、ねえ。
たしかにまるで女の服みたいな布が申し訳程度についているくらいのようなものだから、あってもなくてもよさそうだとも思う。けれど同時に純粋に綺麗だとも思った。もしも少年の背からこのなめらかな布のような翼がなくなってしまったら、なんだか心もとない感じだ。この翼があるから少年は鳥なのだ。人のような何の変哲もない生き物ではない。美しいものなのだ。大鷲のような翼も似合っただろうとは思うけれど、この翼は個人的に嫌いではない。
何か言った方がいいかと思って言葉を探す。けれど、変に慰めていると受け取られたくはない。単に思ったことを言いたくなっただけなのだから。
結局、何を言っても嘘くさくなりそうで、ギリシェは黙って少年の頭を撫でた。翼に触れようかとも思ったが、知覚はあるはずだ。下手に触って痛かったらよくない。
少年は戸惑ったように身をすくめていたが、やがて肩の力を抜いた。まるで野良猫を懐かせたような気分になる。
「ほんとはね、」
少年はグリーグの翼であろうものに視線を戻して静かに続けた。
「僕は自分のこの羽に、劣等感を、みじめさを感じてもいるし、ちょっと酔ってもいるんだ。
「僕のこの翼だけが、グリーグ様のものとそっくりで、他の【鳥】たちはみんなただの鳥と同じものしか持っていない。僕が自分を卑下するのもただの申し訳で、本当は心の奥底で、自己満足してるよ。だって僕の翼はグリーグ様と同じなんだ。みんなよりもずっと綺麗だし希少価値があって。だけどこんな風におごっている自分が気持ちよくもあるけど嫌いでもあるんだ。だから僕は人前では自分を卑下しないではいられないし、自分を奇形だって言わずにはいられない。自分で言って自分で傷ついて、一人になった時に自分に言い訳するんだ。だけど僕は綺麗な子だからいいんだって。慰めるみたいにさ。だけど僕は・・・綺麗なものになりたいんじゃなくて、かっこよくなりたいんだ。女みたいに儚いって言われても全然嬉しくなかったよ。僕は男らしくなりたいだけなんだけどな。骨太っていうかさ。兄さんは趣味がちょっとおかしいからなぁ。線が細けりゃいいって思ってる」
少年は、小さく嘆息した。中腰になっていた体を起こす。
「うん、満足した。聞いてくれてありがとう」
ギリシェは少しだけ顔をしかめた。礼を言われるのはなんだか居心地が悪い。言われ慣れていないのだ。なんだか腹立つし、妙な気持ちになる。
ギリシェは自分が捻くれているのは重々承知している。だから謝られるのと同じくらい礼を言われるのはあまり好きじゃない、つまりそういうことだ。どちらの行為も単なる本人の自己完結の手段にしか感じられないからだ。けれど、今は、この少年に素直に自己完結させてやってもいいかな、と思った。彼はこう言うことできっと、ゆらぐ細い自分を支えるのだろう。いつものギリシェなら、礼を言われるのは好かない、くらいはつい言ってしまうけれど。
「あれね、」
少年はグリーグの翼を指差す。
「片方しかないでしょ?もう片方はね、転生に使ったらしいんだよね」
「転生?」
「生まれ変わる、ってこと。僕達の魂は、君達もきっとそうだと思うけれど、この体の成分すべてが一つの魂を構成しているんだ。魂は光から生まれて光に還る。ほら、あの太陽」
少年は梢から微かに見える、世界の昼を照らす丸い光を指差した。
「【人々】の死生観がどうなってるのかはよく知らないけどさ、この世で生きていると、魂は汚れも吸っていくんだ。だから老いて行くし、いつかは摩耗して死んでしまう。だけど生まれ変わって、もう一度同じ存在になることはできる。死ぬ時は体のすべてを太陽にお返しするんだよ。あそこでもう一度綺麗に体を掃除してもらって、もう一回生まれてくる。だけど、体の何かを失ったままだったり、逆に要らないものを持っていってしまうと少しずつ違うものが魂に混じっていくんだ。生まれ変わった時、前とは違う魂になってしまってる。別人になるんだ。だから僕達鳥は、体の全てを必ず太陽に還す。火葬する人々がかわいそうだな、ってときどき思うよ。君達は必ず魂を構成する何かを無くしたまま生まれ変わっていくから、きっといつかは魂もなくなっちゃって、何者にもなれなくなるんだろうね。世界から消えてしまうんだろう。
「まあ、それはいいとして、とにかく、普通は両翼含めて体全部使って生まれ変わるのに、なぜかグリーグ様はああして羽を片方だけ残していったんだ。理由は僕にはよくわからないんだけど・・・なんでなんだろう。だけどこうして鮮度を保つようにこの中に閉じ込めているってことはね、きっとまた何かに使うつもりなんだ。多分・・・生まれ変わってきた子に役立てるんだと思う」
少年は口元に手を置いて何事か考え込む。
「ただこの辺は機密事項らしくて外部には漏らされてないし、僕もこれを見て初めてその可能性を思いついただけだから、全然分かんないんだけど」
なんでそういう重要なことをよそ者の僕に話してんの?という突っ込みはしないほうがいいんだろうな、とギリシェは心の中でだけ思う。そもそも、ここに自分を連れてきている時点で非常におかしい。見れて悪かったとは思わないけれど、どうしてこの少年は自分にこれを見せたのだろうかと思わずにはいられない。
とはいえ、見せられて見てしまったもの、聞いてしまったものはもうどうしようもないのだから、ギリシェはそれ以上は深く追求しないでおくことにした。ギリシェが黙っていると、少年は困ったように微笑んだ。
「ほんと、変な子だね、何で僕が君にこれを見せたかって聞かないの?」
―ああ、これは聞かなきゃいけなかったわけ。
人との対話は加減が難しいな、と思いながら心の中でだけ嘆息した。
「見てしまったものをなかったことに出来るわけじゃないだろ」
思ったままを答えると、少年は吹き出した。
「まあ、そう、だけどさ!」
くすくすと笑いをこらえている。
「なんだかものすごく君面白いね。おおらかだね!なんだか新鮮」
「いや、多分僕が普通より変わってるだけだから」
自分が人間一般に対して思いやる必要はないのだけれど、一応申し訳程度に言い訳をしておく。少なくともギリシェ自身は自分が一般的な感覚を持てていないことくらいは認識できている。
「鳥にもいないよ、君みたいなの」
少年はにっこり笑った。
「あ、そうだ、名前聞いてなかったや。なんて言うの?僕はシンシア。さっき君に気色悪く迫ってたキシュキってやつの弟なんだ」
「似てないな、顔が」
「顔以外は似てるって言いたいの?心外なんだけどちょっと」
シンシアは少し口をとがらせる。男らしくなりたいと言った傍からその仕草はどうなのだろうと少し思ったりする。
「兄さんには気をつけてね。あの人自分の研究しか頭にないから、目をつけられてる君は相当執着されるはずだよ、なんの目的かは知らないけどさ」
シンシアはあさっての方向を見たまま言った。
「僕はギリシェ。見ての通り人」
シンシアはまた吹き出した。
とりあえず放っておいて、改めてギリシェは自分の周りの世界を見渡してみた。
瞼を閉じても、その裏側に陽の光を透かして緑の色が映り揺れる。緑は嫌いじゃなかった。自分が溶け込める気がする。誰にも見つかることもなく、誰にも邪魔されることなく。
ただ静かに暮らしたいだけだ。それだけだ。誰と関わりたいわけでもない。
とはいえ、シンシアとの最初は不毛に思えた会話も、意外と楽しかったかなと思ったりした。
「人間は火葬したり土葬したり水葬したり、いろいろするけど」
ギリシェはふと、これだけは言っておこうと思って口を開く。
「僕の生まれた地方では土葬だったから他のことはよくは知らないけどさ、多分目的は一緒だと思う。土葬することで、体が土に還る、って考え方。大地の一部になるんだ。自然の一部になって、循環して、命が廻る。そういう考え方をしてる。だから多分、根本的に死生観はやっぱり違うんだと思う」
シンシアは戸惑ったように眉をひそめた。
「何それ。自然になって満足してるの?それって自己満足じゃない?元々あった自然の、土や木や風たちのありようをそうすることで少しずつ変えていってるってことでしょう?いつか摩耗しちゃうよ。人ったらなんてもったいないことをするんだろ」
「そもそもたしか、自然っていう大きな塊の一部が人間になったって考え方じゃなかったっけな」
ギリシェは記憶を頼りに呟く。聖書の暗記をさせられたのなんて物心がつくかつかないかのことだから、うろ覚えだ。
「だから、多分それで摩耗したりはしない。むしろ世界のあるがままに直してるつもりだと思う。人は全体的に捉えてるんだろ。で、あんた達は個を捉えてるってこと。僕から言わせれば結局どっちも自己本位で自己満足な結論のように思うけど」
「なぜ?」
シンシアが不安そうに小さな声で問う。
ギリシェは答えなかった。特に理由なんてない。ただ、なんだから苛々するだけだ。綺麗事なんかどうでもいいのだ。そんなものあったって今生きている瞬間が幸せでいられるわけでもなし。ギリシェはおもむろに自分の掌を見つめる。何度も赤黒く生ぬるい液体で汚れてきたそれは、今は何事もなかったように白く滑らかだ。なんてくだらない。生まれ変わるとか役に立つとか還るとか、どうだっていい。少なくとも死んだら終わりなことだけがわかっている。それがすべてだ。
「帰ろうか」
ギリシェは言った。一体いつこの時間は終わるのかな、と思っていた。そろそろ限界だ。別にシンシアといた時間が嫌だったわけではない。ただ、漫然と時が一つの場所で過ぎていくのは大嫌いだった。温いものは大嫌いだ。痛いくらいでちょうどいい。痛覚が刺激されていれば満足だ。熱くても冷たくても。なんだっていいのだ。早く終われと思う。小さな時間の切片がとめどなく繋がり続けばいい。それでようやくギリシェは生きていると感じられる。死にたくはない。
シンシアはギリシェの顔を覗き込んで、頬をひっぱりやがった。
「何」
「怖い顔しているんだもの」
「怖い顔して何が悪いわけ」
「・・・悪かないかもだけど、なんか、こう」
シンシアの言葉は尻切れトンボになった。肩をすくめる。
「ほんと、変な子」
無理やり完結させた。ギリシェは今度こそため息をついた。
ふと、背中の内側を、斜めにざらりとした感触が走って行った。
―何だ?
それは、左の肩甲骨の辺りだったようにも思う。気色悪かった。つい振り返ったが、自分の背中が見えるわけがない。見えたのはピルミラの奥でぼんやりと透けるグリーグの翼だけだ。
もしも体を内側から誰かに撫でられたらこんな感覚なんだろうか、といい加減なことを考える。奇妙な違和感は脳に残り続けた。気色悪い。
「なんで君をここに連れてくる気になったかっていうとね、」
シンシアはギリシェの様子には気付かなかったようにのんびりと言葉を紡ぐ。
「最初は君のこと興味本位で覗いたんだ。だって、兄さんが最近下界に降りて行ったって聞いて、どうやら誰かを連れて帰ってきたらしいって噂で、何事だろうかと思って。もしも人に惚れた子でもいるんならからかってやろうとか顔拝んでみたいとか思ってさ、ほら、僕の友達にそういう子いるじゃない?」
―いや、いるじゃない、って言われても僕知らないから。
もはやつっこむのも面倒だ。
「でもまあ、男の子だったから、なんだ、って思って、やっぱり兄さんって研究にしか興味ないんだな、さっさと腰落ちつけろよこん畜生この目ざわりとか思ったわけなんだけどまあそれはいいとして、」
シンシアははあ、と深く嘆息する。
「わざわざこうして何者でもない人間をここに連れてくるのはありえないと思ったんだ。ということは何かしら君には重大な秘密があって・・・兄さんのもっぱらの興味と照らし合わせた結果、グリーグ様に関することに君がかかわりがあるんじゃないかって思って。僕もこう見えてあの鬼畜兄貴の弟だからね、馬鹿じゃないんだ」
「誰も馬鹿とは言ってないけど」
疲れたようにギリシェが言うと、シンシアはにっこりと笑う。
「で、もしもそうなら遅かれ早かれ、君がここに連れてこられる可能性もなくはないと思うんだ。あの人はグリーグ様のキチガイ信者だから、きっと君は何の知識もないままここに連れてこられても、兄さんに言いくるめられて、兄さん達に言いように使われてしまうんじゃないかと思って。だから連れてきた。まあ、僕がずっとずっと、ここをせっかく自力で見つけたのに誰にも自慢できなくて欲求不満がたまってたっていうのもあるけど」
「あんたさ、」
「シンシア」
「・・・とにかく、僕はあんた達鳥にとっては支配層、究極的にいえばただの僕で奴隷身分の人間なんだけど。特に僕はその中でも多分底辺以下の位置づけなわけ。なのにまるで、自分と同等扱いするんだな。なんで?」
「なんで名前で呼んでくれないの?」
「は・・・だから、僕が今聞きたいのはそういうことじゃ」
「呼んでよ。なんか気持ち悪い」
気持ち悪いのはこっちだと言いたい。ギリシェは下唇をかんだ。
「そもそも初対面のくせしてここまでだらだら話してたこと自体非常なんだよ。そこまであんたと僕は親しいわけでもないだろうが」
まあ少々親しいからって名前で呼んでやる義理もないのだが。基本的にギリシェは人の名前を覚えるのは苦手だ。そもそも覚えるのが好かなかった。今までも、名前はまるでただの物質名のように呼ばれてきた。他と区別するためにただ与えられただけの名前だ。ギリシェの名前を呼ぶ輩がどういう意図でギリシェを呼び利用してきたか思い出したくもないほどに知っていた。だからそういう奴らの名前を覚えたいとも思わない。自分の名前も嫌いなのに、どうして他人の名前を大事にしてやらねばならないのか。
「じゃあ、」
シンシアは喧嘩腰でつんけんとして言った。
「親しくなればちゃんと呼んでくれるね?僕の名前」
「は?」
そうきたか、とギリシェはさらに唇を噛みしめる。なんだか馬鹿らしくなってきた。
「そんな約束してやる義理ないんだけど」
「僕こそ君にそこまで拒否されるいわれはないよ。ほんっと失礼で常識のない人だね」
常識云々言えた立場かと言いたい。そもそもあんたは鳥で僕は人だ。常識なんかあっても同じとは限らないじゃないか。けれどその反論たちは、心の中だけにとどまった。本気で意地を張っていることが馬鹿らしくなった。そうして自分が、子供じみた意地を張っていたこともようやく自覚する。ギリシェは嘆息した。
「はぁ・・・シンシア、いいから僕の聞いたことに答えろって」
シンシアはにやりと笑った。つくづく嫌な奴だ。
「よし、一歩前進。次はシンシィって呼んでね。あ、シアでもいいよ」
「は?」
我ながら驚くほど低い声が出た。
「シンシィ、って前兄さんが可愛かった時僕をそう呼んでたんだよね。あの人今はシア、って呼んでる。僕はどっちでもいいよ。ここでは仲のいい子は愛称で呼ぶ決まりなんだ」
そもそもあんたと仲良くするつもりないから。あとここに長居する気もないから。
ギリシェは応対するのもおっくうになった。
そもそもここまで話がずれると、先の質問の答えをしつこく聞こうとするのさえ馬鹿らしいことに思えてきた。つくづく他人との会話は思い通りに効率よく進まず不便だ。そもそも目の前の相手は人ですらない。
頭が痛い。
「君のこと、そういう風に扱いたくないよ」
シンシアが静かな声で言う。
それが先のギリシェの言葉に対する返答であることに気付くのに少し時間を要した。
「それがなんでかっていうことをつまり僕は聞きたかったんだけどねえ」
もはや苛々した気持ちを隠す気も起きない。シンシアは肩をすくめた。
「うーん、僕にもよくわからないんだけど、なんていうか、僕初めて【羽なし】を見たからさ、よくわからないんだよね。しかも、文字通り羽がないだけで僕らとたいして変わらないじゃん。なんか親近感わいちゃって。僕と同じように、君ったら兄さんにひじょーに興味持たれてる立場みたいだし。他人の気がしないって言うかさ」
「僕は他人の気しかしないな」
「まあ、そう言わないでよ。ていうかそろそろ戻った方がいいかな。よく考えたら君がいないことに誰か気付いたらまずいよね。ま、さっきみたいに兄さんが人払いしたら、少なくとも半刻は誰も部屋に入ろうとはしないだろうけどさ」
シンシアはにこにこしながら言った。一つの木に近付き、根元に片膝を立ててかがむ。よく育った根の一本を、ひょい、と持ち上げた。まるで軟体動物のようにくにゃりと動かされたそれに、ギリシェも多少驚く。シンシアはその下に在った灰色の石をぐい、と押した。途端に勢いよく木が黄色と橙色の光の交錯する線で網状に下から上へと覆われていく。
シンシアは、そっとギリシェの手をとった。
「さあ帰るよ。君、もう少し寝ててもらわないとね。兄さんにばれたら後が大変だ」
触れている手を、嫌だとは思わなかった。ギリシェはいつの間にか、軽く引かれただけの手のままに付いていっていた。網に近付くと、少しだけ網目がほぐれて、光も薄くなった。シンシアがそのまま中に入って見えなくなったので、ギリシェもそのまま後に続く。
キン、という音がして、また視界が反転した。シンシアが羽で自分とギリシェをくるみこんだ。耳の奥まで入り込んでくる機械音のような奇妙な音は相変わらず耳障りだし、目もちかちかして非常に不快だ。けれど来た時ほど自分の体も強張ってはいなかった。慣れたのかもしれない。この装置にも、世界にも、そして、この一見人畜無害そうでそうでもなさそうな少年にも。
ギリシェはそのまま目を閉じた。頭が痛いし体はだるい。まだ本調子ではないらしい。あの暗闇は、よほどギリシェの体力を削ぎ落としていたようだ。
芳しい緑の匂いが遠ざかっていく。
三、
キシュキ=レシラの部屋は、青を基調としている。
これでもかというくらいに全てを青で統一している。唯一青でないとすれば、白い天井と、白木でできた机、寝台くらいのものだった。それだって青の模様がひしめき合っている。
【研究】や【気晴らし】といった名目、私用で使う全ての部屋をただ一色で揃えるのは彼の趣味だった。違う色が混じっていると気持ちが悪いのだそうだ。気になって集中ができない、という。何かひらめくとその場で計算に没頭してしまう彼の行動傾向と照らし合わせれば、まあ納得ができないこともない。
それでも正直悪趣味だと思う。ここまでくるといっそすがすがしい気持ちの悪さだ。客間に使う部屋は色がいくつかあるだけでまだましだが、それでも悪趣味なことに変わりはない。もう少し質素にしてもいいのではないかと思う。ごてごてしすぎている。それはもう、目に痛いくらいに。
おかげでこの屋敷に働く者で長続きした者はそうそういないし、弟子入りを志願してきた【鳥】達もたった一人の例外を除いて全て泡食って逃げ出した。特にかわいそうだったのが、真っ白な部屋をあてがわれた子だ。数日のうちに気が狂ったように泣き叫び、這うように出て行った。あの部屋は、少年も苦手だ。何の拷問かと思う。なのにキシュキ=レシラがやけに気にいっているから余計に性質が悪い。
少年―イース=イーダに言わせれば、キシュキ=レシラはほぼきちがいだった。
弟は弟で性格が捻くれている。ろくな兄弟ではない。なぜ自分が未だにこの二人と関わりを持っているのか自分で不思議だ。感心する。我がことながら。
そもそも自分から好んできたわけではない。ただ、ここに居続ける面倒よりもここから出てまた奉公先を探すことの方が手間のように思えたのでそのままにしているだけだ。弟の方は別としても正直兄の方にはこれっぽっちも思い入れはない。
とはいえ、学のなかった自分に一から教えてくれたのもキシュキ=レシラだった。頼んだわけでもなかったが迷惑だったわけでもない。
今日もまた、キシュキ=レシラは何やら楽しそうに計算をしている。キシュキ自身が勝手に改造した電子頭脳の画面が、青と黄色の光をちかちかと点滅させている。同じ部屋でイース=イーダもまた、床に座り込んで小型の携帯式電子頭脳の画面に電子筆を走らせていた。キシュキが何をしているのはさして興味がないが、イース=イーダがやっているのは中級程度の数字遊戯盤だ。81個のマスがあって、ところどころに数字が不規則に並んでいる。縦と横、そして9マス単位の区画それぞれに当てはまる数字には規則性がある。空欄のマスに適した数字を入れなければならないのだが、さすがに中級編は難しかった。しかもこれを作っているのがキシュキを筆頭としたアルクメネの集団だから、なおのことなんだか憎々しい。
しかもキシュキは鼻歌まで歌いだした。やっぱりうっとうしい。
初級編で掴みかけたと思ったこつが、中級編ともなるとほぼ役に立たなかった。イース=イーダはため息をつく。
「どう?諦めた?」
キシュキが椅子をくるりと回旋させ、腹立たしいくらいに満面の笑みを浮かべる。
「これほんとに俺解けるのかよ。知らない定理とかほんとは使われてんじゃないの?」
「いやいや、君の知ってる知識をこねくり回せば解ける問題だよ。もちろんまあ、もう一つ上の段階の知識を持っていれば簡単ではあるんだけどね。でもそんなの意味ないし、面白くないでしょ」
「解けない時点で面白くもなんともないんだけど」
「解けたらきっとすっきりするよ」
「だからさぁ、いきなりこんな応用問題出されても解き方分かんないっての。初級は公式当てはめりゃ解けたのになんだよこの問題。鬼畜だろ」
「公式丸暗記なんて面白くもなんともないじゃない。それにね、イース、僕達がやってる研究なんかもっと人生悲観したくなるくらい複雑な応用の迷路なんだらからね?」
「誰もそんなとこまで望んでないから」
イース=イーダは嘆息した。キシュキは肩をすくめる。
「君はいい素質持ってるから、ここで終わらせたくないんだよねえ。だからこうして君に手とり足とり教えてるんじゃないか」
「自分の弟にしとけよ、ったく」
「まあねえ。シアはさすが僕の弟で馬鹿ではないんだけど、やっぱり僕の方がどうしたって上なんだよねえ」
「ろくな教育もしてないくせによく言うよ。赤の他人にはこうして教育するくせに」
「あの子の役割はそういう方面じゃないからね。適材適所、って言うでしょ」
そういう考え方は、理にはかなっているのかもしれないとは思う。けれど、イース=イーダは好きではなかった。シンシア=レシラが、何も与えてもらえず何を望むことも許されないまま、世に緩く失望し惰性で生きているのを知っている。彼の心を揺さぶるものがこの世界には何もない。何も与えてもらえない。
「仕方ないね、じゃあとっかかりだけ教えてあげよう。ほら、こことここ、数字が点対称に位置してるだろう?対応する数字同士をかけたら全て同じ規則の元にある数列になる。その数列から逆算してご覧」
言われて、しばし文字盤をじいっと見つめる。ようやく他の区画の規則性も分かって、イース=イーダは眉根を寄せた。
「ちょ・・・これいきなり難しくしすぎだろ!中級だからってもう少し易しく解けるはずって悩んでた俺が馬鹿みたいじゃん!」
「いやあ、でも、易しい解法を模索することこそいいことだよ。世の中の事象はある程度からは難しい数式や定理を使わないと解読できないけれどある程度まではやっぱり極力単純な数理を使って解く訓練をしないとね。どうしても分からない時はやっぱり結局は基本に帰るものだから。あ、僕が今言った方法は一つの解法であって他にもいくつかあるからね、それも君、見つけといてね」
「はぁ?」
イース=イーダはむっとして画面をにらんだ。
「・・・いくつだよ」
「さあ?それは自分で見つけてよ。僕も思いつかなかった解法を君が思いつくとなお嬉しいな」
「無茶言うなよ」
キシュキはくすり、と笑ってまた机に向かう。しばらく沈黙が続いた。
「よし、できた。一個上がり」
イース=イーダはにっこりと笑う。あとは、出来上がった答えを見直して、ここから逆に別の解法を見つければいい・・・はずだ。それしか思いつく気がしない。
「ああ、そうだ、イース」
キシュキが手に持って読んでいた紙の束をぽん、と机に投げた。
「君に頼みがあるんだよ、もう一つ」
「なんだよ、弟の面倒ならいつも見てますけど?」
「ああうん、それはどうも。それだけど、ちょっと趣向を変えたいんだよね」
イース=イーダは顔を上げた。キシュキはこちらに背を向けたまま首筋を撫でて何事か考えている。
「は?」
「こ、れ。読んでごらーん」
キシュキは先刻まで自分が読んでいた書類をイース=イーダに放り投げた。
「は?なんだよこれ・・・ギリシェ=ラスバーンについての見解?誰だよこれ」
「まあ、読めばわかるよ」
イース=イーダは、いつになくキシュキの目が笑っていないのを見てとって、大人しく紙面に視線を戻した。
しばらく、沈黙が続く。壁に反射した青の光が移ろう中で、紙をめくる音だけが聞こえる。
「何?これ。つまりどういうこと?こんな非科学的なこと信じろって?」
「非科学性の問題で言えばそもそも、【来世でまた会いましょう】的な言い伝えも信憑性はないじゃない。だけど実際に、今までも過去の偉人の生まれ変わりはいたし、グリーグ様はこうして確かに生まれ変わってきてる。根拠はそこに書いてあるとーり。そもそもグリーグ様がバベルを封印したっていうのも実に非科学的な魔法のような話だよ。だって、バベルだよ?君も見たことくらいあるでしょ、標本。あんな魔物を次から次へと吐きだす悪魔の空間だよ?僕は魔法なんて半分しか信じてないけれど、まあ、見たことはないけれどアルヴという種族は魔法のようなものが使えるらしいしね。この世界にはまだ確認されていない生き物がたくさんいるし。ま、とにかく、色々調べて裏付けも取った結果、グリーグ様の転生は彼で間違いないわけだ。僕はまだ、彼が【暴走する】のを見たことはないけれど。ウィルドの話によると、それはアルヴやオルヴァーラといった古代種族が用いた魔導に近いものだったらしいんだよね。生憎僕らの種族は地上の種族なんてあんまり興味はなかったからきちんと調べていないもんで、標本も古文書も残っちゃいないんだけどね。まあ、ほら、僕らが電子情報を羽の繊維に取り込んだりするのも、こうした電子頭脳を使っているのも、彼らから見たらまさしく魔法らしいから、魔法の定義や概念が本当のところ何を基準にしているものなのか僕にはまだ判別付かないけれど」
「で?何が言いたいの?これを僕みたいな底辺層に見せていいのかっていう話はまあ置いておくとしてだよ、これ読んだ限りでは、アルクメネの見解ではこのギリシェ=ラスバーンっていう人間にグリーグ様の残された片翼を還元して、グリーグ様の生まれ変わりとしてバベルを閉じるために動いてもらう、ってことだよね。しかもここに書いてあるえげつないやり方で傀儡にするってことでしょ」
「まあ、そうだね。麻薬とかいろいろこっちにはあるからね。元々グリーグ様っていうのはこちら側の存在であって、人間に生まれてしまったこと自体が誤作動、って認識なわけだ。こちら側に取り込まなければいけない。なんとしても、ね」
「胸糞悪いったらないね」
「同感だねえ」
「嘘だ。お前目が笑ってる。本当はたいして同情もしてない」
「まあね」
キシュキは薄く笑った。
「ただ、僕個人の意見はこのアルクメネの議決とは違うよ。ギリシェ=ラスバーンがウィルドに生まれたことは逆に転機じゃないかなって思ってるんだよね。今まで僕らエデンは支配階級としてこの世界で空のみに生きてきたわけだけど、人口は増えているし土地はない。食べ物も正直底をついてきているよ。君なら知っているだろう?ここは中枢部だからまだましだけど、末梢区域の貧困さったらないよね、かといってお伽噺のテレサのように、このエデンの土地を増築するわけにはいかない。一応、約束だからね。これ以上の空をウィルド達から奪わないこと。となるとまだ未開拓の地の多いウィルドの世界にそう遠くない未来移住せざるを得なくなってくる可能性があるんだ。もちろん?エデンはウィルドを野蛮の族と刷り込まれているわけだから、多分そうなったときにあちこちで色々と問題が起こると思うんだよね。だったらいっそ、ギリシェ=ラスバーンを利用したらいいと思うんだ。別の意味でね。エデンとウィルドの架け橋になってもらう。一応、いくら体はウィルドとはいえ彼は恐れ多くもグリーグ様の転生、器だ。アルクメネだってないがしろにはできないだろうよ。だから僕はね、単にバベルを閉じる云々だけじゃなくて、むしろ地上の開拓の方をこそ重要視すべきかなって」
「開拓、ねえ」
イース=イーダは片膝の上で頬杖をついた。
「具体的に何をさせたいの?」
イース=イーダの言葉にキシュキはにっこりと笑う。
「そうだね、まずは恐らく、グリーグ様のお導きに従ってバベルの扉を探すことになるんだろう。バベルは少なくともこの辺にはない。世界の最果てにあると言われている。その道中で、各部落や未開の地を同時に調べてもらう。交易を出来そうなところとは手を結ぶ。つまり、ギリシェ=ラスバーンに数名同行させる方針で行きたいよね。できれば僕が信用できる人物でかつ役に立つのがいい。それと同時に僕はこっちでメティス、っていうウィルドの集団と接触を図ろうかと思うんだよね」
「メティス?何それ」
「ウィルドの暮らすクレセラ帝国帝都で台頭してきている集団だよ。地上クレアはいくつもの集落や国家があるみたいだけど、その中でも一番大きく影響力のあるのがクレセラ帝国。そこの政治は一種の貴族独裁政権のようなものらしくってね、政治で強い影響力を持っているのが、ペルセフォネ、という部落だよ。それに対抗して設立された機関がメティス、ってわけ。今のところ二大勢力みたいだね。で、メティスの敵方であるペルセフォネの長、サルウォンは、このギリシェ=ラスバーンの実父でもあるようだ」
キシュキはにやり、と笑った。イース=イーダは顔をしかめる。
「は?なんでわざわざ対抗馬と手を組むわけ?ギリシェ=ラスバーンって人がこっちの手中にあるなら普通その縁のある方につくでしょ」
「馬鹿だなあ、その書類ちゃんと読んだの?彼は重罪を背負って、地下の牢獄に投獄されてたんだよ。懲役五五六年の刑だ。実質的な無期懲役さ。それを執行したのは紛れもないペルセフォネ。しかも、その罪状はギリシェ=ラスバーンの精神疾患による【集団殺戮】とされているけれど、まあ、このあたりは間違ってはいないようだけど、どうも裏があるんだよね。彼を獄に入れて一生出さないことで何か隠蔽したかったことがあるみたいなんだ。その辺りの詳しいことはまだ調べがついていないけれど。そしてギリシェ=ラスバーンの出自や経歴を調べた感じでも、このペルセフォネには何かありそうなんだよね。僕、こういう暗部に触れるとわくわくするんだよ。暴きたくってしょうがなくなる。つまり、ペルセフォネと直接手を結ぶよりはメティスに尽力した方が僕にとっても、ひいては我らがエデンにとっても得策かなって」
キシュキはにこにこと楽しそうに微笑んでいる。
「精神疾患、ねえ・・・」
「ま、そのあたりもまだよくわかってないけどね。少なくとも僕が少し話した感じでは頭ははっきりとしていたし、特に狂った子と言うわけでもなさそうだったよ」
「で?そんな話を僕にして、何をさせたいわけ?」
イース=イーダは手に持っていた電子頭脳の電源を切った。とてもじゃないが呑気に遊んでいる気分ではなくなった。気分がひどく重い。
「もちろん、僕に協力してくれるでしょ?」
キシュキはにっこりと笑った。目は笑っていない。
こいつは怖い。時々体の芯からそう感じることがある。今もそうだった。
イース=イーダは断ることもできる。振り払うことはできる。もしここで否、と言ったとしても、きっとキシュキは表立って何かをしてきたりはしないだろう。けれど怖くてならなかった。きっと彼はこういうだろう。『そう。それじゃあ僕はもう君達家族のことには関与しないことにするよ』
たとえキシュキが関わらないからと言って、すぐにイース=イーダの家族―両親や、幼い弟妹達、体の弱い姉が、すぐにどうこうなるというわけではない。それでも、ぞっとするのだ。キシュキはきっと何もしない。それなのに、【キシュキが家族の身柄を保証しなくなる】、たったそれだけで、この世の全てから見放された、悪食共の格好の餌食と一瞬でなってしまったような恐怖を感じる。こんなに怖いことはない。きっと、今ここで舌を噛み切って死ねと言われた方が何倍も心穏やかにいられる。なぜかは分からない。それでも、キシュキ=レシラの存在はそれだけの恐怖をイース=イーダに湧き起こさせる。
イース=イーダは目を反らした。キシュキはそれを肯定の合図として受け取ったようだった。
「簡単なことだよ。君がアルクメネを裏切るだけでいい。この天空、テレサの掟に一生そむく覚悟はできる?それでも僕は君の味方だよ。絶対に裏切ったりしない。裏切らないよ。君に悪いようにはしない。君の家族も絶対に守ろう。誓うよ」
キシュキはにっこりと笑った。きっと彼は約束を絶対に違えないだろう。約束にだけは誠実な男だ。その代わり、条件を満たさないものには容赦がない。容赦なく興味を無くす。
アルクメネの最年少の男、稀代の天才。
この男から興味を持たれなくなるということは、死よりも恐ろしい。なぜかは分からない。それなのに、イース=イーダは肌でそれを学んでいた。それを知っていてなお彼の傍に、彼の弟の傍にいるのだ。自分でもなぜかは分からないのだ。
恐らくそれが、権力と言うものなのだと思う。
キシュキ=レシラの指に絡まるいくつもの金の糸が、イース=イーダには見える。
その糸を切られたらもう終わりだ。イース=イーダに繋がるその糸は蜘蛛の糸のようにとても細く頼りないのだ。篩い落とされるわけにはいかない。
イース=イーダは口を小さく開いた。躊躇いもあったが、消した。
いいよ、何をしたらいいの?
唇が動く。キシュキ=レシラは柔らかく笑った。
キシュキ=レシラの部屋は、青を基調としている。
これでもかというくらいに全てを青で統一している。唯一青でないとすれば、白い天井と、白木でできた机、寝台くらいのものだった。それだって青の模様がひしめき合っている。
【研究】や【気晴らし】といった名目、私用で使う全ての部屋をただ一色で揃えるのは彼の趣味だった。違う色が混じっていると気持ちが悪いのだそうだ。気になって集中ができない、という。何かひらめくとその場で計算に没頭してしまう彼の行動傾向と照らし合わせれば、まあ納得ができないこともない。
それでも正直悪趣味だと思う。ここまでくるといっそすがすがしい気持ちの悪さだ。客間に使う部屋は色がいくつかあるだけでまだましだが、それでも悪趣味なことに変わりはない。もう少し質素にしてもいいのではないかと思う。ごてごてしすぎている。それはもう、目に痛いくらいに。
おかげでこの屋敷に働く者で長続きした者はそうそういないし、弟子入りを志願してきた【鳥】達もたった一人の例外を除いて全て泡食って逃げ出した。特にかわいそうだったのが、真っ白な部屋をあてがわれた子だ。数日のうちに気が狂ったように泣き叫び、這うように出て行った。あの部屋は、少年も苦手だ。何の拷問かと思う。なのにキシュキ=レシラがやけに気にいっているから余計に性質が悪い。
少年―イース=イーダに言わせれば、キシュキ=レシラはほぼきちがいだった。
弟は弟で性格が捻くれている。ろくな兄弟ではない。なぜ自分が未だにこの二人と関わりを持っているのか自分で不思議だ。感心する。我がことながら。
そもそも自分から好んできたわけではない。ただ、ここに居続ける面倒よりもここから出てまた奉公先を探すことの方が手間のように思えたのでそのままにしているだけだ。弟の方は別としても正直兄の方にはこれっぽっちも思い入れはない。
とはいえ、学のなかった自分に一から教えてくれたのもキシュキ=レシラだった。頼んだわけでもなかったが迷惑だったわけでもない。
今日もまた、キシュキ=レシラは何やら楽しそうに計算をしている。キシュキ自身が勝手に改造した電子頭脳の画面が、青と黄色の光をちかちかと点滅させている。同じ部屋でイース=イーダもまた、床に座り込んで小型の携帯式電子頭脳の画面に電子筆を走らせていた。キシュキが何をしているのはさして興味がないが、イース=イーダがやっているのは中級程度の数字遊戯盤だ。81個のマスがあって、ところどころに数字が不規則に並んでいる。縦と横、そして9マス単位の区画それぞれに当てはまる数字には規則性がある。空欄のマスに適した数字を入れなければならないのだが、さすがに中級編は難しかった。しかもこれを作っているのがキシュキを筆頭としたアルクメネの集団だから、なおのことなんだか憎々しい。
しかもキシュキは鼻歌まで歌いだした。やっぱりうっとうしい。
初級編で掴みかけたと思ったこつが、中級編ともなるとほぼ役に立たなかった。イース=イーダはため息をつく。
「どう?諦めた?」
キシュキが椅子をくるりと回旋させ、腹立たしいくらいに満面の笑みを浮かべる。
「これほんとに俺解けるのかよ。知らない定理とかほんとは使われてんじゃないの?」
「いやいや、君の知ってる知識をこねくり回せば解ける問題だよ。もちろんまあ、もう一つ上の段階の知識を持っていれば簡単ではあるんだけどね。でもそんなの意味ないし、面白くないでしょ」
「解けない時点で面白くもなんともないんだけど」
「解けたらきっとすっきりするよ」
「だからさぁ、いきなりこんな応用問題出されても解き方分かんないっての。初級は公式当てはめりゃ解けたのになんだよこの問題。鬼畜だろ」
「公式丸暗記なんて面白くもなんともないじゃない。それにね、イース、僕達がやってる研究なんかもっと人生悲観したくなるくらい複雑な応用の迷路なんだらからね?」
「誰もそんなとこまで望んでないから」
イース=イーダは嘆息した。キシュキは肩をすくめる。
「君はいい素質持ってるから、ここで終わらせたくないんだよねえ。だからこうして君に手とり足とり教えてるんじゃないか」
「自分の弟にしとけよ、ったく」
「まあねえ。シアはさすが僕の弟で馬鹿ではないんだけど、やっぱり僕の方がどうしたって上なんだよねえ」
「ろくな教育もしてないくせによく言うよ。赤の他人にはこうして教育するくせに」
「あの子の役割はそういう方面じゃないからね。適材適所、って言うでしょ」
そういう考え方は、理にはかなっているのかもしれないとは思う。けれど、イース=イーダは好きではなかった。シンシア=レシラが、何も与えてもらえず何を望むことも許されないまま、世に緩く失望し惰性で生きているのを知っている。彼の心を揺さぶるものがこの世界には何もない。何も与えてもらえない。
「仕方ないね、じゃあとっかかりだけ教えてあげよう。ほら、こことここ、数字が点対称に位置してるだろう?対応する数字同士をかけたら全て同じ規則の元にある数列になる。その数列から逆算してご覧」
言われて、しばし文字盤をじいっと見つめる。ようやく他の区画の規則性も分かって、イース=イーダは眉根を寄せた。
「ちょ・・・これいきなり難しくしすぎだろ!中級だからってもう少し易しく解けるはずって悩んでた俺が馬鹿みたいじゃん!」
「いやあ、でも、易しい解法を模索することこそいいことだよ。世の中の事象はある程度からは難しい数式や定理を使わないと解読できないけれどある程度まではやっぱり極力単純な数理を使って解く訓練をしないとね。どうしても分からない時はやっぱり結局は基本に帰るものだから。あ、僕が今言った方法は一つの解法であって他にもいくつかあるからね、それも君、見つけといてね」
「はぁ?」
イース=イーダはむっとして画面をにらんだ。
「・・・いくつだよ」
「さあ?それは自分で見つけてよ。僕も思いつかなかった解法を君が思いつくとなお嬉しいな」
「無茶言うなよ」
キシュキはくすり、と笑ってまた机に向かう。しばらく沈黙が続いた。
「よし、できた。一個上がり」
イース=イーダはにっこりと笑う。あとは、出来上がった答えを見直して、ここから逆に別の解法を見つければいい・・・はずだ。それしか思いつく気がしない。
「ああ、そうだ、イース」
キシュキが手に持って読んでいた紙の束をぽん、と机に投げた。
「君に頼みがあるんだよ、もう一つ」
「なんだよ、弟の面倒ならいつも見てますけど?」
「ああうん、それはどうも。それだけど、ちょっと趣向を変えたいんだよね」
イース=イーダは顔を上げた。キシュキはこちらに背を向けたまま首筋を撫でて何事か考えている。
「は?」
「こ、れ。読んでごらーん」
キシュキは先刻まで自分が読んでいた書類をイース=イーダに放り投げた。
「は?なんだよこれ・・・ギリシェ=ラスバーンについての見解?誰だよこれ」
「まあ、読めばわかるよ」
イース=イーダは、いつになくキシュキの目が笑っていないのを見てとって、大人しく紙面に視線を戻した。
しばらく、沈黙が続く。壁に反射した青の光が移ろう中で、紙をめくる音だけが聞こえる。
「何?これ。つまりどういうこと?こんな非科学的なこと信じろって?」
「非科学性の問題で言えばそもそも、【来世でまた会いましょう】的な言い伝えも信憑性はないじゃない。だけど実際に、今までも過去の偉人の生まれ変わりはいたし、グリーグ様はこうして確かに生まれ変わってきてる。根拠はそこに書いてあるとーり。そもそもグリーグ様がバベルを封印したっていうのも実に非科学的な魔法のような話だよ。だって、バベルだよ?君も見たことくらいあるでしょ、標本。あんな魔物を次から次へと吐きだす悪魔の空間だよ?僕は魔法なんて半分しか信じてないけれど、まあ、見たことはないけれどアルヴという種族は魔法のようなものが使えるらしいしね。この世界にはまだ確認されていない生き物がたくさんいるし。ま、とにかく、色々調べて裏付けも取った結果、グリーグ様の転生は彼で間違いないわけだ。僕はまだ、彼が【暴走する】のを見たことはないけれど。ウィルドの話によると、それはアルヴやオルヴァーラといった古代種族が用いた魔導に近いものだったらしいんだよね。生憎僕らの種族は地上の種族なんてあんまり興味はなかったからきちんと調べていないもんで、標本も古文書も残っちゃいないんだけどね。まあ、ほら、僕らが電子情報を羽の繊維に取り込んだりするのも、こうした電子頭脳を使っているのも、彼らから見たらまさしく魔法らしいから、魔法の定義や概念が本当のところ何を基準にしているものなのか僕にはまだ判別付かないけれど」
「で?何が言いたいの?これを僕みたいな底辺層に見せていいのかっていう話はまあ置いておくとしてだよ、これ読んだ限りでは、アルクメネの見解ではこのギリシェ=ラスバーンっていう人間にグリーグ様の残された片翼を還元して、グリーグ様の生まれ変わりとしてバベルを閉じるために動いてもらう、ってことだよね。しかもここに書いてあるえげつないやり方で傀儡にするってことでしょ」
「まあ、そうだね。麻薬とかいろいろこっちにはあるからね。元々グリーグ様っていうのはこちら側の存在であって、人間に生まれてしまったこと自体が誤作動、って認識なわけだ。こちら側に取り込まなければいけない。なんとしても、ね」
「胸糞悪いったらないね」
「同感だねえ」
「嘘だ。お前目が笑ってる。本当はたいして同情もしてない」
「まあね」
キシュキは薄く笑った。
「ただ、僕個人の意見はこのアルクメネの議決とは違うよ。ギリシェ=ラスバーンがウィルドに生まれたことは逆に転機じゃないかなって思ってるんだよね。今まで僕らエデンは支配階級としてこの世界で空のみに生きてきたわけだけど、人口は増えているし土地はない。食べ物も正直底をついてきているよ。君なら知っているだろう?ここは中枢部だからまだましだけど、末梢区域の貧困さったらないよね、かといってお伽噺のテレサのように、このエデンの土地を増築するわけにはいかない。一応、約束だからね。これ以上の空をウィルド達から奪わないこと。となるとまだ未開拓の地の多いウィルドの世界にそう遠くない未来移住せざるを得なくなってくる可能性があるんだ。もちろん?エデンはウィルドを野蛮の族と刷り込まれているわけだから、多分そうなったときにあちこちで色々と問題が起こると思うんだよね。だったらいっそ、ギリシェ=ラスバーンを利用したらいいと思うんだ。別の意味でね。エデンとウィルドの架け橋になってもらう。一応、いくら体はウィルドとはいえ彼は恐れ多くもグリーグ様の転生、器だ。アルクメネだってないがしろにはできないだろうよ。だから僕はね、単にバベルを閉じる云々だけじゃなくて、むしろ地上の開拓の方をこそ重要視すべきかなって」
「開拓、ねえ」
イース=イーダは片膝の上で頬杖をついた。
「具体的に何をさせたいの?」
イース=イーダの言葉にキシュキはにっこりと笑う。
「そうだね、まずは恐らく、グリーグ様のお導きに従ってバベルの扉を探すことになるんだろう。バベルは少なくともこの辺にはない。世界の最果てにあると言われている。その道中で、各部落や未開の地を同時に調べてもらう。交易を出来そうなところとは手を結ぶ。つまり、ギリシェ=ラスバーンに数名同行させる方針で行きたいよね。できれば僕が信用できる人物でかつ役に立つのがいい。それと同時に僕はこっちでメティス、っていうウィルドの集団と接触を図ろうかと思うんだよね」
「メティス?何それ」
「ウィルドの暮らすクレセラ帝国帝都で台頭してきている集団だよ。地上クレアはいくつもの集落や国家があるみたいだけど、その中でも一番大きく影響力のあるのがクレセラ帝国。そこの政治は一種の貴族独裁政権のようなものらしくってね、政治で強い影響力を持っているのが、ペルセフォネ、という部落だよ。それに対抗して設立された機関がメティス、ってわけ。今のところ二大勢力みたいだね。で、メティスの敵方であるペルセフォネの長、サルウォンは、このギリシェ=ラスバーンの実父でもあるようだ」
キシュキはにやり、と笑った。イース=イーダは顔をしかめる。
「は?なんでわざわざ対抗馬と手を組むわけ?ギリシェ=ラスバーンって人がこっちの手中にあるなら普通その縁のある方につくでしょ」
「馬鹿だなあ、その書類ちゃんと読んだの?彼は重罪を背負って、地下の牢獄に投獄されてたんだよ。懲役五五六年の刑だ。実質的な無期懲役さ。それを執行したのは紛れもないペルセフォネ。しかも、その罪状はギリシェ=ラスバーンの精神疾患による【集団殺戮】とされているけれど、まあ、このあたりは間違ってはいないようだけど、どうも裏があるんだよね。彼を獄に入れて一生出さないことで何か隠蔽したかったことがあるみたいなんだ。その辺りの詳しいことはまだ調べがついていないけれど。そしてギリシェ=ラスバーンの出自や経歴を調べた感じでも、このペルセフォネには何かありそうなんだよね。僕、こういう暗部に触れるとわくわくするんだよ。暴きたくってしょうがなくなる。つまり、ペルセフォネと直接手を結ぶよりはメティスに尽力した方が僕にとっても、ひいては我らがエデンにとっても得策かなって」
キシュキはにこにこと楽しそうに微笑んでいる。
「精神疾患、ねえ・・・」
「ま、そのあたりもまだよくわかってないけどね。少なくとも僕が少し話した感じでは頭ははっきりとしていたし、特に狂った子と言うわけでもなさそうだったよ」
「で?そんな話を僕にして、何をさせたいわけ?」
イース=イーダは手に持っていた電子頭脳の電源を切った。とてもじゃないが呑気に遊んでいる気分ではなくなった。気分がひどく重い。
「もちろん、僕に協力してくれるでしょ?」
キシュキはにっこりと笑った。目は笑っていない。
こいつは怖い。時々体の芯からそう感じることがある。今もそうだった。
イース=イーダは断ることもできる。振り払うことはできる。もしここで否、と言ったとしても、きっとキシュキは表立って何かをしてきたりはしないだろう。けれど怖くてならなかった。きっと彼はこういうだろう。『そう。それじゃあ僕はもう君達家族のことには関与しないことにするよ』
たとえキシュキが関わらないからと言って、すぐにイース=イーダの家族―両親や、幼い弟妹達、体の弱い姉が、すぐにどうこうなるというわけではない。それでも、ぞっとするのだ。キシュキはきっと何もしない。それなのに、【キシュキが家族の身柄を保証しなくなる】、たったそれだけで、この世の全てから見放された、悪食共の格好の餌食と一瞬でなってしまったような恐怖を感じる。こんなに怖いことはない。きっと、今ここで舌を噛み切って死ねと言われた方が何倍も心穏やかにいられる。なぜかは分からない。それでも、キシュキ=レシラの存在はそれだけの恐怖をイース=イーダに湧き起こさせる。
イース=イーダは目を反らした。キシュキはそれを肯定の合図として受け取ったようだった。
「簡単なことだよ。君がアルクメネを裏切るだけでいい。この天空、テレサの掟に一生そむく覚悟はできる?それでも僕は君の味方だよ。絶対に裏切ったりしない。裏切らないよ。君に悪いようにはしない。君の家族も絶対に守ろう。誓うよ」
キシュキはにっこりと笑った。きっと彼は約束を絶対に違えないだろう。約束にだけは誠実な男だ。その代わり、条件を満たさないものには容赦がない。容赦なく興味を無くす。
アルクメネの最年少の男、稀代の天才。
この男から興味を持たれなくなるということは、死よりも恐ろしい。なぜかは分からない。それなのに、イース=イーダは肌でそれを学んでいた。それを知っていてなお彼の傍に、彼の弟の傍にいるのだ。自分でもなぜかは分からないのだ。
恐らくそれが、権力と言うものなのだと思う。
キシュキ=レシラの指に絡まるいくつもの金の糸が、イース=イーダには見える。
その糸を切られたらもう終わりだ。イース=イーダに繋がるその糸は蜘蛛の糸のようにとても細く頼りないのだ。篩い落とされるわけにはいかない。
イース=イーダは口を小さく開いた。躊躇いもあったが、消した。
いいよ、何をしたらいいの?
唇が動く。キシュキ=レシラは柔らかく笑った。
カレンダー
| 06 | 2025/07 | 08 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
リンク
カテゴリー
フリーエリア
最新CM
最新記事
(12/01)
(11/28)
(09/21)
(08/10)
(08/10)
(08/10)
(08/09)
(08/09)
(07/14)
最新TB
プロフィール
バーコード
RSS
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事
(07/14)
(08/09)
(08/09)
(08/10)
(08/10)
(08/10)
(09/21)
(11/28)
(12/01)
P R