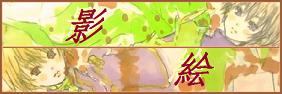□
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
二、
非常に不快だった。
まず、温い。そしてちりちりと耳障りな音がする。
言うなれば腹から嚥下したとき口まで上ってくる胃液の中に体をびしょ濡れにされたような感覚だった。目を見開くこともできなかったけれど閉じ切ることもなんだかできず、そうしているうちに角膜の上を金色と灰色の針金のような光の点線がひどく忙しなく縦に横に斜めに螺旋を描いて動いた。それを見ていただけで気分が悪くなった。そして何より音だ。脳髄にまでじんじんと響いてくるから、耳を塞いだところでほぼ意味はない。ちり、ぎり、がり、とまるで金属で金属を削るようなキーキーとした音がとぎれとぎれにのろのろと鳴った。それらがすべて自分達を包み込んだ。世界は水色と黄色。ところどころ意味のわからない赤橙と橙の色をした球体のような円盤のような半透明のものがぴょんぴょん飛んで行った。
そう長い時間ではなかったのかもしれないけれど、十分にギリシェにとっては疲労の材料になった。
空間が巻貝のようにぐるぐると絞り上げられ、先端の方へ二人は吸いこまれていく。痛くはなかった。自分の周りにねっとりと纏わりついていた温い液体のようなものが体からしぼりとられていくようで、ようやくすう、と息ができたような心地がした。ギリシェは大きくため息をついた。ため息がこんなにも気持ちの良いものだとはついぞ知らなんだ。これからは大いに息を吐くとしよう。
「着いたよー。あはは、相変わらず気色悪かった!」
薄青の髪の少年は妙にすっきりした顔もちで言った。ギリシェは一瞬何を言われたのかわからなくて、止まる。
自分もあまり気持ちよくないなら何故にこの移動手段を使うのかと問いたくないこともなかった。ぐっとこらえる。面倒な会話で時間が浪費されるのは疲れるから嫌いだ。
まずは状況を判断しよう、とギリシェは辺りを見渡した。黙ってそうするのは一種の癖だ。人にいちいち分からないことを聞くのはあまり好きではなかった。わずらわしいからだ。自分の目で見て知ることができることは、意外と多いものだ。もしよくわからなくてもそれは今の自分にはきっと必要がないから分からないのだ。それがギリシェの信条のようなものだった。分からないものは目に焼き付けておけばいい。いつかそれが必要になった時に、それが何だったのかきっと分かるだろう。そう思っている。
一面は緑の森だ。青緑の瑞々しく肉厚な葉の茂った木が地面中に根を張っている。普通の木と違うところ言えば、根にもまた葉がまるで蔦や蔓草の類のように茂っているということだろうか。おかげで地上で見られる草のようなものはないけれど、十分に地面も緑に覆われている。
そして不自然に、ぽっかりと空いた、いや、空けられた空間がある。作為的にも見えるよく伸びた三つの木の枝が絡み合って網をつくり、屋根になっている。その下でその格子の影を映しているのはやや茶色がかった黄色の四角錐の大きな物体だった。その全ての辺と中線もまた、先刻奇妙な空間で見たものとよく似た、赤みのある金色の点線状の光の通路になっている。そしてその四角錐の周りの地面に、ぽつぽつと長方形の白金の薄板が刺さっている。まるで規則性がない並びのように見えて目を細めたら、実はそれらの板は四角錐の建物を中心に据えた見えない正方形の辺上にきちんと立っているのだとわかった。それがわかって改めて眺めると、不整合に見えたそれらの構造が実は綿密な計算のもとに配置されているのだと分かる。地上ではまず見ない様式美だ。少なくとも地上の人間達は均等を好む。対称なものを美しいと直感的に感じる。今目の前にある建築物は、全体としてみれば点対称ですらない。
そして、妙に静かだった。風ひとつ吹いていないのだ。空気はあるはずなのに、居心地が悪くなるような静けさだ。身動きをして音を立ててはいけないかのような心地になる。
意味が分からなかった。結局分かるのは、地上とこの羽のある生物たちの暮らす環境は似ているようで実は全然違うのであろうということ、そして美しいようでどこか怖いものなのだと肌で感じ取れるだけ。
「ここはピルミラ。グリーグ様の社だよ」
少年が、それをじっと見つめながらささやく。
だからグリーグって誰だよ、と思う。鳥達の常識を自分のようなただの人間も当然のように持っているように思わないでほしい。父親なら知っていたかもしれないな、と頭の中で言葉がかすっていって、ギリシェはかぶりを振った。どうでもいいことだ。自分は知らない。それが事実だ。あと、耳元で話すのやめてほしい。
「グリーグ様はもう亡くなってるから、今は誰も住んでないんだけど、ただ、多分ここは保管庫なんだと思う。上の人たちは、文化的遺産であるグリーグ様の住まいの永久的保護のために立ち入り禁止、だなんて言ってるけど、現にあの人たち結構ここにちょこちょこ達言ってるみたいだし、それは多分詭弁だよね。多分、【あれ】を保護してるんだ、ここで。腐らないように」
―【あれ】、ねえ。
だからなんだよ、と思ったりしなくもない。そんなことを自分に話したところでさっぱり意味が分からないのだから非常に不毛だ。無駄だ。
溜息でもつこうかな、と思ったがやめておくことにした。わざわざ人前でするものでもない。あとあと面倒だ。自分はなるべく透明に生きていきたいのだ。
まあ、もう少し人並みに生きていてもいいなら、の話だが。
「多分、【それ】をここから出しちゃいけないのと、僕が外を歩いちゃいけない理由はつながっているんだと思うんだけど、いかんせん兄さんに聞くわけにもいかないから、ばれちゃうから、僕には未だに痒いところに手が届かない気持ちってこういうことなのかなって」
先刻から筋の通らない言葉遣いなやつだな、とギリシェは思った。そうしてふと、なんでこいつら、羽があるのに歩くんだろう、と思ったりした。そういえばキシュキと名乗った青年も女中も羽があるくせに床をぺたぺたと歩いていたように記憶している。
ふと、少年は不思議そうにギリシェの顔を覗き込んだ。いちいち距離が近い。まあだからと言ってひるむわけでもないのだが。少々のことでは動じない癖がついてしまっている。
「君、変な子」
「は?」
つい相手をしてしまった。
「だって、さっきからずっと取り乱すこともなくだんまりなんだもん。臆してるわけじゃないんだよね?人ってみんなそうなの?」
「さあ」
「さあって」
「僕に人類一般の傾向を語れと言われてもな。言うほど経験積んでないもん」
「そうなの?」
ふーん、と少年は一人で納得したようだった。そうして唐突ににっこりと嬉しそうな笑顔を浮かべる。
何、と思ったりする。
「えへへ、でもなんだか楽だな!僕が一人でしゃべってても変な空気にならないしね!やっぱり相手がいるっていいことだよね。一人きりの時ぶつぶつ独り言言っててたまに無性に恥ずかしくなる時あるんだよね」
そこまできちんと耳を傾けてもいないんだけど、と心の中でだけ応対して、ギリシェはそのまま四角錐の方へ視線を戻した。
なんだろう。最初の衝撃が薄れると、だんだん愛着がわいてくるというか、この形がどこか可愛いものに思えてくる。何の変哲もない図形の塊なのに、奇妙な感覚なことだ。
上手い言葉が見つからないけれど、少なくとも警戒心があおられたりはしない。この場所にいると、神経を張り詰めようとする気が削がれていく。
「あのね、ちょっとついてきてよ」
少年はさらりと言うと、そのままピルミラの方へ近づいていく。その足取りを見ながら、やっぱり人よりも足取りに重さがないんだな、とギリシェは少しだけ思う。
着いていかない理由もないけれどついていかなければならない理屈もないんだけどな、などと思いながらギリシェは大人しくその後ろを着いて行った。
「ほら、こっち。ここまで寄ってみて」
少年は手招きする。ピルミラの壁にぴったりと鼻と手を寄せて中を食い入るように見る。
ギリシェも、さすがにそこまではしなかったが少年の肩の後ろから覗いてみた。
離れた所からは分からなかったが、ピルミラの壁は透明で、中が見えるようになっていた。点線の光がちらちらとせわしなく動いて交錯するので鬱陶しかったりする。
けれど、その光達が載る物、内部の中央に浮かんでいるそれは、綺麗だと思った。
片翼だ。
はっきりとした色は壁の色に透かされてよくわからないけれど、光沢や影の度合いでかなりいろんな色の混じった翼なのだろうとは分かった。朱子織のようになめらかで柔らかそうだ。こうして見るだけでも、収集品に興味のないギリシェでさえ惹きつけられるものがある。魅入るとでも言うのだろうか。
「あれ?」
ギリシェはふと呟いた。よく考えてみれば、その翼はキシュキ達のような翼とは全く違うものだ。どちらかと言えば―美しさは劣るにしても―目の前にいるこの線の細い少年の翼に近い。
「鳥の翼ってやつは、いろんな種類があるんだな」
ギリシェは多分、少年に対しては初めて自分から声をかけてみる。
少年は目を丸くして振り返る。しばらくじっとギリシェの目を見つめた後、なぜか顔を赤らめてうつむいた。何故そこではにかむ必要があるのかギリシェにはよく分からない。奇妙奇天烈とはこのことだな、と呑気にそんなことを考える。
「僕のは・・・ううん、違うんだ、僕のは、ちょっと、特別なんだ。特別っていうか、奇形と言った方が正しいんじゃないかな・・・あ、グリーグ様の翼が奇形だなんて言ってないよ!?だってグリーグ様はあの翼でちゃんと飛べた。僕は飛べない。あんなに美しくもない。だから僕は多分奇形だ」
少年はぼそぼそと言う。どこか覇気がなかった。
まあ絶対に気にかけなければいけないことでもないはずなので、とりあえずギリシェは頭の中で少年の発言を整理する。
察するに、このピルミラの中にある翼はグリーグという奴の翼と言うことだろうか。そして、様と呼ばれるからにはなかなか立場の偉い人物なのだろう。そういえばもう死んだとか言っていたような気がする。つまり翼を片方だけぶった切ってここに押し込んでいるということか。見た目は綺麗だが意外と鳥達も残酷な―いや、思い切ったことをするもんなんだな、と少しだけ思う。少なくとも自分の知っている限りでは、地上の人間は敬意を表している相手の体を切断したりはしないはずだ。
ギリシェは少年の髪色と同じ柔らかで薄い翼をじっと眺めた。奇形、ねえ。
たしかにまるで女の服みたいな布が申し訳程度についているくらいのようなものだから、あってもなくてもよさそうだとも思う。けれど同時に純粋に綺麗だとも思った。もしも少年の背からこのなめらかな布のような翼がなくなってしまったら、なんだか心もとない感じだ。この翼があるから少年は鳥なのだ。人のような何の変哲もない生き物ではない。美しいものなのだ。大鷲のような翼も似合っただろうとは思うけれど、この翼は個人的に嫌いではない。
何か言った方がいいかと思って言葉を探す。けれど、変に慰めていると受け取られたくはない。単に思ったことを言いたくなっただけなのだから。
結局、何を言っても嘘くさくなりそうで、ギリシェは黙って少年の頭を撫でた。翼に触れようかとも思ったが、知覚はあるはずだ。下手に触って痛かったらよくない。
少年は戸惑ったように身をすくめていたが、やがて肩の力を抜いた。まるで野良猫を懐かせたような気分になる。
「ほんとはね、」
少年はグリーグの翼であろうものに視線を戻して静かに続けた。
「僕は自分のこの羽に、劣等感を、みじめさを感じてもいるし、ちょっと酔ってもいるんだ。
「僕のこの翼だけが、グリーグ様のものとそっくりで、他の【鳥】たちはみんなただの鳥と同じものしか持っていない。僕が自分を卑下するのもただの申し訳で、本当は心の奥底で、自己満足してるよ。だって僕の翼はグリーグ様と同じなんだ。みんなよりもずっと綺麗だし希少価値があって。だけどこんな風におごっている自分が気持ちよくもあるけど嫌いでもあるんだ。だから僕は人前では自分を卑下しないではいられないし、自分を奇形だって言わずにはいられない。自分で言って自分で傷ついて、一人になった時に自分に言い訳するんだ。だけど僕は綺麗な子だからいいんだって。慰めるみたいにさ。だけど僕は・・・綺麗なものになりたいんじゃなくて、かっこよくなりたいんだ。女みたいに儚いって言われても全然嬉しくなかったよ。僕は男らしくなりたいだけなんだけどな。骨太っていうかさ。兄さんは趣味がちょっとおかしいからなぁ。線が細けりゃいいって思ってる」
少年は、小さく嘆息した。中腰になっていた体を起こす。
「うん、満足した。聞いてくれてありがとう」
ギリシェは少しだけ顔をしかめた。礼を言われるのはなんだか居心地が悪い。言われ慣れていないのだ。なんだか腹立つし、妙な気持ちになる。
ギリシェは自分が捻くれているのは重々承知している。だから謝られるのと同じくらい礼を言われるのはあまり好きじゃない、つまりそういうことだ。どちらの行為も単なる本人の自己完結の手段にしか感じられないからだ。けれど、今は、この少年に素直に自己完結させてやってもいいかな、と思った。彼はこう言うことできっと、ゆらぐ細い自分を支えるのだろう。いつものギリシェなら、礼を言われるのは好かない、くらいはつい言ってしまうけれど。
「あれね、」
少年はグリーグの翼を指差す。
「片方しかないでしょ?もう片方はね、転生に使ったらしいんだよね」
「転生?」
「生まれ変わる、ってこと。僕達の魂は、君達もきっとそうだと思うけれど、この体の成分すべてが一つの魂を構成しているんだ。魂は光から生まれて光に還る。ほら、あの太陽」
少年は梢から微かに見える、世界の昼を照らす丸い光を指差した。
「【人々】の死生観がどうなってるのかはよく知らないけどさ、この世で生きていると、魂は汚れも吸っていくんだ。だから老いて行くし、いつかは摩耗して死んでしまう。だけど生まれ変わって、もう一度同じ存在になることはできる。死ぬ時は体のすべてを太陽にお返しするんだよ。あそこでもう一度綺麗に体を掃除してもらって、もう一回生まれてくる。だけど、体の何かを失ったままだったり、逆に要らないものを持っていってしまうと少しずつ違うものが魂に混じっていくんだ。生まれ変わった時、前とは違う魂になってしまってる。別人になるんだ。だから僕達鳥は、体の全てを必ず太陽に還す。火葬する人々がかわいそうだな、ってときどき思うよ。君達は必ず魂を構成する何かを無くしたまま生まれ変わっていくから、きっといつかは魂もなくなっちゃって、何者にもなれなくなるんだろうね。世界から消えてしまうんだろう。
「まあ、それはいいとして、とにかく、普通は両翼含めて体全部使って生まれ変わるのに、なぜかグリーグ様はああして羽を片方だけ残していったんだ。理由は僕にはよくわからないんだけど・・・なんでなんだろう。だけどこうして鮮度を保つようにこの中に閉じ込めているってことはね、きっとまた何かに使うつもりなんだ。多分・・・生まれ変わってきた子に役立てるんだと思う」
少年は口元に手を置いて何事か考え込む。
「ただこの辺は機密事項らしくて外部には漏らされてないし、僕もこれを見て初めてその可能性を思いついただけだから、全然分かんないんだけど」
なんでそういう重要なことをよそ者の僕に話してんの?という突っ込みはしないほうがいいんだろうな、とギリシェは心の中でだけ思う。そもそも、ここに自分を連れてきている時点で非常におかしい。見れて悪かったとは思わないけれど、どうしてこの少年は自分にこれを見せたのだろうかと思わずにはいられない。
とはいえ、見せられて見てしまったもの、聞いてしまったものはもうどうしようもないのだから、ギリシェはそれ以上は深く追求しないでおくことにした。ギリシェが黙っていると、少年は困ったように微笑んだ。
「ほんと、変な子だね、何で僕が君にこれを見せたかって聞かないの?」
―ああ、これは聞かなきゃいけなかったわけ。
人との対話は加減が難しいな、と思いながら心の中でだけ嘆息した。
「見てしまったものをなかったことに出来るわけじゃないだろ」
思ったままを答えると、少年は吹き出した。
「まあ、そう、だけどさ!」
くすくすと笑いをこらえている。
「なんだかものすごく君面白いね。おおらかだね!なんだか新鮮」
「いや、多分僕が普通より変わってるだけだから」
自分が人間一般に対して思いやる必要はないのだけれど、一応申し訳程度に言い訳をしておく。少なくともギリシェ自身は自分が一般的な感覚を持てていないことくらいは認識できている。
「鳥にもいないよ、君みたいなの」
少年はにっこり笑った。
「あ、そうだ、名前聞いてなかったや。なんて言うの?僕はシンシア。さっき君に気色悪く迫ってたキシュキってやつの弟なんだ」
「似てないな、顔が」
「顔以外は似てるって言いたいの?心外なんだけどちょっと」
シンシアは少し口をとがらせる。男らしくなりたいと言った傍からその仕草はどうなのだろうと少し思ったりする。
「兄さんには気をつけてね。あの人自分の研究しか頭にないから、目をつけられてる君は相当執着されるはずだよ、なんの目的かは知らないけどさ」
シンシアはあさっての方向を見たまま言った。
「僕はギリシェ。見ての通り人」
シンシアはまた吹き出した。
とりあえず放っておいて、改めてギリシェは自分の周りの世界を見渡してみた。
瞼を閉じても、その裏側に陽の光を透かして緑の色が映り揺れる。緑は嫌いじゃなかった。自分が溶け込める気がする。誰にも見つかることもなく、誰にも邪魔されることなく。
ただ静かに暮らしたいだけだ。それだけだ。誰と関わりたいわけでもない。
とはいえ、シンシアとの最初は不毛に思えた会話も、意外と楽しかったかなと思ったりした。
「人間は火葬したり土葬したり水葬したり、いろいろするけど」
ギリシェはふと、これだけは言っておこうと思って口を開く。
「僕の生まれた地方では土葬だったから他のことはよくは知らないけどさ、多分目的は一緒だと思う。土葬することで、体が土に還る、って考え方。大地の一部になるんだ。自然の一部になって、循環して、命が廻る。そういう考え方をしてる。だから多分、根本的に死生観はやっぱり違うんだと思う」
シンシアは戸惑ったように眉をひそめた。
「何それ。自然になって満足してるの?それって自己満足じゃない?元々あった自然の、土や木や風たちのありようをそうすることで少しずつ変えていってるってことでしょう?いつか摩耗しちゃうよ。人ったらなんてもったいないことをするんだろ」
「そもそもたしか、自然っていう大きな塊の一部が人間になったって考え方じゃなかったっけな」
ギリシェは記憶を頼りに呟く。聖書の暗記をさせられたのなんて物心がつくかつかないかのことだから、うろ覚えだ。
「だから、多分それで摩耗したりはしない。むしろ世界のあるがままに直してるつもりだと思う。人は全体的に捉えてるんだろ。で、あんた達は個を捉えてるってこと。僕から言わせれば結局どっちも自己本位で自己満足な結論のように思うけど」
「なぜ?」
シンシアが不安そうに小さな声で問う。
ギリシェは答えなかった。特に理由なんてない。ただ、なんだから苛々するだけだ。綺麗事なんかどうでもいいのだ。そんなものあったって今生きている瞬間が幸せでいられるわけでもなし。ギリシェはおもむろに自分の掌を見つめる。何度も赤黒く生ぬるい液体で汚れてきたそれは、今は何事もなかったように白く滑らかだ。なんてくだらない。生まれ変わるとか役に立つとか還るとか、どうだっていい。少なくとも死んだら終わりなことだけがわかっている。それがすべてだ。
「帰ろうか」
ギリシェは言った。一体いつこの時間は終わるのかな、と思っていた。そろそろ限界だ。別にシンシアといた時間が嫌だったわけではない。ただ、漫然と時が一つの場所で過ぎていくのは大嫌いだった。温いものは大嫌いだ。痛いくらいでちょうどいい。痛覚が刺激されていれば満足だ。熱くても冷たくても。なんだっていいのだ。早く終われと思う。小さな時間の切片がとめどなく繋がり続けばいい。それでようやくギリシェは生きていると感じられる。死にたくはない。
シンシアはギリシェの顔を覗き込んで、頬をひっぱりやがった。
「何」
「怖い顔しているんだもの」
「怖い顔して何が悪いわけ」
「・・・悪かないかもだけど、なんか、こう」
シンシアの言葉は尻切れトンボになった。肩をすくめる。
「ほんと、変な子」
無理やり完結させた。ギリシェは今度こそため息をついた。
ふと、背中の内側を、斜めにざらりとした感触が走って行った。
―何だ?
それは、左の肩甲骨の辺りだったようにも思う。気色悪かった。つい振り返ったが、自分の背中が見えるわけがない。見えたのはピルミラの奥でぼんやりと透けるグリーグの翼だけだ。
もしも体を内側から誰かに撫でられたらこんな感覚なんだろうか、といい加減なことを考える。奇妙な違和感は脳に残り続けた。気色悪い。
「なんで君をここに連れてくる気になったかっていうとね、」
シンシアはギリシェの様子には気付かなかったようにのんびりと言葉を紡ぐ。
「最初は君のこと興味本位で覗いたんだ。だって、兄さんが最近下界に降りて行ったって聞いて、どうやら誰かを連れて帰ってきたらしいって噂で、何事だろうかと思って。もしも人に惚れた子でもいるんならからかってやろうとか顔拝んでみたいとか思ってさ、ほら、僕の友達にそういう子いるじゃない?」
―いや、いるじゃない、って言われても僕知らないから。
もはやつっこむのも面倒だ。
「でもまあ、男の子だったから、なんだ、って思って、やっぱり兄さんって研究にしか興味ないんだな、さっさと腰落ちつけろよこん畜生この目ざわりとか思ったわけなんだけどまあそれはいいとして、」
シンシアははあ、と深く嘆息する。
「わざわざこうして何者でもない人間をここに連れてくるのはありえないと思ったんだ。ということは何かしら君には重大な秘密があって・・・兄さんのもっぱらの興味と照らし合わせた結果、グリーグ様に関することに君がかかわりがあるんじゃないかって思って。僕もこう見えてあの鬼畜兄貴の弟だからね、馬鹿じゃないんだ」
「誰も馬鹿とは言ってないけど」
疲れたようにギリシェが言うと、シンシアはにっこりと笑う。
「で、もしもそうなら遅かれ早かれ、君がここに連れてこられる可能性もなくはないと思うんだ。あの人はグリーグ様のキチガイ信者だから、きっと君は何の知識もないままここに連れてこられても、兄さんに言いくるめられて、兄さん達に言いように使われてしまうんじゃないかと思って。だから連れてきた。まあ、僕がずっとずっと、ここをせっかく自力で見つけたのに誰にも自慢できなくて欲求不満がたまってたっていうのもあるけど」
「あんたさ、」
「シンシア」
「・・・とにかく、僕はあんた達鳥にとっては支配層、究極的にいえばただの僕で奴隷身分の人間なんだけど。特に僕はその中でも多分底辺以下の位置づけなわけ。なのにまるで、自分と同等扱いするんだな。なんで?」
「なんで名前で呼んでくれないの?」
「は・・・だから、僕が今聞きたいのはそういうことじゃ」
「呼んでよ。なんか気持ち悪い」
気持ち悪いのはこっちだと言いたい。ギリシェは下唇をかんだ。
「そもそも初対面のくせしてここまでだらだら話してたこと自体非常なんだよ。そこまであんたと僕は親しいわけでもないだろうが」
まあ少々親しいからって名前で呼んでやる義理もないのだが。基本的にギリシェは人の名前を覚えるのは苦手だ。そもそも覚えるのが好かなかった。今までも、名前はまるでただの物質名のように呼ばれてきた。他と区別するためにただ与えられただけの名前だ。ギリシェの名前を呼ぶ輩がどういう意図でギリシェを呼び利用してきたか思い出したくもないほどに知っていた。だからそういう奴らの名前を覚えたいとも思わない。自分の名前も嫌いなのに、どうして他人の名前を大事にしてやらねばならないのか。
「じゃあ、」
シンシアは喧嘩腰でつんけんとして言った。
「親しくなればちゃんと呼んでくれるね?僕の名前」
「は?」
そうきたか、とギリシェはさらに唇を噛みしめる。なんだか馬鹿らしくなってきた。
「そんな約束してやる義理ないんだけど」
「僕こそ君にそこまで拒否されるいわれはないよ。ほんっと失礼で常識のない人だね」
常識云々言えた立場かと言いたい。そもそもあんたは鳥で僕は人だ。常識なんかあっても同じとは限らないじゃないか。けれどその反論たちは、心の中だけにとどまった。本気で意地を張っていることが馬鹿らしくなった。そうして自分が、子供じみた意地を張っていたこともようやく自覚する。ギリシェは嘆息した。
「はぁ・・・シンシア、いいから僕の聞いたことに答えろって」
シンシアはにやりと笑った。つくづく嫌な奴だ。
「よし、一歩前進。次はシンシィって呼んでね。あ、シアでもいいよ」
「は?」
我ながら驚くほど低い声が出た。
「シンシィ、って前兄さんが可愛かった時僕をそう呼んでたんだよね。あの人今はシア、って呼んでる。僕はどっちでもいいよ。ここでは仲のいい子は愛称で呼ぶ決まりなんだ」
そもそもあんたと仲良くするつもりないから。あとここに長居する気もないから。
ギリシェは応対するのもおっくうになった。
そもそもここまで話がずれると、先の質問の答えをしつこく聞こうとするのさえ馬鹿らしいことに思えてきた。つくづく他人との会話は思い通りに効率よく進まず不便だ。そもそも目の前の相手は人ですらない。
頭が痛い。
「君のこと、そういう風に扱いたくないよ」
シンシアが静かな声で言う。
それが先のギリシェの言葉に対する返答であることに気付くのに少し時間を要した。
「それがなんでかっていうことをつまり僕は聞きたかったんだけどねえ」
もはや苛々した気持ちを隠す気も起きない。シンシアは肩をすくめた。
「うーん、僕にもよくわからないんだけど、なんていうか、僕初めて【羽なし】を見たからさ、よくわからないんだよね。しかも、文字通り羽がないだけで僕らとたいして変わらないじゃん。なんか親近感わいちゃって。僕と同じように、君ったら兄さんにひじょーに興味持たれてる立場みたいだし。他人の気がしないって言うかさ」
「僕は他人の気しかしないな」
「まあ、そう言わないでよ。ていうかそろそろ戻った方がいいかな。よく考えたら君がいないことに誰か気付いたらまずいよね。ま、さっきみたいに兄さんが人払いしたら、少なくとも半刻は誰も部屋に入ろうとはしないだろうけどさ」
シンシアはにこにこしながら言った。一つの木に近付き、根元に片膝を立ててかがむ。よく育った根の一本を、ひょい、と持ち上げた。まるで軟体動物のようにくにゃりと動かされたそれに、ギリシェも多少驚く。シンシアはその下に在った灰色の石をぐい、と押した。途端に勢いよく木が黄色と橙色の光の交錯する線で網状に下から上へと覆われていく。
シンシアは、そっとギリシェの手をとった。
「さあ帰るよ。君、もう少し寝ててもらわないとね。兄さんにばれたら後が大変だ」
触れている手を、嫌だとは思わなかった。ギリシェはいつの間にか、軽く引かれただけの手のままに付いていっていた。網に近付くと、少しだけ網目がほぐれて、光も薄くなった。シンシアがそのまま中に入って見えなくなったので、ギリシェもそのまま後に続く。
キン、という音がして、また視界が反転した。シンシアが羽で自分とギリシェをくるみこんだ。耳の奥まで入り込んでくる機械音のような奇妙な音は相変わらず耳障りだし、目もちかちかして非常に不快だ。けれど来た時ほど自分の体も強張ってはいなかった。慣れたのかもしれない。この装置にも、世界にも、そして、この一見人畜無害そうでそうでもなさそうな少年にも。
ギリシェはそのまま目を閉じた。頭が痛いし体はだるい。まだ本調子ではないらしい。あの暗闇は、よほどギリシェの体力を削ぎ落としていたようだ。
芳しい緑の匂いが遠ざかっていく。
非常に不快だった。
まず、温い。そしてちりちりと耳障りな音がする。
言うなれば腹から嚥下したとき口まで上ってくる胃液の中に体をびしょ濡れにされたような感覚だった。目を見開くこともできなかったけれど閉じ切ることもなんだかできず、そうしているうちに角膜の上を金色と灰色の針金のような光の点線がひどく忙しなく縦に横に斜めに螺旋を描いて動いた。それを見ていただけで気分が悪くなった。そして何より音だ。脳髄にまでじんじんと響いてくるから、耳を塞いだところでほぼ意味はない。ちり、ぎり、がり、とまるで金属で金属を削るようなキーキーとした音がとぎれとぎれにのろのろと鳴った。それらがすべて自分達を包み込んだ。世界は水色と黄色。ところどころ意味のわからない赤橙と橙の色をした球体のような円盤のような半透明のものがぴょんぴょん飛んで行った。
そう長い時間ではなかったのかもしれないけれど、十分にギリシェにとっては疲労の材料になった。
空間が巻貝のようにぐるぐると絞り上げられ、先端の方へ二人は吸いこまれていく。痛くはなかった。自分の周りにねっとりと纏わりついていた温い液体のようなものが体からしぼりとられていくようで、ようやくすう、と息ができたような心地がした。ギリシェは大きくため息をついた。ため息がこんなにも気持ちの良いものだとはついぞ知らなんだ。これからは大いに息を吐くとしよう。
「着いたよー。あはは、相変わらず気色悪かった!」
薄青の髪の少年は妙にすっきりした顔もちで言った。ギリシェは一瞬何を言われたのかわからなくて、止まる。
自分もあまり気持ちよくないなら何故にこの移動手段を使うのかと問いたくないこともなかった。ぐっとこらえる。面倒な会話で時間が浪費されるのは疲れるから嫌いだ。
まずは状況を判断しよう、とギリシェは辺りを見渡した。黙ってそうするのは一種の癖だ。人にいちいち分からないことを聞くのはあまり好きではなかった。わずらわしいからだ。自分の目で見て知ることができることは、意外と多いものだ。もしよくわからなくてもそれは今の自分にはきっと必要がないから分からないのだ。それがギリシェの信条のようなものだった。分からないものは目に焼き付けておけばいい。いつかそれが必要になった時に、それが何だったのかきっと分かるだろう。そう思っている。
一面は緑の森だ。青緑の瑞々しく肉厚な葉の茂った木が地面中に根を張っている。普通の木と違うところ言えば、根にもまた葉がまるで蔦や蔓草の類のように茂っているということだろうか。おかげで地上で見られる草のようなものはないけれど、十分に地面も緑に覆われている。
そして不自然に、ぽっかりと空いた、いや、空けられた空間がある。作為的にも見えるよく伸びた三つの木の枝が絡み合って網をつくり、屋根になっている。その下でその格子の影を映しているのはやや茶色がかった黄色の四角錐の大きな物体だった。その全ての辺と中線もまた、先刻奇妙な空間で見たものとよく似た、赤みのある金色の点線状の光の通路になっている。そしてその四角錐の周りの地面に、ぽつぽつと長方形の白金の薄板が刺さっている。まるで規則性がない並びのように見えて目を細めたら、実はそれらの板は四角錐の建物を中心に据えた見えない正方形の辺上にきちんと立っているのだとわかった。それがわかって改めて眺めると、不整合に見えたそれらの構造が実は綿密な計算のもとに配置されているのだと分かる。地上ではまず見ない様式美だ。少なくとも地上の人間達は均等を好む。対称なものを美しいと直感的に感じる。今目の前にある建築物は、全体としてみれば点対称ですらない。
そして、妙に静かだった。風ひとつ吹いていないのだ。空気はあるはずなのに、居心地が悪くなるような静けさだ。身動きをして音を立ててはいけないかのような心地になる。
意味が分からなかった。結局分かるのは、地上とこの羽のある生物たちの暮らす環境は似ているようで実は全然違うのであろうということ、そして美しいようでどこか怖いものなのだと肌で感じ取れるだけ。
「ここはピルミラ。グリーグ様の社だよ」
少年が、それをじっと見つめながらささやく。
だからグリーグって誰だよ、と思う。鳥達の常識を自分のようなただの人間も当然のように持っているように思わないでほしい。父親なら知っていたかもしれないな、と頭の中で言葉がかすっていって、ギリシェはかぶりを振った。どうでもいいことだ。自分は知らない。それが事実だ。あと、耳元で話すのやめてほしい。
「グリーグ様はもう亡くなってるから、今は誰も住んでないんだけど、ただ、多分ここは保管庫なんだと思う。上の人たちは、文化的遺産であるグリーグ様の住まいの永久的保護のために立ち入り禁止、だなんて言ってるけど、現にあの人たち結構ここにちょこちょこ達言ってるみたいだし、それは多分詭弁だよね。多分、【あれ】を保護してるんだ、ここで。腐らないように」
―【あれ】、ねえ。
だからなんだよ、と思ったりしなくもない。そんなことを自分に話したところでさっぱり意味が分からないのだから非常に不毛だ。無駄だ。
溜息でもつこうかな、と思ったがやめておくことにした。わざわざ人前でするものでもない。あとあと面倒だ。自分はなるべく透明に生きていきたいのだ。
まあ、もう少し人並みに生きていてもいいなら、の話だが。
「多分、【それ】をここから出しちゃいけないのと、僕が外を歩いちゃいけない理由はつながっているんだと思うんだけど、いかんせん兄さんに聞くわけにもいかないから、ばれちゃうから、僕には未だに痒いところに手が届かない気持ちってこういうことなのかなって」
先刻から筋の通らない言葉遣いなやつだな、とギリシェは思った。そうしてふと、なんでこいつら、羽があるのに歩くんだろう、と思ったりした。そういえばキシュキと名乗った青年も女中も羽があるくせに床をぺたぺたと歩いていたように記憶している。
ふと、少年は不思議そうにギリシェの顔を覗き込んだ。いちいち距離が近い。まあだからと言ってひるむわけでもないのだが。少々のことでは動じない癖がついてしまっている。
「君、変な子」
「は?」
つい相手をしてしまった。
「だって、さっきからずっと取り乱すこともなくだんまりなんだもん。臆してるわけじゃないんだよね?人ってみんなそうなの?」
「さあ」
「さあって」
「僕に人類一般の傾向を語れと言われてもな。言うほど経験積んでないもん」
「そうなの?」
ふーん、と少年は一人で納得したようだった。そうして唐突ににっこりと嬉しそうな笑顔を浮かべる。
何、と思ったりする。
「えへへ、でもなんだか楽だな!僕が一人でしゃべってても変な空気にならないしね!やっぱり相手がいるっていいことだよね。一人きりの時ぶつぶつ独り言言っててたまに無性に恥ずかしくなる時あるんだよね」
そこまできちんと耳を傾けてもいないんだけど、と心の中でだけ応対して、ギリシェはそのまま四角錐の方へ視線を戻した。
なんだろう。最初の衝撃が薄れると、だんだん愛着がわいてくるというか、この形がどこか可愛いものに思えてくる。何の変哲もない図形の塊なのに、奇妙な感覚なことだ。
上手い言葉が見つからないけれど、少なくとも警戒心があおられたりはしない。この場所にいると、神経を張り詰めようとする気が削がれていく。
「あのね、ちょっとついてきてよ」
少年はさらりと言うと、そのままピルミラの方へ近づいていく。その足取りを見ながら、やっぱり人よりも足取りに重さがないんだな、とギリシェは少しだけ思う。
着いていかない理由もないけれどついていかなければならない理屈もないんだけどな、などと思いながらギリシェは大人しくその後ろを着いて行った。
「ほら、こっち。ここまで寄ってみて」
少年は手招きする。ピルミラの壁にぴったりと鼻と手を寄せて中を食い入るように見る。
ギリシェも、さすがにそこまではしなかったが少年の肩の後ろから覗いてみた。
離れた所からは分からなかったが、ピルミラの壁は透明で、中が見えるようになっていた。点線の光がちらちらとせわしなく動いて交錯するので鬱陶しかったりする。
けれど、その光達が載る物、内部の中央に浮かんでいるそれは、綺麗だと思った。
片翼だ。
はっきりとした色は壁の色に透かされてよくわからないけれど、光沢や影の度合いでかなりいろんな色の混じった翼なのだろうとは分かった。朱子織のようになめらかで柔らかそうだ。こうして見るだけでも、収集品に興味のないギリシェでさえ惹きつけられるものがある。魅入るとでも言うのだろうか。
「あれ?」
ギリシェはふと呟いた。よく考えてみれば、その翼はキシュキ達のような翼とは全く違うものだ。どちらかと言えば―美しさは劣るにしても―目の前にいるこの線の細い少年の翼に近い。
「鳥の翼ってやつは、いろんな種類があるんだな」
ギリシェは多分、少年に対しては初めて自分から声をかけてみる。
少年は目を丸くして振り返る。しばらくじっとギリシェの目を見つめた後、なぜか顔を赤らめてうつむいた。何故そこではにかむ必要があるのかギリシェにはよく分からない。奇妙奇天烈とはこのことだな、と呑気にそんなことを考える。
「僕のは・・・ううん、違うんだ、僕のは、ちょっと、特別なんだ。特別っていうか、奇形と言った方が正しいんじゃないかな・・・あ、グリーグ様の翼が奇形だなんて言ってないよ!?だってグリーグ様はあの翼でちゃんと飛べた。僕は飛べない。あんなに美しくもない。だから僕は多分奇形だ」
少年はぼそぼそと言う。どこか覇気がなかった。
まあ絶対に気にかけなければいけないことでもないはずなので、とりあえずギリシェは頭の中で少年の発言を整理する。
察するに、このピルミラの中にある翼はグリーグという奴の翼と言うことだろうか。そして、様と呼ばれるからにはなかなか立場の偉い人物なのだろう。そういえばもう死んだとか言っていたような気がする。つまり翼を片方だけぶった切ってここに押し込んでいるということか。見た目は綺麗だが意外と鳥達も残酷な―いや、思い切ったことをするもんなんだな、と少しだけ思う。少なくとも自分の知っている限りでは、地上の人間は敬意を表している相手の体を切断したりはしないはずだ。
ギリシェは少年の髪色と同じ柔らかで薄い翼をじっと眺めた。奇形、ねえ。
たしかにまるで女の服みたいな布が申し訳程度についているくらいのようなものだから、あってもなくてもよさそうだとも思う。けれど同時に純粋に綺麗だとも思った。もしも少年の背からこのなめらかな布のような翼がなくなってしまったら、なんだか心もとない感じだ。この翼があるから少年は鳥なのだ。人のような何の変哲もない生き物ではない。美しいものなのだ。大鷲のような翼も似合っただろうとは思うけれど、この翼は個人的に嫌いではない。
何か言った方がいいかと思って言葉を探す。けれど、変に慰めていると受け取られたくはない。単に思ったことを言いたくなっただけなのだから。
結局、何を言っても嘘くさくなりそうで、ギリシェは黙って少年の頭を撫でた。翼に触れようかとも思ったが、知覚はあるはずだ。下手に触って痛かったらよくない。
少年は戸惑ったように身をすくめていたが、やがて肩の力を抜いた。まるで野良猫を懐かせたような気分になる。
「ほんとはね、」
少年はグリーグの翼であろうものに視線を戻して静かに続けた。
「僕は自分のこの羽に、劣等感を、みじめさを感じてもいるし、ちょっと酔ってもいるんだ。
「僕のこの翼だけが、グリーグ様のものとそっくりで、他の【鳥】たちはみんなただの鳥と同じものしか持っていない。僕が自分を卑下するのもただの申し訳で、本当は心の奥底で、自己満足してるよ。だって僕の翼はグリーグ様と同じなんだ。みんなよりもずっと綺麗だし希少価値があって。だけどこんな風におごっている自分が気持ちよくもあるけど嫌いでもあるんだ。だから僕は人前では自分を卑下しないではいられないし、自分を奇形だって言わずにはいられない。自分で言って自分で傷ついて、一人になった時に自分に言い訳するんだ。だけど僕は綺麗な子だからいいんだって。慰めるみたいにさ。だけど僕は・・・綺麗なものになりたいんじゃなくて、かっこよくなりたいんだ。女みたいに儚いって言われても全然嬉しくなかったよ。僕は男らしくなりたいだけなんだけどな。骨太っていうかさ。兄さんは趣味がちょっとおかしいからなぁ。線が細けりゃいいって思ってる」
少年は、小さく嘆息した。中腰になっていた体を起こす。
「うん、満足した。聞いてくれてありがとう」
ギリシェは少しだけ顔をしかめた。礼を言われるのはなんだか居心地が悪い。言われ慣れていないのだ。なんだか腹立つし、妙な気持ちになる。
ギリシェは自分が捻くれているのは重々承知している。だから謝られるのと同じくらい礼を言われるのはあまり好きじゃない、つまりそういうことだ。どちらの行為も単なる本人の自己完結の手段にしか感じられないからだ。けれど、今は、この少年に素直に自己完結させてやってもいいかな、と思った。彼はこう言うことできっと、ゆらぐ細い自分を支えるのだろう。いつものギリシェなら、礼を言われるのは好かない、くらいはつい言ってしまうけれど。
「あれね、」
少年はグリーグの翼を指差す。
「片方しかないでしょ?もう片方はね、転生に使ったらしいんだよね」
「転生?」
「生まれ変わる、ってこと。僕達の魂は、君達もきっとそうだと思うけれど、この体の成分すべてが一つの魂を構成しているんだ。魂は光から生まれて光に還る。ほら、あの太陽」
少年は梢から微かに見える、世界の昼を照らす丸い光を指差した。
「【人々】の死生観がどうなってるのかはよく知らないけどさ、この世で生きていると、魂は汚れも吸っていくんだ。だから老いて行くし、いつかは摩耗して死んでしまう。だけど生まれ変わって、もう一度同じ存在になることはできる。死ぬ時は体のすべてを太陽にお返しするんだよ。あそこでもう一度綺麗に体を掃除してもらって、もう一回生まれてくる。だけど、体の何かを失ったままだったり、逆に要らないものを持っていってしまうと少しずつ違うものが魂に混じっていくんだ。生まれ変わった時、前とは違う魂になってしまってる。別人になるんだ。だから僕達鳥は、体の全てを必ず太陽に還す。火葬する人々がかわいそうだな、ってときどき思うよ。君達は必ず魂を構成する何かを無くしたまま生まれ変わっていくから、きっといつかは魂もなくなっちゃって、何者にもなれなくなるんだろうね。世界から消えてしまうんだろう。
「まあ、それはいいとして、とにかく、普通は両翼含めて体全部使って生まれ変わるのに、なぜかグリーグ様はああして羽を片方だけ残していったんだ。理由は僕にはよくわからないんだけど・・・なんでなんだろう。だけどこうして鮮度を保つようにこの中に閉じ込めているってことはね、きっとまた何かに使うつもりなんだ。多分・・・生まれ変わってきた子に役立てるんだと思う」
少年は口元に手を置いて何事か考え込む。
「ただこの辺は機密事項らしくて外部には漏らされてないし、僕もこれを見て初めてその可能性を思いついただけだから、全然分かんないんだけど」
なんでそういう重要なことをよそ者の僕に話してんの?という突っ込みはしないほうがいいんだろうな、とギリシェは心の中でだけ思う。そもそも、ここに自分を連れてきている時点で非常におかしい。見れて悪かったとは思わないけれど、どうしてこの少年は自分にこれを見せたのだろうかと思わずにはいられない。
とはいえ、見せられて見てしまったもの、聞いてしまったものはもうどうしようもないのだから、ギリシェはそれ以上は深く追求しないでおくことにした。ギリシェが黙っていると、少年は困ったように微笑んだ。
「ほんと、変な子だね、何で僕が君にこれを見せたかって聞かないの?」
―ああ、これは聞かなきゃいけなかったわけ。
人との対話は加減が難しいな、と思いながら心の中でだけ嘆息した。
「見てしまったものをなかったことに出来るわけじゃないだろ」
思ったままを答えると、少年は吹き出した。
「まあ、そう、だけどさ!」
くすくすと笑いをこらえている。
「なんだかものすごく君面白いね。おおらかだね!なんだか新鮮」
「いや、多分僕が普通より変わってるだけだから」
自分が人間一般に対して思いやる必要はないのだけれど、一応申し訳程度に言い訳をしておく。少なくともギリシェ自身は自分が一般的な感覚を持てていないことくらいは認識できている。
「鳥にもいないよ、君みたいなの」
少年はにっこり笑った。
「あ、そうだ、名前聞いてなかったや。なんて言うの?僕はシンシア。さっき君に気色悪く迫ってたキシュキってやつの弟なんだ」
「似てないな、顔が」
「顔以外は似てるって言いたいの?心外なんだけどちょっと」
シンシアは少し口をとがらせる。男らしくなりたいと言った傍からその仕草はどうなのだろうと少し思ったりする。
「兄さんには気をつけてね。あの人自分の研究しか頭にないから、目をつけられてる君は相当執着されるはずだよ、なんの目的かは知らないけどさ」
シンシアはあさっての方向を見たまま言った。
「僕はギリシェ。見ての通り人」
シンシアはまた吹き出した。
とりあえず放っておいて、改めてギリシェは自分の周りの世界を見渡してみた。
瞼を閉じても、その裏側に陽の光を透かして緑の色が映り揺れる。緑は嫌いじゃなかった。自分が溶け込める気がする。誰にも見つかることもなく、誰にも邪魔されることなく。
ただ静かに暮らしたいだけだ。それだけだ。誰と関わりたいわけでもない。
とはいえ、シンシアとの最初は不毛に思えた会話も、意外と楽しかったかなと思ったりした。
「人間は火葬したり土葬したり水葬したり、いろいろするけど」
ギリシェはふと、これだけは言っておこうと思って口を開く。
「僕の生まれた地方では土葬だったから他のことはよくは知らないけどさ、多分目的は一緒だと思う。土葬することで、体が土に還る、って考え方。大地の一部になるんだ。自然の一部になって、循環して、命が廻る。そういう考え方をしてる。だから多分、根本的に死生観はやっぱり違うんだと思う」
シンシアは戸惑ったように眉をひそめた。
「何それ。自然になって満足してるの?それって自己満足じゃない?元々あった自然の、土や木や風たちのありようをそうすることで少しずつ変えていってるってことでしょう?いつか摩耗しちゃうよ。人ったらなんてもったいないことをするんだろ」
「そもそもたしか、自然っていう大きな塊の一部が人間になったって考え方じゃなかったっけな」
ギリシェは記憶を頼りに呟く。聖書の暗記をさせられたのなんて物心がつくかつかないかのことだから、うろ覚えだ。
「だから、多分それで摩耗したりはしない。むしろ世界のあるがままに直してるつもりだと思う。人は全体的に捉えてるんだろ。で、あんた達は個を捉えてるってこと。僕から言わせれば結局どっちも自己本位で自己満足な結論のように思うけど」
「なぜ?」
シンシアが不安そうに小さな声で問う。
ギリシェは答えなかった。特に理由なんてない。ただ、なんだから苛々するだけだ。綺麗事なんかどうでもいいのだ。そんなものあったって今生きている瞬間が幸せでいられるわけでもなし。ギリシェはおもむろに自分の掌を見つめる。何度も赤黒く生ぬるい液体で汚れてきたそれは、今は何事もなかったように白く滑らかだ。なんてくだらない。生まれ変わるとか役に立つとか還るとか、どうだっていい。少なくとも死んだら終わりなことだけがわかっている。それがすべてだ。
「帰ろうか」
ギリシェは言った。一体いつこの時間は終わるのかな、と思っていた。そろそろ限界だ。別にシンシアといた時間が嫌だったわけではない。ただ、漫然と時が一つの場所で過ぎていくのは大嫌いだった。温いものは大嫌いだ。痛いくらいでちょうどいい。痛覚が刺激されていれば満足だ。熱くても冷たくても。なんだっていいのだ。早く終われと思う。小さな時間の切片がとめどなく繋がり続けばいい。それでようやくギリシェは生きていると感じられる。死にたくはない。
シンシアはギリシェの顔を覗き込んで、頬をひっぱりやがった。
「何」
「怖い顔しているんだもの」
「怖い顔して何が悪いわけ」
「・・・悪かないかもだけど、なんか、こう」
シンシアの言葉は尻切れトンボになった。肩をすくめる。
「ほんと、変な子」
無理やり完結させた。ギリシェは今度こそため息をついた。
ふと、背中の内側を、斜めにざらりとした感触が走って行った。
―何だ?
それは、左の肩甲骨の辺りだったようにも思う。気色悪かった。つい振り返ったが、自分の背中が見えるわけがない。見えたのはピルミラの奥でぼんやりと透けるグリーグの翼だけだ。
もしも体を内側から誰かに撫でられたらこんな感覚なんだろうか、といい加減なことを考える。奇妙な違和感は脳に残り続けた。気色悪い。
「なんで君をここに連れてくる気になったかっていうとね、」
シンシアはギリシェの様子には気付かなかったようにのんびりと言葉を紡ぐ。
「最初は君のこと興味本位で覗いたんだ。だって、兄さんが最近下界に降りて行ったって聞いて、どうやら誰かを連れて帰ってきたらしいって噂で、何事だろうかと思って。もしも人に惚れた子でもいるんならからかってやろうとか顔拝んでみたいとか思ってさ、ほら、僕の友達にそういう子いるじゃない?」
―いや、いるじゃない、って言われても僕知らないから。
もはやつっこむのも面倒だ。
「でもまあ、男の子だったから、なんだ、って思って、やっぱり兄さんって研究にしか興味ないんだな、さっさと腰落ちつけろよこん畜生この目ざわりとか思ったわけなんだけどまあそれはいいとして、」
シンシアははあ、と深く嘆息する。
「わざわざこうして何者でもない人間をここに連れてくるのはありえないと思ったんだ。ということは何かしら君には重大な秘密があって・・・兄さんのもっぱらの興味と照らし合わせた結果、グリーグ様に関することに君がかかわりがあるんじゃないかって思って。僕もこう見えてあの鬼畜兄貴の弟だからね、馬鹿じゃないんだ」
「誰も馬鹿とは言ってないけど」
疲れたようにギリシェが言うと、シンシアはにっこりと笑う。
「で、もしもそうなら遅かれ早かれ、君がここに連れてこられる可能性もなくはないと思うんだ。あの人はグリーグ様のキチガイ信者だから、きっと君は何の知識もないままここに連れてこられても、兄さんに言いくるめられて、兄さん達に言いように使われてしまうんじゃないかと思って。だから連れてきた。まあ、僕がずっとずっと、ここをせっかく自力で見つけたのに誰にも自慢できなくて欲求不満がたまってたっていうのもあるけど」
「あんたさ、」
「シンシア」
「・・・とにかく、僕はあんた達鳥にとっては支配層、究極的にいえばただの僕で奴隷身分の人間なんだけど。特に僕はその中でも多分底辺以下の位置づけなわけ。なのにまるで、自分と同等扱いするんだな。なんで?」
「なんで名前で呼んでくれないの?」
「は・・・だから、僕が今聞きたいのはそういうことじゃ」
「呼んでよ。なんか気持ち悪い」
気持ち悪いのはこっちだと言いたい。ギリシェは下唇をかんだ。
「そもそも初対面のくせしてここまでだらだら話してたこと自体非常なんだよ。そこまであんたと僕は親しいわけでもないだろうが」
まあ少々親しいからって名前で呼んでやる義理もないのだが。基本的にギリシェは人の名前を覚えるのは苦手だ。そもそも覚えるのが好かなかった。今までも、名前はまるでただの物質名のように呼ばれてきた。他と区別するためにただ与えられただけの名前だ。ギリシェの名前を呼ぶ輩がどういう意図でギリシェを呼び利用してきたか思い出したくもないほどに知っていた。だからそういう奴らの名前を覚えたいとも思わない。自分の名前も嫌いなのに、どうして他人の名前を大事にしてやらねばならないのか。
「じゃあ、」
シンシアは喧嘩腰でつんけんとして言った。
「親しくなればちゃんと呼んでくれるね?僕の名前」
「は?」
そうきたか、とギリシェはさらに唇を噛みしめる。なんだか馬鹿らしくなってきた。
「そんな約束してやる義理ないんだけど」
「僕こそ君にそこまで拒否されるいわれはないよ。ほんっと失礼で常識のない人だね」
常識云々言えた立場かと言いたい。そもそもあんたは鳥で僕は人だ。常識なんかあっても同じとは限らないじゃないか。けれどその反論たちは、心の中だけにとどまった。本気で意地を張っていることが馬鹿らしくなった。そうして自分が、子供じみた意地を張っていたこともようやく自覚する。ギリシェは嘆息した。
「はぁ・・・シンシア、いいから僕の聞いたことに答えろって」
シンシアはにやりと笑った。つくづく嫌な奴だ。
「よし、一歩前進。次はシンシィって呼んでね。あ、シアでもいいよ」
「は?」
我ながら驚くほど低い声が出た。
「シンシィ、って前兄さんが可愛かった時僕をそう呼んでたんだよね。あの人今はシア、って呼んでる。僕はどっちでもいいよ。ここでは仲のいい子は愛称で呼ぶ決まりなんだ」
そもそもあんたと仲良くするつもりないから。あとここに長居する気もないから。
ギリシェは応対するのもおっくうになった。
そもそもここまで話がずれると、先の質問の答えをしつこく聞こうとするのさえ馬鹿らしいことに思えてきた。つくづく他人との会話は思い通りに効率よく進まず不便だ。そもそも目の前の相手は人ですらない。
頭が痛い。
「君のこと、そういう風に扱いたくないよ」
シンシアが静かな声で言う。
それが先のギリシェの言葉に対する返答であることに気付くのに少し時間を要した。
「それがなんでかっていうことをつまり僕は聞きたかったんだけどねえ」
もはや苛々した気持ちを隠す気も起きない。シンシアは肩をすくめた。
「うーん、僕にもよくわからないんだけど、なんていうか、僕初めて【羽なし】を見たからさ、よくわからないんだよね。しかも、文字通り羽がないだけで僕らとたいして変わらないじゃん。なんか親近感わいちゃって。僕と同じように、君ったら兄さんにひじょーに興味持たれてる立場みたいだし。他人の気がしないって言うかさ」
「僕は他人の気しかしないな」
「まあ、そう言わないでよ。ていうかそろそろ戻った方がいいかな。よく考えたら君がいないことに誰か気付いたらまずいよね。ま、さっきみたいに兄さんが人払いしたら、少なくとも半刻は誰も部屋に入ろうとはしないだろうけどさ」
シンシアはにこにこしながら言った。一つの木に近付き、根元に片膝を立ててかがむ。よく育った根の一本を、ひょい、と持ち上げた。まるで軟体動物のようにくにゃりと動かされたそれに、ギリシェも多少驚く。シンシアはその下に在った灰色の石をぐい、と押した。途端に勢いよく木が黄色と橙色の光の交錯する線で網状に下から上へと覆われていく。
シンシアは、そっとギリシェの手をとった。
「さあ帰るよ。君、もう少し寝ててもらわないとね。兄さんにばれたら後が大変だ」
触れている手を、嫌だとは思わなかった。ギリシェはいつの間にか、軽く引かれただけの手のままに付いていっていた。網に近付くと、少しだけ網目がほぐれて、光も薄くなった。シンシアがそのまま中に入って見えなくなったので、ギリシェもそのまま後に続く。
キン、という音がして、また視界が反転した。シンシアが羽で自分とギリシェをくるみこんだ。耳の奥まで入り込んでくる機械音のような奇妙な音は相変わらず耳障りだし、目もちかちかして非常に不快だ。けれど来た時ほど自分の体も強張ってはいなかった。慣れたのかもしれない。この装置にも、世界にも、そして、この一見人畜無害そうでそうでもなさそうな少年にも。
ギリシェはそのまま目を閉じた。頭が痛いし体はだるい。まだ本調子ではないらしい。あの暗闇は、よほどギリシェの体力を削ぎ落としていたようだ。
芳しい緑の匂いが遠ざかっていく。
PR
カレンダー
| 03 | 2024/04 | 05 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
リンク
カテゴリー
フリーエリア
最新CM
最新記事
(12/01)
(11/28)
(09/21)
(08/10)
(08/10)
(08/10)
(08/09)
(08/09)
(07/14)
最新TB
プロフィール
バーコード
RSS
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事
(07/14)
(08/09)
(08/09)
(08/10)
(08/10)
(08/10)
(09/21)
(11/28)
(12/01)
P R